映画は闇の中に照らし出される光。その光が純粋かつパワフルであれば、映画館を出た後も人の心にすみついて世界を照らし出す。では、どうすればそんな映画がつくれるのか。「狂い咲きサンダーロード」(1980年)などで知られる石井岳龍監督による「自分革命映画闘争」は、映画創作の光源に手を伸ばす者たちの冒険を描く。石井監督自ら演じる、映画を教える大学教授の乱心から始まる型破りな活劇だ。(編集委員 恩田泰子)
2006年からこの3月まで石井監督が教授を務めてきた神戸芸術工科大学映画コースの学生・教員らとともに作った映画で、全員がスタッフ兼出演者。この映画の物語の中で自分自身を演じている。要するに、虚実皮膜をゆく映画。スポンサーなしの完全自主製作で、石井監督の大学での映画創作研究活動の集大成であり、番外映画創作授業でもある。
冒頭、「石井岳龍教授」は「狂的状況」に陥り、「個の想像力や認識の拡張、意志の強化を目指す内意識革命のためのワークテキスト」なるものを残して失踪する。同僚の「武田助教」(武田峻彦、撮影・照明・編集・VFXも担当)は学生たちとともに「ワーク」の実践を試みることにするが、それはまるで映画体験がそうであるように、彼らの世界をひらき、内面を照らし出していく。
普通の映画ではない。常軌を逸した「石井教授」の挙動。場面ごとに色を変え、サスペンス、コメディ、ミュージカル、不条理劇、アクションとあらゆるジャンルの魅力をはらんで転がっていく内容。前半と後半の分断されているようで地続きの関係――。そうしたカオスを面白がっているうちに、思いがけない境地に連れていかれる。
この映画は、今の時代の空気を濃厚に帯びている。登場人物たちの多くからは私たちと同じにおいがする。多かれ少なかれ、
でも光源は、自分自身の中にあるのではないか。映画はそれと向き合うきっかけになるのではないか。映画のエッセンスとの交信をはかるかのような奇妙なワークを実践しながら、自らと向き合い、覚醒していく登場人物たちの物語は、実は、観客にとってもひとごとではない。
石井監督は、日本大学芸術学部映画学科入学後に撮った8ミリ映画「高校大パニック」(1976年)で映画界に衝撃・刺激を与えて以来、前作「パンク侍、切られて候」(2018年)に至るまで、己のいる世界(それは観客がいる世界でもある)と格闘する人間をさまざまな形でスリリングに描いてきた。今作もしかり。
しかも、その石井ユニバースの構成元素をたっぷりと見せている。それは、映画史の中で重ねられてきた名作たちの色あせぬ力であり、そうした映画と我知らず共振する「自分自身」のものがたり。その真価を学生らの顔・体を通してドキュメントし、実証するかのような映画でもある。
映画に向き合って自分の中に革命を起こし、終幕、映画の現場で黒いものたちとの闘争を描き出していく彼らの姿に、じんとくる。最初は怪しく見えた身体ワークの動作が、こよなく美しく思えてくる。
時折、ふっとあらわれるロックな横文字、偉大な先人たちをめぐる聖なる書を抱きしめる女子の姿など、石井監督の映画への思いがこれでもかと詰め込まれている。それが過剰に思えないのは、映画の力を伝えたい、生かしたいという願いが、恐ろしいほど澄んでいて、尋常でなく切実だからだろう。学生たちのそばにすっくと立つ木が心に残る。
◇自分革命映画闘争=2023年/165分/製作・監督・脚本:石井岳龍=3月18日から神戸・元町映画館で先行公開、同25日から東京・渋谷のユーロスペースで公開。
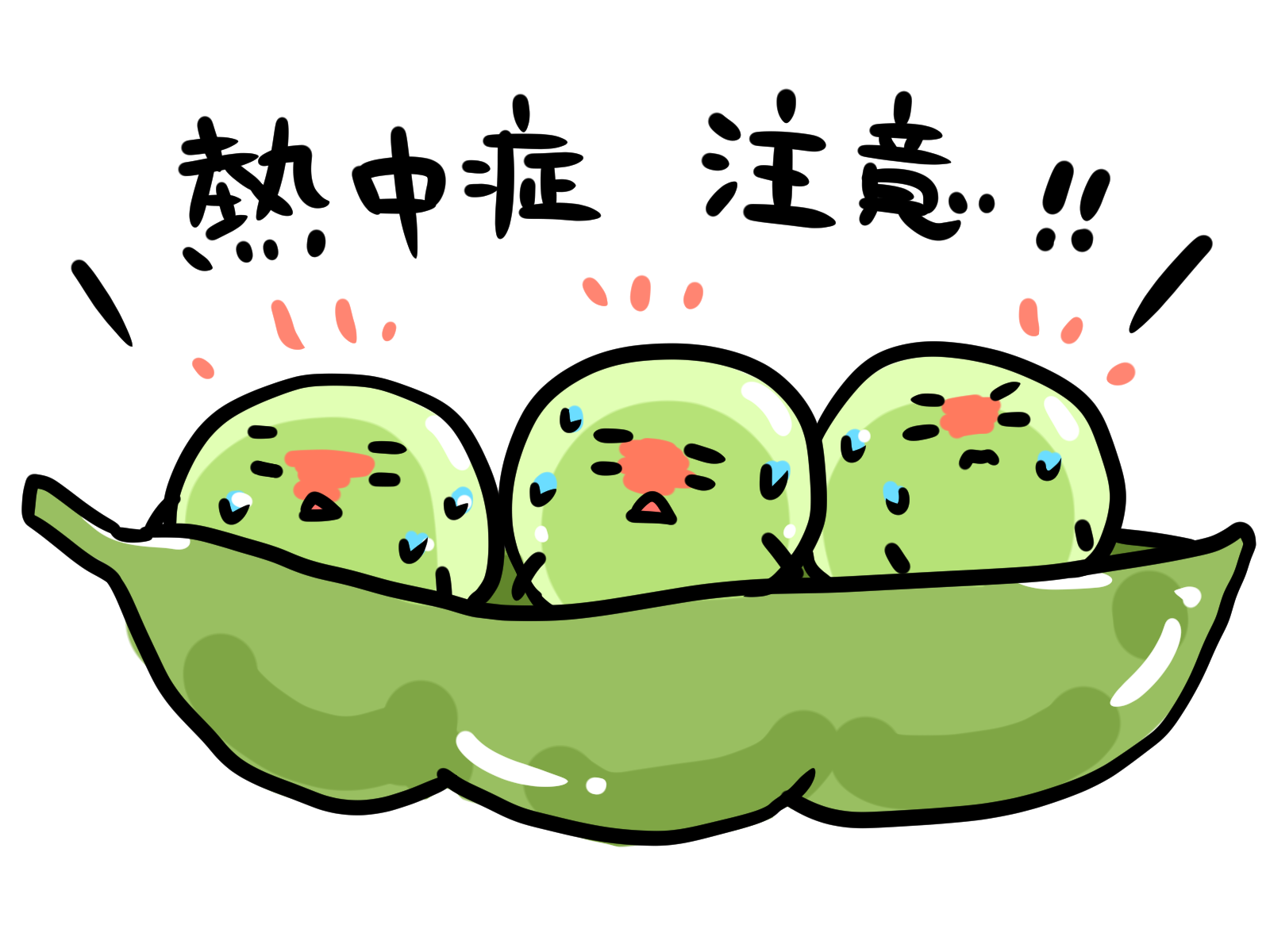


![[映画評]「自分革命映画闘争」…石井岳龍教授による尋常ならざる番外映画創作授業](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/yomiuri/s_20230316-567-OYT1T50310.jpg)









