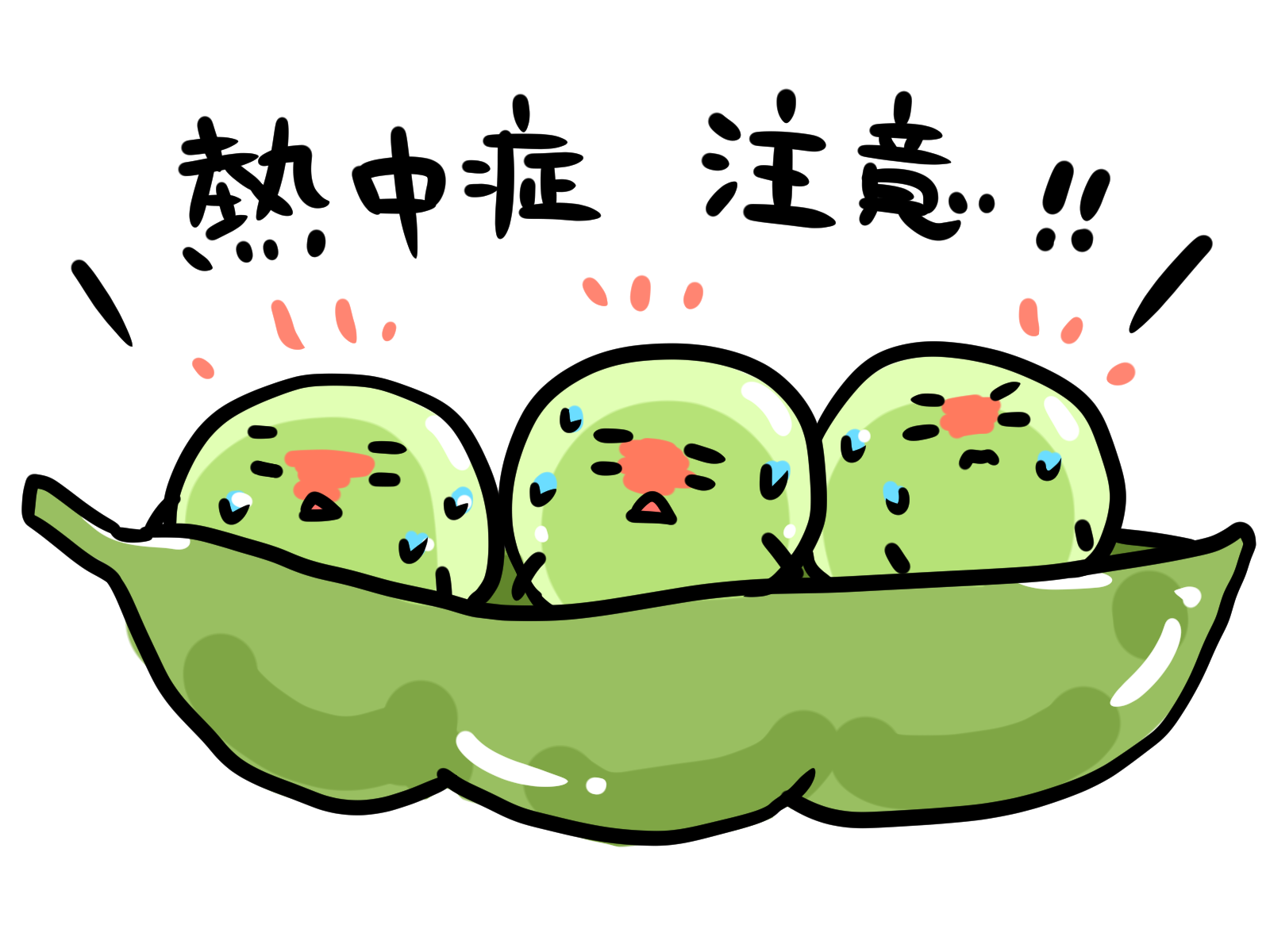『夜を走る』の映画的な美点はたくさんあるが、筆頭に挙げられるのは作品のルックや画面の構図が極めて洗練されているところだろう。また、台詞が聞き取りにくくなるようなやかましくて間の抜けた劇伴も鳴らないし、もちろんエンドロールで野暮なロックや変なJ-POPが流れたりしない。つまり、この作品には普通の日本映画っぽいところや、ありがちなインディーズ映画っぽいところがどこにもないのだ。それを聞いただけで、「それなら観てみようかな」と思う映画ファンも多いのではないだろうか。
『夜を走る』では、どこにでもいそうな”いい顔”をした役者たちが、我々の日常の延長線上のどこにでもある世界で実体をともなって”生活”をしていて、ふとしたきっかけで道を踏み外していく。特に後半に入ると、その道の踏み外し方が、「ブレイキング・バッド」や「FARGO/ファーゴ」のような最上級の海外テレビシリーズを彷彿とさせるほど、予想のつかない展開が連続していく。めちゃくちゃリアルなのに、めちゃくちゃぶっ飛んでいる。要は、文句なしにストーリーそのものがおもしろいのだ。
優れたフィクション作品の多くがそうであるように、『夜を走る』も様々な解釈や、様々なメタファーや、様々な社会的コメンタリーを許容する懐の深さを持っている。インタビューでは、日本映画界の表と裏でキャリアを積み、50歳にして本作を世に送りだした佐向監督の映画的バックグラウンド、そしてパーソナルなバックグラウンドに探りを入れることで、この極めて「2022年の日本」的な傑作が生まれた謎に迫った。
宇野「本当に不勉強でお恥ずかしいんですが、最初に告白すると、佐向監督の作品を観たのは今回の『夜を走る』が初めてだったんですよ。前作の『教誨師』の存在は知ってましたし、今回『夜を走る』を観たあと、慌てて過去の作品もいくつか観させていただいたんですけど」
佐向「はい(笑)」
宇野「自分と同世代の日本の監督にこんなすごい映画を撮る監督がいるんだって。もっと早く気づくべきだったわけですけど、今回気づけて良かったなって」
佐向「いえいえ。ありがとうございます」
宇野「『夜を走る』、いまのところ公開規模は小さいですけど、きっとその評判が広がって、年末までには『これを観ておかないと年間ベストなんて決められない』みたいな作品になっていくんじゃないかなって。佐向監督にとっても、これまでの作品と比べて違った手応えがあったんじゃないかなと」
佐向「それがまだ、あまり手応えがないというか(苦笑)」
宇野「そうなんですか?」
佐向「もともと自分は大杉漣さんの事務所に所属していて、10年くらい前からこの作品を作りたいという話はしていたんですが、なかなかうまくいかなかったんです。そのころはホンの内容も今回の作品とはかなり違っていて、特に後半はまったく違うものでした」
宇野「へえ!」
佐向「そうこうしているうちに、先に『教誨師』を撮ろうということになって。それが7、8年前ですかね。『教誨師』は自分としては満足がいく作品だったんですけど、どこかでまだ『夜を走る』をやりたい気持ちが残っていた。 内容的に一般性がある作品だとは思っていなかったんですけど、自分が観客として一番観たいと思うのがこういう作品で。ただ、完成してからも『これ、誰が観るんだろう?』っていう想いがずっとあって。現場でもスタッフやキャストといろいろ意見を交わして、一致団結でやってきたんで、自分たちが考えうる一番おもしろいものになっているんですが、『これを他人はどう判断するんだろう?』とも思っていて。だから、こうやって褒めていただけて、ホッとしているというのが正直なところです」
宇野「本当ですか?もっと自信満々でいいと思うんですが(苦笑)。最初に本作のアイデアが生まれたきっかけはなんだったんですか?」
佐向「僕の同級生が川崎の鉄屑工場で働いていたんです。『おもしろいから一度見にきなよ、映画の舞台にすごいいいと思うよ』って言われて行ってみたら本当におもしろくて。それと、もともと2人の男が死体を車に積んでさまよっている、みたいな話をなんとなく考えていたんです。じゃあその2つを合体させよう、と思って」
宇野「“2人の男が死体を車に積んで”というのは、2005年に撮られた『まだ楽園』でも同じシチュエーションが描かれてましたね」
佐向「『まだ楽園』はスタッフも全然いなくて、僕と友人で撮影した作品だったんですよ。観た人もあまりいなかったので、もう一回やってもバレないだろうって思いがあったのかもしれません(笑)。やらなきゃいけないこと――この場合は死体をどうにかしなきゃいけないわけですが――をしないでただウロウロしている、みたいなイメージが自分の中にずっとあって。そこになんでこだわるのかっていうのは――これまで特に考えてはいなかったんですが――“本当は重大な事態が起きてそれに対処しなければならないのに、目先のことばかりに気をとられ、後回しにしてるうちに取り返しがつかなくなる”というようなテーマに引かれているのかもしれない。もしかしたら、『教誨師』もそこに通じるところがあるのかもしれません、後付けですけども」
宇野「死体であったり、『教誨師』の場合は死刑であったり、“死”って動かしがたい重い事実としてそこにあるわけじゃないですか。その周りで、核心に触れるのではなく、ただぐるぐる回っているところに物語のおもしろさを感じているということでしょうか?」
佐向「はい。物事の核心のようなものがあるにもかかわらず、そこには触れず、日常生活を送っている人たちというのが、自分の世界に対するイメージなのかもしれない」
宇野「でも、我々の人生も大体そういうものですよね。締め切りを超えた原稿や出さなきゃいけない請求書をほったらかしにして、ベランダの掃除をしてたりする(笑)」
佐向「そうそう。まさにそういうことを日々感じていて。 とりあえずそれで日々は過ごせるけれど、それでだんだんいびつなことになっていったり、追々大惨事に発展したりしていく。そういう危機感のようなものが常にあるんですよね」
宇野「そういう意味では、『まだ楽園』の主人公は20代でしたけど、『夜を走る』では40歳前後で、監督自身は50代を迎えて、より後回しにしていることの後ろめたさや深刻さは増してきているということですよね」
佐向「そうなんですよ(笑)。まだ自分にはなにも出来ていない、だからこそこれを撮らなきゃっていう、そういう使命感みたいなものが生まれてきたのかもしれないですね。『教誨師』以前の自分は脚本を依頼されることが多くて、監督する機会がそんなに多いわけではなかったこともあって。僕のなかで、脚本の仕事とは別に、自分が監督する時はどんな映画を撮りたいのかっていう自問自答は常にありました」
宇野「『夜を走る』を観て自分が最初に連想したのは『ブレイキング・バッド』だったんですよ。『ブレイキング・バッド』のファーストシーズンの最初のほうにも同じく主人公とその相棒が死体を車に積んで走る展開があって。でも、その後に『まだ楽園』を初めて見て『あ、「ブレイキング・バッド」の前からやってたんだ』って」
佐向「『ブレイキング・バッド』、実は見てないんですよね」
宇野「それは本当に意外です(笑)。『ブレイキング・バッド』の序盤って、重要なことには目を背け続けている男2人が、ボロボロの車で徘徊しながら、目の前の問題だけを処理し続けるような話なんですけど、それってまさに『夜を走る』じゃないですか」
佐向「そうなんですね。アメリカのドラマは、『ビバリーヒルズ青春白書』以降観てないかもしれない」
宇野「それはやばい(笑)」
佐向「あ、あれも見てました。ジャド・アパトーの『フリークス学園』」
宇野「コメディ作品ばかりだ」
佐向「ジャド・アパトーやグレッグ・モットーラが大好きなんですよ。あと、ファレリー兄弟とか。『グリーンブック』よりも前作の『帰ってきたMr.ダマー バカMAX!』のほうが断然好きですし」
宇野「ああ、でも、よくよく考えてみると『夜を走る』にもコメディの要素は確かにありますね」
佐向「というか、実はコメディのつもりで作ったんですよ」
宇野「そうなんですか(笑)」
佐向「お客さんから笑いがいっぱい起きてほしかったのに、試写では全然笑いが起きてないって言われて、それにショックを受けて…」
宇野「いや、物語がどこに向かってるのか最後までわからないので、可笑しくても笑っていいのかどうか判断できないような作品なんですよ」
佐向「そうですよね。自分は普段、映画の宣伝の仕事もしていることもあって、『この作品を宣伝するのは大変だろうなあ』って思います(笑)」
宇野「エンタテインメント作品かアート系作品かと言われたら、実は佐向監督はエンタテインメント作品寄りの趣向を持っているように思うんですけど、シネフィル的な層に受けそうな感じもあって。まあ、本来その2つは対立するようなものではないのですが、なかなか難しいですよね」
佐向「もちろんエンタテインメント作品もやりたいと思ってるんですけど、現実的なことをいうと、やっぱり手掛ける作品の規模やテーマということでは、どちらかというとシネフィルっぽいところにいるのかなとは思ってます。別に意識してシネフィル的な人に受けようと思って作ってるわけではないんですけど、自分がおもしろいと思うものを作っていたら自然とこうなるというか」
宇野「映画では、どのあたりの作品からの影響が大きいんですか?」
佐向「1960年代、70年代のアメリカンニューシネマですね。デニス・ホッパーだと『イージー・ライダー』というより『ラスト・ムービー』。あと、ジョン・ヒューストンの『ゴングなき戦い』だとかモンテ・ヘルマンの『断絶』だとか。大きなムーブメントのようなものが通り過ぎた後に『どうすんの?これから』みたいな、それでも生きていかなきゃいけないっていう状況を描いた作品が心情的にはもっともシンパシーを覚えるんです。日本映画だと、やっぱり黒沢(清)さんとか青山(真治)さんの90年代の作品はすごく好きでしたし、その前の藤田敏八さんあたりの作品もずっと好きですね」
宇野「なるほど、よくわかります。『夜を走る』ってなかなかジャンル分けしにくい作品なんですが、言葉にするなら ”ファックトアップ・ムービー(fucked up movie)”だと思ったんですね。いま挙げられた作品も、大体登場人物がファックトアップしている。みんな生きることにうんざりしながら、それでも重たい足を動かし続けているというような。ベトナム戦争以降の70年代のアメリカにはそういう気分が蔓延する社会背景があって、90年代の一部の日本映画にもバブルで浮かれていた社会に取り残された者たちによるオルタナティブという意義があったように思うんですよ。ただ、今回『夜を走る』を観て思ったのは、これはオルタナティブでもなんでもない、2020年代の日本そのものじゃないかということで。だからこそ、自分はこの映画を審美的に評価するだけじゃなく、いま観られるべき作品だと言いたいんです」
佐向「当初考えていたものから、特に後半部分を大きく変えたと言いましたが、その理由の一つは当然、コロナの影響でした。別に、コロナの前だってなんにも順調になんていってなかったですけど、脚本を書いて、稿を重ねているなかでコロナ禍に入って。この映画がオルタナティブなものではなくて、現実の延長として受け入れられるとしたら、それも一因かなと思います」
宇野「最後の高速道路のサービスエリアのシーンとか、現在の、 コロナが終わったのか終わってないのかさえよくわからないこの居心地の悪い空気が完璧にキャプチャーされていて、驚かされたんですけど」
佐向「いまの日本のこの空気をどこかに刻印しておかなきゃいけないという意識はありました。作品の中では、一応終わっている設定なんです。『ワクチンまだ打ってないわけじゃないだろう』とか言ってるし。でも、脚本を書いている時は、みんながこんなにちゃんとワクチンを打つなんて思っていなかったんですよ。『こんなことになっていたりして』という、少し近未来ぐらいのつもりで書いたものが、そのまま現実になったような不思議な気持ちですね。サービスエリアのシーンは、最後に現在の日本と地続きな世界をポンと置こうかなと思ったんです。彼はこのあとも、ずっと同じような日常を生きるんだろうなっていう感じで終わらせたいなと思ったんで」
宇野「『夜を走る』は洗車機で始まりサービスエリアで終わる映画という、象徴的なシーンの多くが車絡みの作品ですよね。先ほどおっしゃったアメリカンニューシネマからの影響というのもあるとは思うのですが、それだけではない執着のようなものも感じます」
佐向「最初から洗車機で始まる映画にしたいと思っていたんです。こちらは動いてないのに洗車ブラシが移動していくとまるで車が進んでいるように感じる。この作品の根底にあるテーマがまさにそれだったので。あとは車絡みの画が好きだから…としか言えないですね(笑)。車窓から見える風景自体が、横長のシネスコみたいなサイズじゃないですか。その風景がずっと流れていくのを見るのも、生理的に好きなんですよ。あと、実は車って密室じゃないですか。密室で、2人が同じ方向を向いているっていうのも、日常のなかでほかにはない非現実的なシチュエーションで好きなんです。前作『教誨師』でさえ、あれはほとんど室内だけの作品ですが、最後だけはどうしても車に乗らせたいなと思って、そういうシーンを入れました。車って、閉塞感と開放感が同時にあるところがおもしろいんですよね」
宇野「しかも、乗っている車は、なんの変哲もない営業車だったり、軽トラだったり、あくまでも“移動の道具”としての車で。車に対してのフェティシズムというより、車での移動に対するフェティシズムっていうことですよね」
佐向「そうです、そうです。いい車が好きとかじゃなくて、労働に結びついていたり、生活に結びついていたり、映画の登場人物が本当に乗っているような車を撮るのが好きなんですよ。もちろん、自分が乗るならこういう車に乗りたいとかはあるんですけど(笑)、映画で車が悪目立ちするのは絶対違うよねという思いもあって」
宇野「いや、本当その通りで。日本のインディーズ映画で、車関連の描写がこんなに的確な作品ってなかなかなくて、そこにも個人的にすごく感動しました。あとやっぱり、撮影の渡邉(寿岳)さんの貢献もかなり大きいんじゃないかと。渡邊さんと組まれたのは初めてですよね」
佐向「初めてです。もともと(主演の)足立智充さんが草野なつか監督の『王国(あるいはその家について)』でご一緒されていて、足立さんからの推薦だったんです。で、ちょうど渡邊さんが、コロナ禍にリモート舞台の中継で、森山未來と黒木華が出ている『プレイタイム』っていう配信の有料コンテンツをやっていて。舞台裏からラストまでワンカットで撮っている作品だったんですけど、それがあまりにもすごすぎて。舞台裏の機械を撮る感じとかものすごくよかったんで、この感じでスクラップ工場を撮ってほしいと思ってお願いしたんですが。普段は映画の撮影よりも、いわゆる現代アートをやる方と一緒にやることが多い方ということもあって、彼のおかげでルーティン的な日本映画の画から抜け出すことができたかなって」
宇野「いや、本当に。移動撮影にこだわりのある佐向監督ともめちゃくちゃ相性がいいと思いました」
佐向「まだ30代の若い方なんですよね。というか、そもそも今回の『夜を走る』って、本当はデビュー作だったり30代で撮っておくべき映画だったと思うんですよ」
宇野「確かにそれはそうかも(笑)」
佐向「だから、これからどうしようかなって(笑)。映画業界で仕事をしていて、気がついたら50歳になっていて。50でこんな映画を撮ってていいのかっていう思いはすごくあって」
宇野「いや、それは全然いいんじゃないですか?」
佐向「でも、もう少し人が入るような作品性に向かっていかないと、これで食っていくのは難しいと思うんです。今回、お金集めからキャスティングからすべてに関わったわけですけど、これを50代に入ってからまた繰り返すのは正直しんどい(笑)」
宇野「なるほど、そういう意味ですね。でも、もちろん20代や30代の新人監督が撮った作品ならではの無軌道な良さというのもありますが、『夜を走る』の良さって、観客を途中から思いもしないところまで連れていってしまうストーリーテリングにおいても、主人公がいきなり踊り出したりする描写においても、普通だったらやっちゃいけないことを確信を持ってやりきったかっこよさだと思うんですよね。で、そこで確信を持ってやりきるには、やっぱりキャリアや人生経験からくる、地に足がついた感覚が重要で。ちゃんと作り手が最後まで作品をコントロールしている。作り手がコントロールを放棄して、結果としてわけわかんなくなってるような作品とは全然違うと思うんですよ」
佐向「自分自身がこういうことになった時にどうするかってところからじっくりと考えましたし、スタッフや足立さんにその都度相談もして決めていった部分もあるんですけど、それが一般的におもしろいものになっているかどうかはわかりませんが、少なくとも僕自身はすべておもしろいと思ってやったことなんですよね」
宇野「でも、その感覚が、ちょっとほかではあまり見たことがないような不思議な感覚ですよね。それがこの作品の肝になってると思うんですけど。この作品の撮影は東京で行われてますけど、出身の横須賀というのは、なにかバックグラウンドとして影響があったりしますか?」
佐向「大学を卒業して、社会人になるまで横須賀にいたんですけど、やっぱり基地の街で暮らしていたというのは少なからず影響はあったと思います」
宇野「アウトローの人たちとかも多い土地柄ですよね」
佐向「多いですね(笑)。成人になる前ぐらいから、米軍の人たちが集まるところによく行って、バンドをやったりもしていて」
宇野「ライブハウスも多いですしね」
佐向「そう。一番最初に撮った『夜と昼』という作品はまさに当時のそういう生活を描いた映画だったんですけど、アメリカに対する憧れと、すごく冷めた視線の両方があって、そういうのは、いまもずっと続いていると思います。あと、父親が自衛官だったんですよ」
宇野「へえ!」
佐向「それで、当時は団地みたいなところに住んでいたんですが、祝日にウチの部屋だけ窓から日の丸を出してるんですよ。それがすっごく嫌で」
宇野「でも、我々が子どものころの時代って、祝日になると結構みんな日の丸出してましたよね。集合住宅だと珍しかったのかもしれないですけど」
佐向「だからといって、めちゃくちゃ右寄りの家庭とか、そういうわけではなかったんですけども」
宇野「いや、お父様の職業的に、愛国心はあってしかるべきだと思いますよ、当然」
佐向「まあでも、息子って父親に反発するものじゃないですか」
宇野「最近はそうでもないという話はよく聞きますし、その実感もありますけど(笑)」
佐向「僕自身は若い時、思いっきり父親とは反対の方向にいって、父親と取っ組み合いになったりしたこともあって。そのころに比べて自分自身もかなり変わりましたけど、そういう少年時代を経て、国家とか体制とかに対する複雑な想いはずっと抱えてきましたね」
宇野「監督のパーソナルな生い立ちが作品への先入観になっちゃいけないとは思うんですが、『夜を走る』にも流れている、単純な反体制とは違う、だからといってただの体制順応とも違う、あのちょっと不思議な感覚のカウンター意識みたいなものとつながってる気がしてとても興味深い話ですね」
佐向「ちょっと違うかもしれないんですが、自分は刑事ものってあんまり好きじゃないんです。刑事ものって、警察組織に順応してる人間は主人公になりにくくて、大体主人公は組織に反発してる刑事ばかりじゃないですか」
宇野「確かに」
佐向「体制組織の中の一匹狼ってすごく図式的というか、逆に権威主義のように思えてしまう。だから、クリント・イーストウッドは大好きなんですが、『ダーティハリー』シリーズとか全然おもしろいと思わないんですよ。例外は、警察官で、体制側の人間だったつもりが、圧倒的な壁にぶち当たってだんだん落ちぶれたり潰されていったりする映画で」
宇野「そっちだったらいいんですね(笑)」
佐向「リチャード・フライシャーの『センチュリアン』とか、アレックス・コックスの『PNDC エル・パトレイロ』とか」
宇野「アベル・フェラーラの『バッド・ルーテナント 刑事とドラッグとキリスト』とかもそういう映画ですよね」
佐向「そうそう。ああいう作品は好きなんです」
宇野「なるほど。ありがちな一匹狼ものの刑事ものとかを見てると『体制のなかにいるくせに反体制ぶってんじゃないよ』って気持ちになる?」
佐向「そうですよ。刑事のくせに俺は俺のやり方でいくみたいなのを見せられると、白けちゃうというか。どうせなら体制側に立って、もう悪いことばかりしてればいいんですよ(笑)。そういう屈折したところがあって」
宇野「ああ、でもすごくよくわかりますよ。それでいうと刑事の内部告発ものとかとんでもないですよね。組織のなかにおけるスニッチ(密告者)って、もっとも軽蔑すべき存在ですもんね。確かによくないわ。自分もこれからはその視点で刑事ものを見よう」
佐向「(笑)」
宇野「佐向監督が撮る刑事もの、観てみたいですね。今日はお話できてとてもおもしろかったです。次作も『夜を走る』のようなスペシャルな作品を期待してます!」
佐向「そうですねえ。『夜を走る』がちゃんとお客さんに観てもらえたら、そこに近づけるとは思うんですが」
宇野「大丈夫です。きっちり盛り上げます!」
取材・文/宇野維正