喜びとか怒りとか楽しさとか寂しさとか、人間が持っているとされる感情の一部が欠けている4人きょうだいの物語。それぞれ別々の監督が撮った各人のストーリーを順番に見せていく。普通でない人々を、変わったスタイルで描いた作品かと思いきや、見てみると、何が普通で、何が普通でないか、ちょっと思いをめぐらせたくなる。(編集委員 恩田泰子)
プロローグに続き、「長男のはなし:“Voice Recorder”」(横浜聡子監督)、「長女のはなし:“Humanoid”」(石井岳龍監督)、「次男のはなし:“Still Ok”」(加藤拓人監督)、「次女のはなし:“Honeymoon Baby”」(守屋文雄監督)と、4つのエピソードを順番に見せ、エピローグで閉じる構成の映画だ。
主人公の4人きょうだいはそれぞれ、ある感情が欠けている。長男(嶺豪一)は「喜び」、長女(柳英里紗)は「怒り」、次男(井之脇海)は「楽しさ」、次女(白田
設定だけ聞くとひとごとのように感じる人も多いだろう。だが、それがふっと自分ごとに反転する瞬間が、この映画にはある。
それが最初に訪れるのは、「長男のはなし」の途中。脚本家である長男は、喜びを表現するせりふをさがし当てたいのだが、うまくいかない。途中までそれは、彼だけの物語。だが、彼と食事していた俳優(宇野祥平)が自然に吐く罪のないうそを目の当たりにするうちに、むむむと思う。
日常を円滑に生きるために呼吸をするようにうそをつく。演技する。このエピソードで宇野が演じる俳優は、そんな人物。でも思えば、人は多かれ少なかれ、そんなふうに生きている。
本当にうれしいから喜ぶのか、それとも、うれしくて喜んでいる自分を演じているのか。自分たちの感情のどこまでが本当でどこからがうそか。もし、ちゃんと心が動いていないのに動いているふりをしていたとしたら、あるいはその逆を演じているとしたら、感情の一部が欠けている主人公たちと自分たちは一体何が違うのか。そう考え始めた瞬間から、この映画は、結構切実な「自分ごと」になる。
長男のはなしに続き、今様の社会革命に身を投じた長女の葛藤を描く「長女のはなし」で描かれる世界を見ていると、そうした思いは、さらに膨らむ。
演技、うそ、つくりごとの中にこそ、あらわれる本当のこと。「長男のはなし」の横浜監督は、嶺や宇野のさりげなく味わい深い演技をたっぷり生かして、それをあぶり出す。「長女のはなし」の石井監督は、現実社会と人間のあれこれを巧みに増幅。「いい加減」がわからず、自分にうそがつけないヒロインが、人のとてつもなさと卑小さ、怖さとおかしさの間で戸惑い、揺さぶられていくさまを凝視させる。渋川清彦が演じる「いい加減」な元上司の言動でアクセントをつけながら。
「長男のはなし」「長女のはなし」の2本は、いながききよたかによる脚本と、横浜監督、石井監督それぞれの世界が有機的に結合。緩急自在、笑いどころも完備して、観客を引きつける。特に「長女」の終盤は、どきどきするような目覚めの気配に満ちていて、その先が見たいと思わずにはいられない。
ただ、映画の仕立て上、話は移る。加藤監督、守屋監督がそれぞれ脚本を自分で手がけた後半の2つの物語は、前半の作にくらべると淡い味わいだが、それも個性。4つのエピソードに一体感をもたらす仕掛けがもう少しあれば、よりパワフルな映画になったのではないかとは思うけれど、のびのび作っている感じは悪くない。「次男のはなし」終盤の井之脇の演技など、思わず胸をつかまれる瞬間もある。
全体を通して大きな魅力になっているのは、本当の風景。東京の街の様子などが物語の現実感を補強している。近年の日本の劇映画は、汎用性を重んじてか、実在する商品を登場させることが少ないが、本作には、実在のビールや飲料がちゃんと登場しているのもいい。製作サイドの気概は、そういった点にも出ると思う。
企画・製作・配給のコギトワークスは。本作の国内外での公開を目指して、海外のミニシアターとも直接交渉。ロンドンや米ニューヨーク州ロチェスターなどでの同時期公開にこぎつけている。
◇「almost people(オールモスト ピープル)」=2023年/140分/企画・製作・配給:コギトワークス=9月30日、東京・渋谷のユーロスペースほかで公開
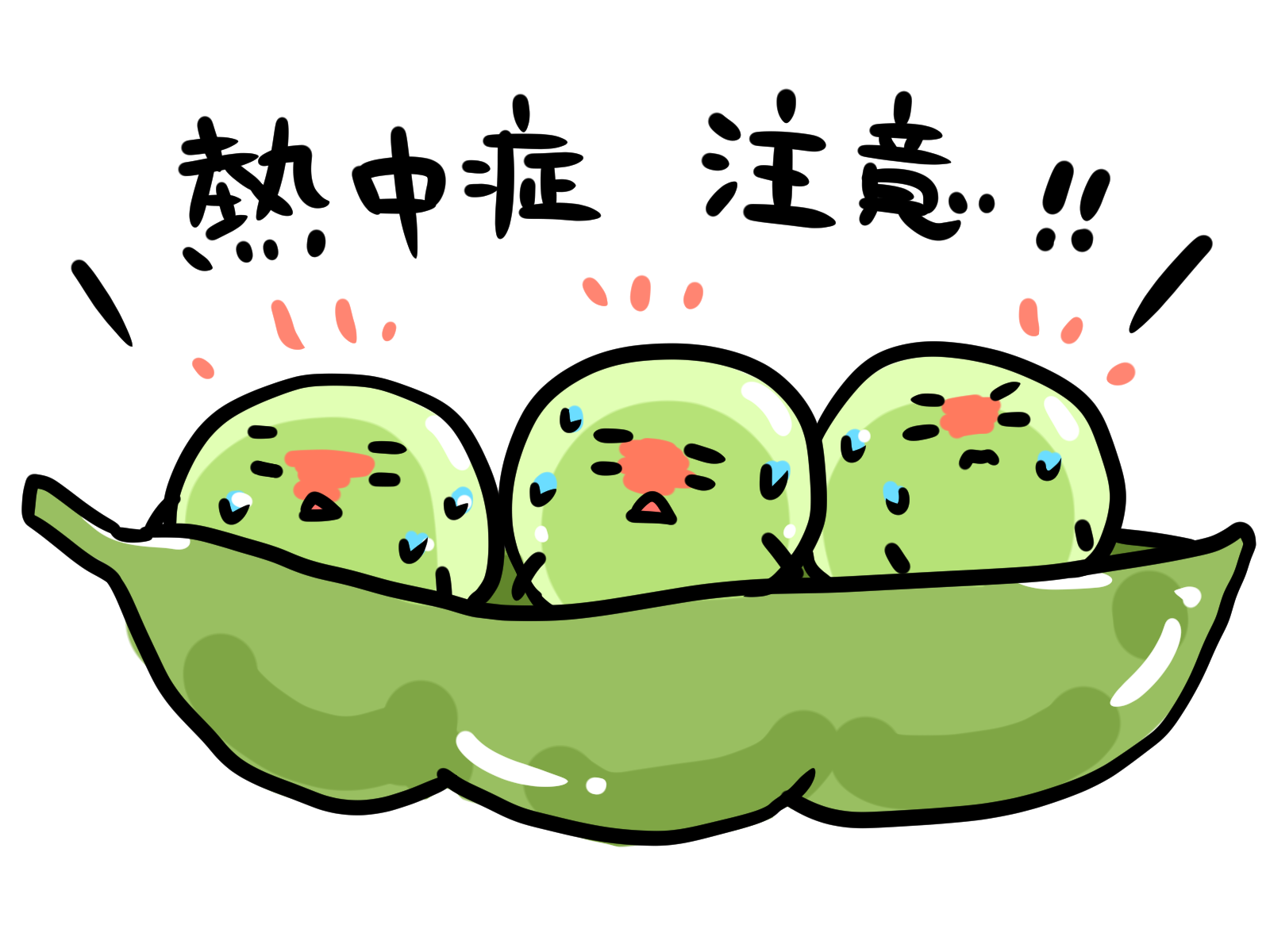


![[映画評]「almost people」…ひとごととは思えない、感情が欠けた兄弟姉妹の物語](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/yomiuri/s_20230928-567-OYT1T50244.jpg)









