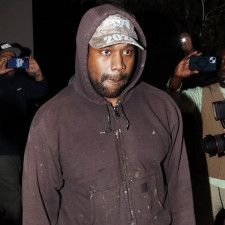この世とあの世、生きてるものと死んでるものは、分かたれているはずなのだけれど、そう簡単には割り切れない「何か」を感じながら、大抵の人は生きている。そして、この「はだかのゆめ」という映画には、その「何か」が映っている。子を思う親、親を思う子をめぐる物語である。
監督・脚本・編集の
高知県、四万十川のほとり。母(唯野未歩子)と祖父(甫木元尊英)が穏やかに暮らす地に、息子のノロ(青木柚)がやって来る。母は闘病中で、どうやらそう長くはない。ノロマなノロはあわてているが、母とは距離を置いて幽霊のようにうろつくばかり。神出鬼没の酔っ払い、おんちゃん(前野健太)という男とのやり取りも何だか奇妙だ。一体、彼らは何なのか。不確かなものだらけの世界で、親と子の互いへの思いだけが確かに浮かび上がってくる。
水の音、ゆらめく炎、季節外れのせみ。映画はひそやかに始まり、走り出す。闇の中を行く列車と、駆けていくノロ。美しい旋律とともにあふれ出すただならぬ気配にぞくりとする。だが、映画はそのまままっすぐ走って行ったりはしない。アナログレコードよろしく、ぐるぐる回りながら、でも確かに進んでいく。
生と死をめぐる映画だが、この映画において、両者は、ぱきっと二分して描かれてはいない。なぜ割り切れないのか。そのあわいには何があるのか。「生きてるものが死んでいて、死んでるものが生きている」といったせりふは一体どういうことなのか。この映画は、豊かなイメージと音、そして、そっけないようでいて、心にしみる言葉をもって、きっと誰しもが感じたことがある割り切れない「何か」をつかみ出していく。
監督は現在、四万十町在住。本作には、自身と家族のことが投影されていて、「祖父」を演じているのも、実の祖父なのだという。でも、家族、そして自分自身ほど、近くて遠いものはない。この映画を見ていると、つくづくそう思う。相手を大切に思えば思うほどに。 観客は、きっと、誰もが自分の家族、そして自分を重ね合わせたくなる部分を見出すだろう。そして、ずうっと抱いてきた名状しがたい感覚に姿かたちを与えてみせる映画作家と出会えたことに興奮するだろう。
監督はバンド「Bialystocks(ビアリストックス)」として活動しており、本作の音楽も手がけている。同バンドのミュージックビデオ「灯台」の世界も、また、この映画とつながっている。(編集委員 恩田泰子)
◇「はだかのゆめ」=2022年、59分、製作:ポニーキャニオン、配給:boid/VOICE OF GHOST=11月25日から東京・渋谷のシネクイントほか全国順次公開
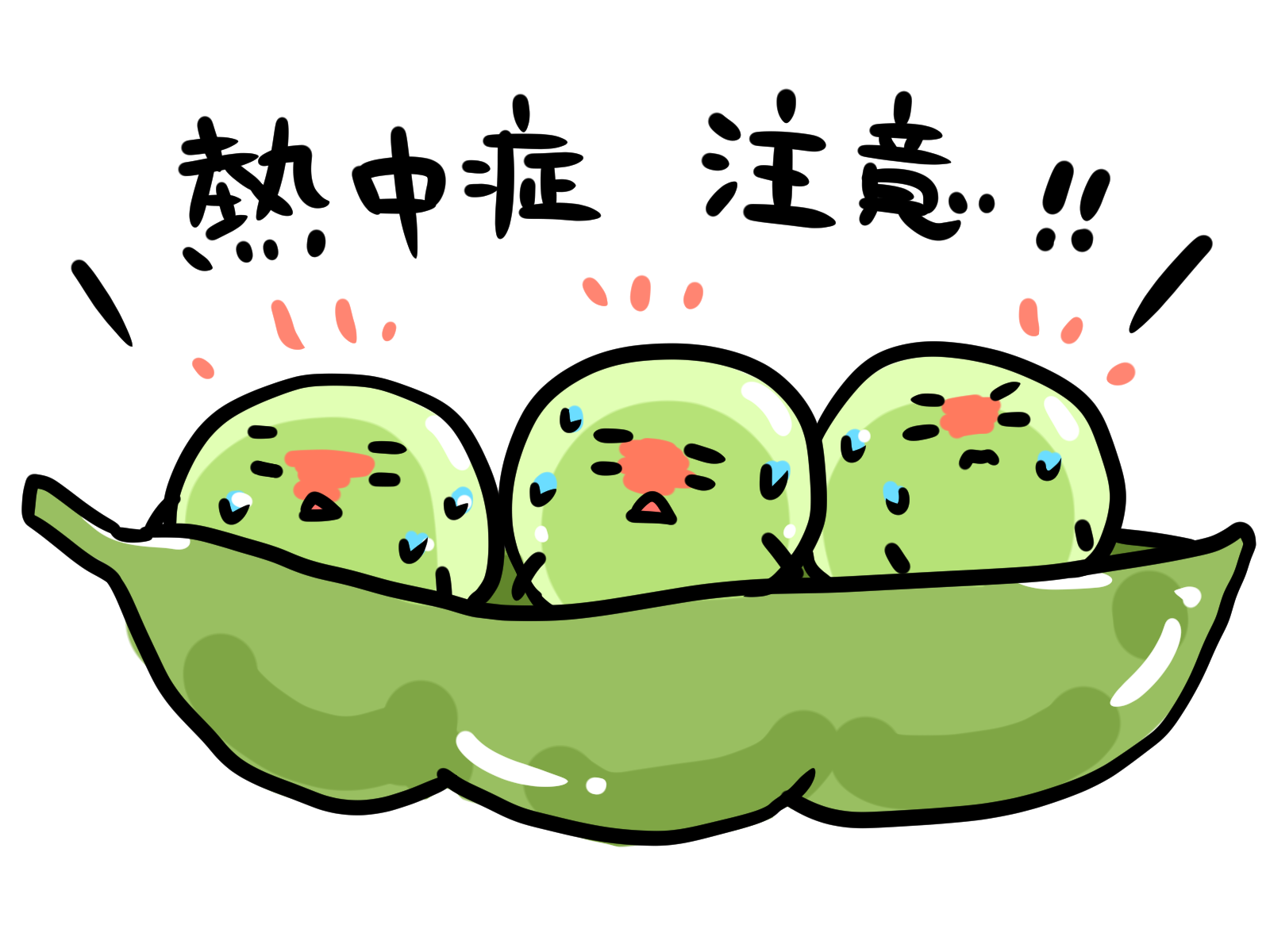


![[映画評]「はだかのゆめ」…近くて遠く、夢のようだが確かな家族の物語](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/yomiuri/s_20221124-567-OYT1T50229.jpg)