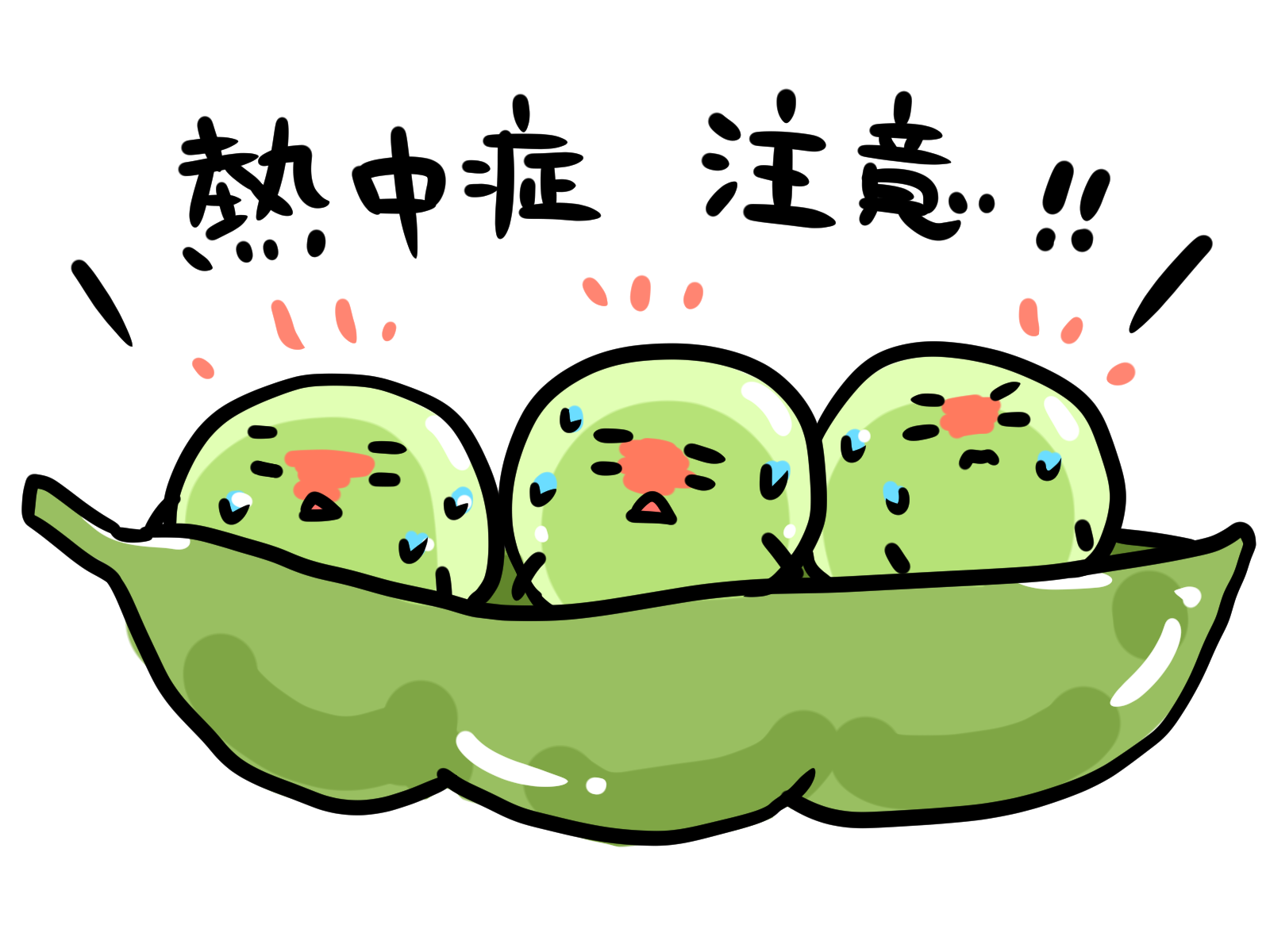「昴─すばる─」「いい日旅立ち」「サライ」と、昭和からの時代を彩る名曲は数知れず。このほど74歳で亡くなったシンガー・ソングライター谷村新司さん。ことし3月に急性腸炎で手術後、バンド「アリス」での復帰を目指し闘病していたそうだ。
「渡り鳥シリーズ」でギターを弾く小林旭に憧れ、「自分もモテたい」とギターを手にしたのはファンならば誰もが知るところ。そして「アリス」を結成し、1972年に「走っておいで恋人よ」でレコードデビューするが、その誕生エピソードは70年の大阪万博にさかのぼる。
アマバンドのボーカルとして、カナダ館で演奏していた22歳の谷村さんは「おまえらの歌をアメリカ人に聴かせたろやないか」と、このとき知り合った若者から誘われた。
「僕らもピュアだったから、そうやなと言ってたら、本当にそれが実現して、アメリカ大陸をバンクーバーからニューヨークまで横断したんだけど、メキシコまでたどり着いた時に持っていたお金が尽きたんです」
メキシコでの原体験
谷村さんは昨年、そうラジオで楽しそうに振り返っている。メキシコではこの若者が国営放送に掛け合い、なんとメキシコフェスタに出演。言葉も通じず、歌もうけなかったが、意気消沈しなかった。
「残り時間3分くらい、アミーゴ一発で通しましたね。一点突破。メキシコ人がおまえらのアミーゴ最高だったよと言ってくれて、良かったのかな、それでと。怖いものは何もなくなりました。友達ひとりいたらその国を好きになると体感できた。この原体験が凄く大きかった」と。
全米横断中にはレッド・ツェッペリン、ジャニス・ジョプリンのステージをライブで見たそうだ。ちなみに「アリス」とは、ロスのレストランのメニューにペン字で書いてあった「Alice」の表記から。かっこいい、とその場でバンド名に決めたのだという。以下、ご本人を知る構成作家のチャッピー加藤氏にエピソードを聞いた。
「この『万博で知り合った若者』というのは、アリスの所属事務所になる『ヤングジャパン』社長の細川健氏です。細川氏の企画した米国ツアーには谷村さん以外のミュージシャンも同行し、谷村さんはアリスのドラマーとなる矢沢透さんと出会います。万博会場での出会い、無謀ともいえる米国ツアーがなければ、アリスは誕生していなかった。面白そうなことはまずやってみようという、谷村さんのポリシーはこういう経験を通じて、培ったものだったのでしょう」
趣味はビニ本集め
「ヤンタン」の愛称で親しまれているMBSラジオのDJ時代はこんなエピソードが。
「深夜ラジオだけに、聴いている人はそんなにいないだろうと、冗談で(大阪の)中之島公園に集まってと呼び掛けたら、リスナーであふれかえり、警察が出動する事態に。アリスが売れる前の話ですからね。車で聴いている人にクラクションを鳴らすよう呼びかけ、大阪の街にクラクションが響き渡ったとか。警察からは大目玉で、しょっちゅうディレクターが始末書を書いていたそうです」
いまほど規制も厳しくなかった時代、谷村さんはそうやって自由に行動し、発想し、創造の羽を広げていったのだろう。
「そういえば、文化放送の『青春キャンパス』も、ばんばひろふみさんと下ネタ、バカネタのオンパレードでしたね。ビニ本集めが趣味と公言したりしていました。大笑いしながら、受験戦争や出世争いで大変な学生やサラリーマンは慰められたのではないでしょうか」
とはいえ、「アリス」では長い下積みも経験した。
■「遠くで汽笛を聞きながら」の汽笛は…
「しゃべりは面白いし、楽曲も演奏も素晴らしく、評価されていたのに、なぜかレコードは売れなかった。それで、とにかく全国の人たちに自分たちの曲を聴いてもらおうと、年間300本以上のステージをこなしたんですね。そんな日々の中から生まれたのが、谷村さん作詞、堀内孝雄さん作曲の『遠くで汽笛を聞きながら』。青森へライブに行ったとき、遠くで汽笛が聞こえたのだそうです。『それが青函連絡船の汽笛でね』とご本人から伺ったことがあります。♪悩み続けた日々が〜の歌い出しは、まさに当時のアリスの状況そのもの。何もいいことがなかったけど、ここでやめたらすべて終わってしまう。だから諦めず、音楽の世界に踏みとどまろうという決意を歌った曲だと聞いて、胸が熱くなったものです。遠くの汽笛を、再出発の合図と聞いていたんですね」
その後、「チャンピオン」などのヒット曲を連発させるが、谷村さんは「アリスに欠かせない曲」として、この歌をステージで歌い続けたのだそうだ。
大御所になり、数々の肩書を持っても、親しみやすく、際どいジョークで相手を和ませた。遠くに響いたあのときの汽笛が、天国への旅立ちの際も聞こえていたのかも知れない。