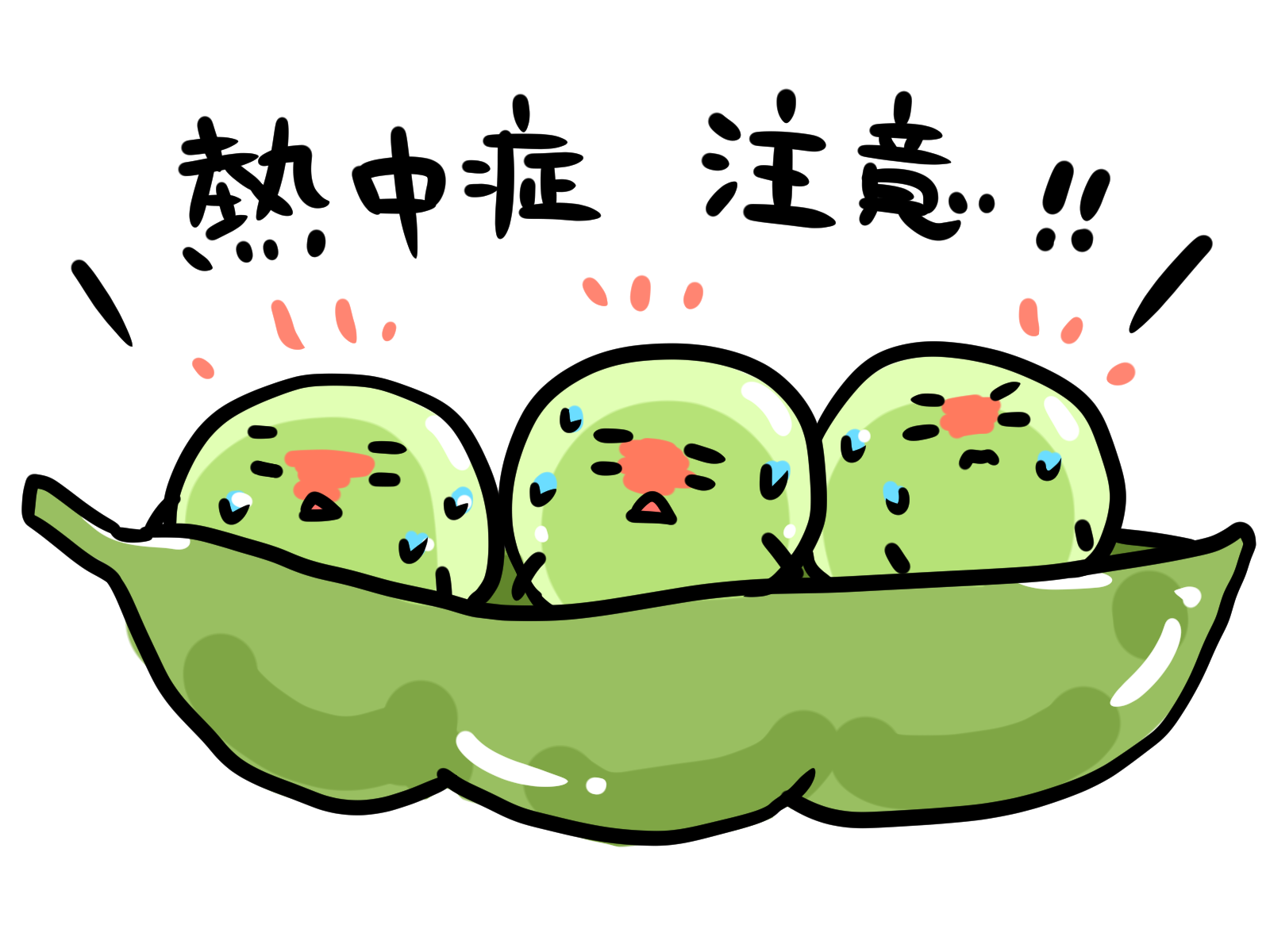関西国際空港からわずか7キロに位置するりんくう総合医療センター。国際診療科では、機内で発症した救急患者や訪日観光客、全国から評判を聞きつけた在留者など多くの外国人を受け入れている。診察室では、医療通訳者が医師と患者の間に入り、国際医療コーディネーターが、診察前の手続きや検査、会計までもフォローする。
率いるのは、ブラジルと日本の医師免許を持ち、ポルトガル語、スペイン語、英語を駆使する南谷かおり医師だ。幼いころブラジルへ転居した南谷医師は、異国で言葉が通じない不安を知っている。そうした経験も活かし、診察室の外も含め、言葉の壁で困っている外国人患者へ徹底的に寄り添っていた。南谷医師は、全国に先駆けこうした取り組みを続けている。
取材を始めたのは、コロナの規制も緩和し外国人観光客が再び日本に戻ってきた4月。ある夜、観光で訪れていたオランダ人が心筋梗塞で救急外来に運び込まれ、緊急オペが行われた。対応に追われる国際診療科のスタッフたち。患者や家族への病状の説明や、保険加入の確認、同意書へのサインなどやるべきことは尽きない。退院の日まで寄り添ったスタッフに、患者は感激していた。
来院するのは訪日患者ばかりではない。むしろ割合が多いのは在留の外国人だ。日本で税金を払い、日本の健康保険に加入しているものの日本語が話せず病院を避けがちな外国人も少なくないという。たとえば、20年以上日本に住んでいるが、日本語が話せないブラジル人女性。彼女が訴えていたのは、以前から抱えていた不整脈の悪化だ。
今回、南谷医師のサポートで手術を受けることになった。言葉のわからない異国の地で受ける、心臓の手術。オペ室で飛び交う執刀医たちの専門用語に、不安は増していく。そんな彼女に、南谷医師が患者の母国語・ポルトガル語で語りかけたこととは。
ディレクターメモ(取材こぼれ話)「取材中、私は20代の南谷医師の写真を手に取り、思わず『先生モテたでしょう?』と漏らした。すると彼女は、半年前に、ブラジル時代の仲間たちと再会した時のエピソードを話してくれた。『かおりは明るくおしゃべりな女性になったね』と、皆が口を揃えて言ったそうだ。ブラジルでは、彼女自身も言葉の壁に苦しんだ外国人だった…。もしかしたら、彼女のそんな経験が、外国人患者を助けたいという情熱の源なのかもしれない」と伝えている。