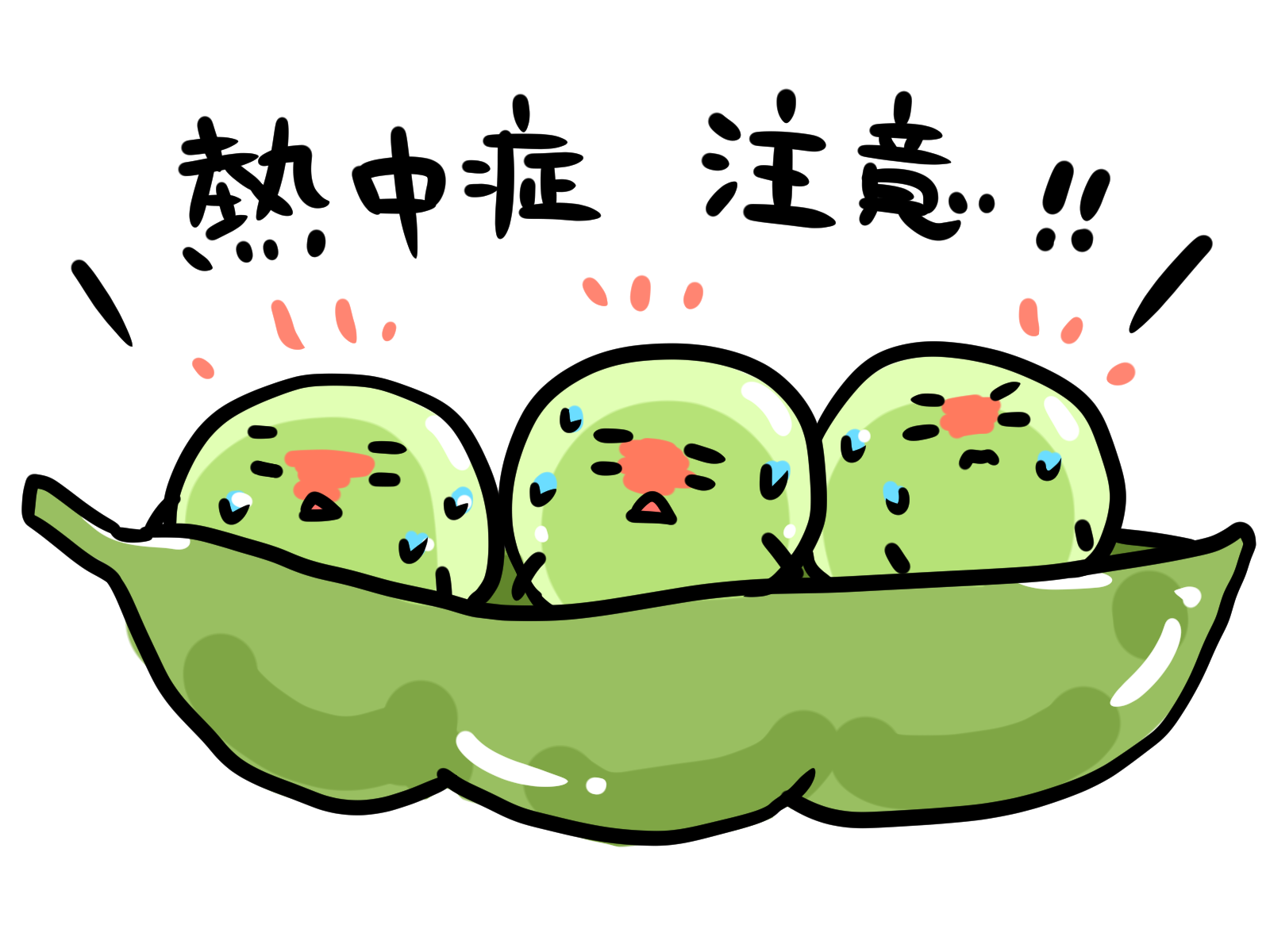中間小説の戦後史たどる
純文学と大衆文学の間に位置付けられた「中間小説」という分野があった。戦後 日本文学の研究者らが、昭和20〜40年代に刊行された雑誌を分析してその歴史をたどった、『中間小説とは何だったのか』(文学通信)=写真=を刊行した。これまでほとんど論じられることがなかった中間小説の実相と掲載した雑誌の輪郭をとらえた。(池田創)
戦後の日本では、活字への飢えや新時代の空気から、文学青年や一部のエリートのためではない、一般市民も面白く味わえる小説が求められた。純文学と大衆文学の中間的な小説として、「中間小説」という呼称が生まれ、文芸評論などで用いられた。妖しい女性の運命を描いた舟橋聖一『雪夫人絵図』(1948〜50年連載)、ある殺人事件をつづった松本清張『地方紙を買う女』(57年)などの作品が挙げられる。
ただ、中間小説の全体像や歴史は、ほとんど論じられてこなかった。
名桜大の小嶋洋輔教授を中心とした戦後文学の研究者4人による研究グループは、中間小説が活況を呈した昭和20〜40年代に刊行された中間小説誌を収集し、入手が難しいものは国立国会図書館で閲覧するなど、10年以上にわたって調査・分析を続け、本書をまとめた。小嶋教授らは、「中間小説という言葉そのものが忘れられており、時代とともに、その輪郭をとらえたかった」と語る。
本書は年代ごとに、各出版社の中間小説誌について、刊行経緯や掲載作品の内容を見渡していく。「オール読物」「小説現代」など今も続く雑誌もあれば、「小説セブン」など、既に刊行していないものもある。戦後日本で展開した小説メディア史の一側面を見るようだ。
後に直木賞作家となる和田芳恵(1906〜77年)が創刊に携わった「日本小説」の編集後記は、中間小説を考える上で示唆に富む。
<ここに広々とした荒野があり、放たれた人民の群れが
研究本刊行「文壇より読者」読む喜びと熱気
帝京平成大の高橋孝次准教授は、和田が批評や文壇に背を向け、読者のみを見たことに注目し、「シビアな読者を想定して、新たな小説の場を創り出そうとしている張り詰めた気配が漂っている」と述べる。編集者や作家が奮闘して、純粋に親しめる本を届け、多くのベストセラーが生まれた。その熱気こそ、中間小説の戦後文学史上の意義だったと言えるのではないか。
小嶋教授らは今後も研究を発展させるといい、「戦後社会で出版社がどのような戦略を持っていたかも研究対象になる」と話す。
「オール読物」が隔月刊化
1930年に前身の雑誌が誕生し、かつて中間小説誌と位置づけられた「オール読物」(文芸春秋)は、6月発売号から隔月刊化した。現在は平均約2万7000部を発行しているが、出版不況に加え、輸送費や紙代の値上げも影響した。
今後は掲載する小説の本数を増やしたり、文学賞などの特集を掲載したりして、「引き続き小説の面白さを読者に届けたい」としている。来年は定期購読者を招いた愛読者大会を開催予定だという。
石井一成編集長=写真=は「人気作家の作品をいち早く掲載するだけでなく、ほかの作家も読んでもらうことで、読者が持つ小説の世界を広げることができる。これからも小説の可能性を考えていきたい」と話している。