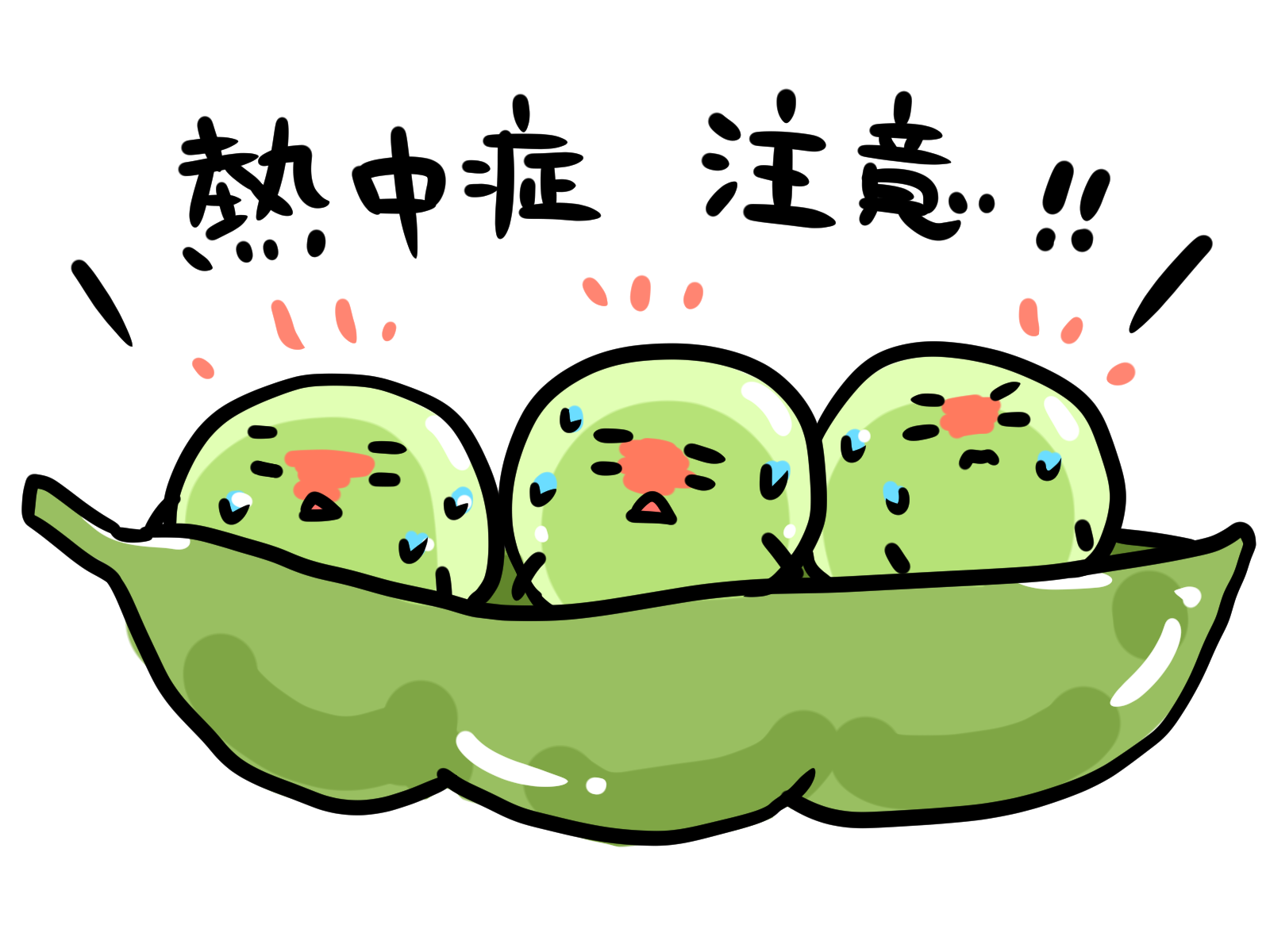「ウルトラマン」の企画・発想の原点へと立ち還り、現代の日本を舞台に“ウルトラマン”が初めて降着した世界を描きだす本作。5月13日に公開されると初日から3日間で興行収入10億円に迫るスタートダッシュを飾り、国内動員ランキングでは2週連続で1位を獲得。6月10日からはMX4Dや4DX、Dolby Cinemaなどの上映もスタートし、6月26日までの公開45日間で興行収入40億円を突破。海外の映画祭への出品が決まるなど、その勢いは増すばかり。
全国の上映劇場で販売されている劇場用パンフレットと、同じく上映劇場および書店にて発売中の「シン・ウルトラマン デザインワークス」の2冊を読めば、その想いをより深く感じることができるだろう。とりわけ本稿では、「シン・ウルトラマン デザインワークス」を中心に、全特撮ファンにとって必見のこの2冊を紹介していこう。
※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。
■禍威獣やメフィラスなどデザイン資料は500点超!オリジナルへのオマージュがそこかしこに
「シン・ウルトラマン デザインワークス」にはウルトラマンはもちろんのこと、劇中に登場する禍威獣(カイジュウ)たちや外星人、ベーターカプセルなどのプロップから禍特対本部のセットの図画に至るまで、本作の世界観を構築するありとあらゆる要素のデザインが500点以上掲載されている。
「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の実質的な美術総監督の成田亨が描いた、「真実と正義と美の化身」をデザインコンセプトの原点に、成田が志した本来の姿を目指したウルトラマンのデザイン。本書では、体表のラインやマスクの形状から、カラータイマーをつけないことなど、成田の望んでいたテイストを再現するに至るまでの過程が、質感から色彩のバリエーションまで細部にわたって確認することができる。
ちなみに、禍威獣たちのデザインにもオリジナルへの敬意が余すところなく込められている。例えばアバンタイトルの一番初めに登場するのは「ウルトラQ」第1話に登場したゴメス。本作では『シン・ゴジラ』(16)で使われたゴジラのCGモデルをベースに登場している。
また同じくアバンタイトルに登場するパゴスと、ウルトラマンと戦うネロンガとガボラも同様だ。元々『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(65)のバラゴンの着ぐるみを流用していた「ウルトラQ」のパゴスの着ぐるみは、その後「ウルトラマン」第3話ではネロンガになり、第8話のマグラーを経て第9話でガボラへと改造されていったのは、特撮ファンにはよく知られたことだ。本作においては禍威獣たちをCGで作りだすにもかかわらず、あえてそうしたオリジナルの造形の流れを踏襲。劇中の登場人物のセリフでもパゴスとネロンガ、ガボラが似ていることが指摘されるかたちでオマージュが捧げられている。
本書のデザイン集には形状案のスケッチ、手書きのメモが加えられた設定案や修正案、検証用立体造形物の写真、CGモデルなど、各々のキャラクターについて数ページにわたって克明に記録。本編では登場時間が短くじっくり観ることができなかったゴメスらアバンタイトルの禍威獣たちのCGモデルも掲載。もちろんザラブやメフィラスといった外星人のアートワークもたっぷり収められており、山下いくとが描いた形状案から完成形に至るまでの詳細な検討と修正の過程は必見だ!
■庵野秀明が明かす『シン・ゴジラ』とのつながり。続編の可能性は?
さらに本書には、庵野が本作の企画の原点からオリジナルへの想い、制作の一連を振り返った約1万2000字に及ぶ手記も掲載されており、こちらも制作の舞台裏を知るのにはもってこいの充実の内容となっている。
その一部を抜粋すると、物語の構成について「基本は“初代”の流れの分解と再構成」と表現する庵野は、「本編は物語の基本である“出会いと別れ”を主題としています。これも初代と同じというか、シリーズ全体を圧縮した踏襲すべきテーマなのかなと」と、ストーリー面でもオリジナルをリスペクトしたことに言及。
また、「ウルトラマン」のオープニングで見られた前作「ウルトラQ」のタイトルから爆発ワイプでタイトルが出るという表現を踏襲したことに触れ、「該当する前作が作品世界的に存在しないので、メタ的な理由しかないのですが、『シン・』というタイトルとスタッフの共通点、なんとなくつながっているような世界観から『シン・ゴジラ』のタイトルロゴにしました」と明かす。
ちなみに、前述したゴジラのCGモデルを流用したゴメスの登場と同様に、『シン・ゴジラ』とのつながりは本編の随所に見受けられる。 “シン・”というタイトルや、“巨大不明生物”という用語だけでなく、政府の人間として竹野内豊をキャスティングしたという共通点に気付いた『シン・ゴジラ』ファンも少なくないだろう。
庵野の手記では、劇中に登場する禍威獣や外星人のセレクトについては「アバン、禍威獣×2、ザラブ星人、メフィラス星人、ゼットンを操るゾーフィというテレビシリーズ5話分の流れは極初期から考えていました」と明かし、「禍威獣だけだと話の流れのパターンが似てしまい、人間サイドのドラマを作りにくいので、後半は宇宙人との話にしました。バラエティー豊かなエピソードが詰まっているのも初代の魅力なので、それもなるべく踏襲しようと試みました」と隅々にまでオリジナル愛を行きわたらせたことを説明。
ほかにも手記のなかでは、ウルトラマンや禍威獣、外星人のデザインコンセプトが庵野の口から直接語られており、先で紹介したデザイン集と併せてチェックしていくとさらにそのこだわりを感じることができる。また、編集や音響、VFXなどのこだわりも語られており、最後には続編の可能性についても言及されているので絶対に見逃せない。
■パンフレットとデザインワークス、2冊合わせてチェック!
そして劇場用パンフレットには本作の詳細なストーリーをはじめ、 “ウルトラマンになる男”神永新二役の斎藤工や、神永のバディとなる浅見弘子役の長澤まさみ、“禍特対”班長である田村君男役の西島秀俊らメインキャストのインタビューも掲載。さらに樋口監督や准監督の尾上克郎らスタッフ陣のインタビュー、貴重な絵コンテや豊富な劇中カットなども掲載されているのでこちらも注目だ。
「デザインワークス」も劇場用パンフレットも、ストーリーの核心に触れる内容が含まれているので本編鑑賞前にはうっかり開かないように気を付けてほしい。パンフレットと「デザインワークス」の両方を読めば、二度三度といわず何度でも劇場に足を運び、そのディテールを確認したくなること間違いなしだ。是非とも入手して、『シン・ウルトラマン』の世界をより深く堪能してほしい。
文/久保田和馬