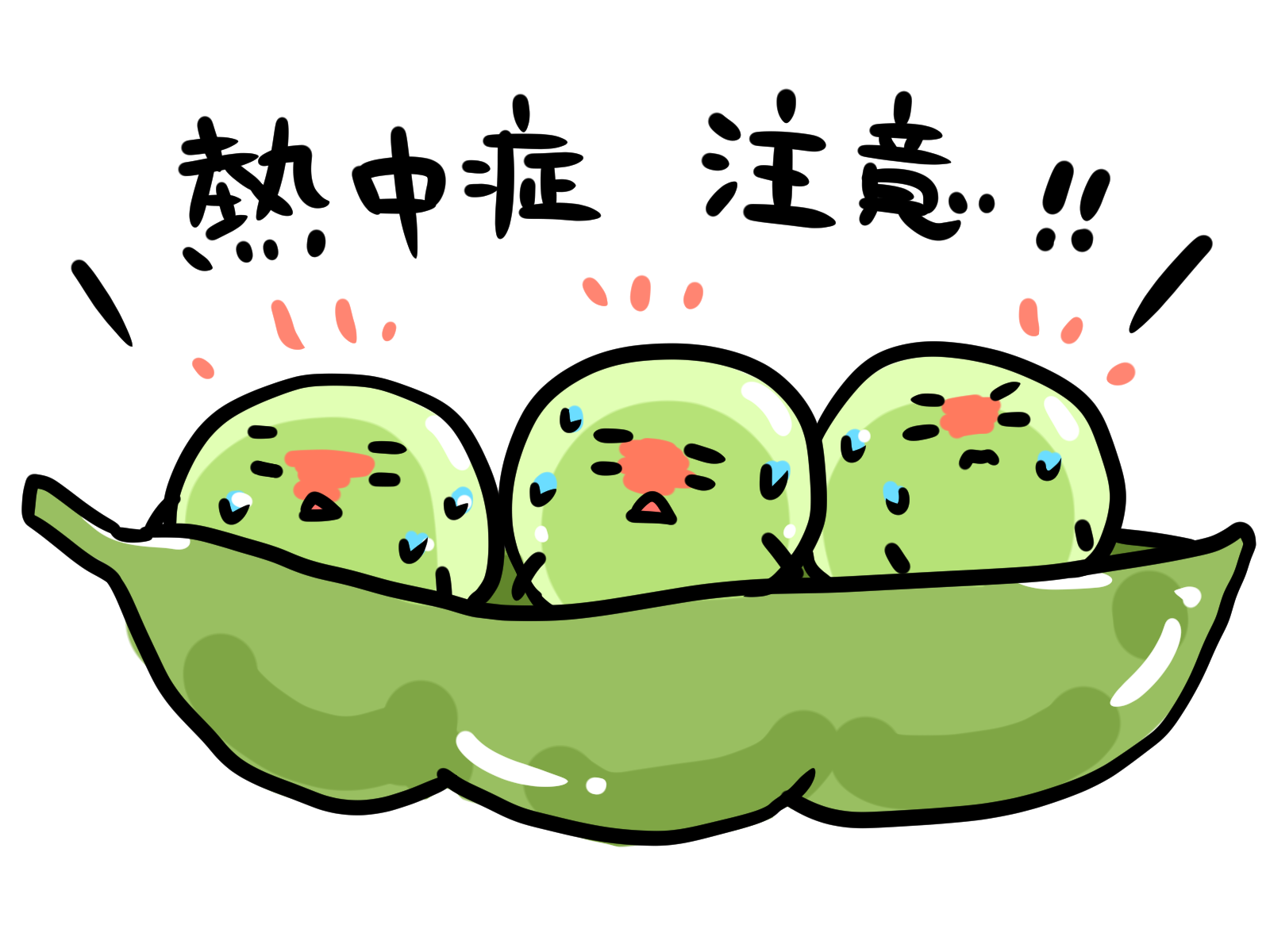韓国の赤ちゃんポストに年間200人以上が預けられることを知り、題材として温めてきた是枝監督。これまでに撮った「誰も知らない」(2004年)で育児放棄された子どもたちを描き、「そして父になる」(13年)で父性の所在に焦点を当て、「万引き家族」(18年)では疑似家族を通して現代社会を問うた。だが今作は、何もないところから出発した人々が次第に距離を縮める。まとまるのか、またばらけるのか。その行方が見ものだ。
脚本を書くため是枝監督は韓国の赤ちゃんポストと、関わる人々に取材を重ねた。養護施設出身者、刑事、シェルターで暮らす母子、弁護士。「実親と一緒に暮らすことができなかった子どもは、自分は生まれてきてよかったのか、悩みながら生きていた。それに応えることができる内容にしなくては」と心に決めて撮影に入ったという。
張り込みの刑事のつぶやき、「育てられないなら産むな」は世間の声だ。しかし是枝監督は「映画は預けざるを得なかった母親だけでなく、見えてはいない赤ちゃんの父親の存在も考えなければいけない」との姿勢も説明した。
取材の中で是枝監督に、この6月、60年を迎えた、実親と暮らすことが困難な子どもと里親をつなぐ「愛の手運動」のことを話した。公益社団法人「家庭養護促進協会」(神戸市中央区)が神戸新聞などと協力してマッチングを推進、血縁を超えた家族の出会いをサポートするほか、研修、啓発活動にも取り組む。何もないところからつながりを生むという点では映画と同じ。「60年ですか…長いですね」と是枝監督はうなずいていた。
映画の中の預けられた赤ちゃんはかわいいが、感動の対象として消費するようなスタンスは見せない。かといって言葉を発しない赤ちゃんの代弁者にもならない。「被害者としてとらえ、その側に立って撮ることはしたくなかった」と話す是枝監督。その広い視野が作品に奥行きを与えている。