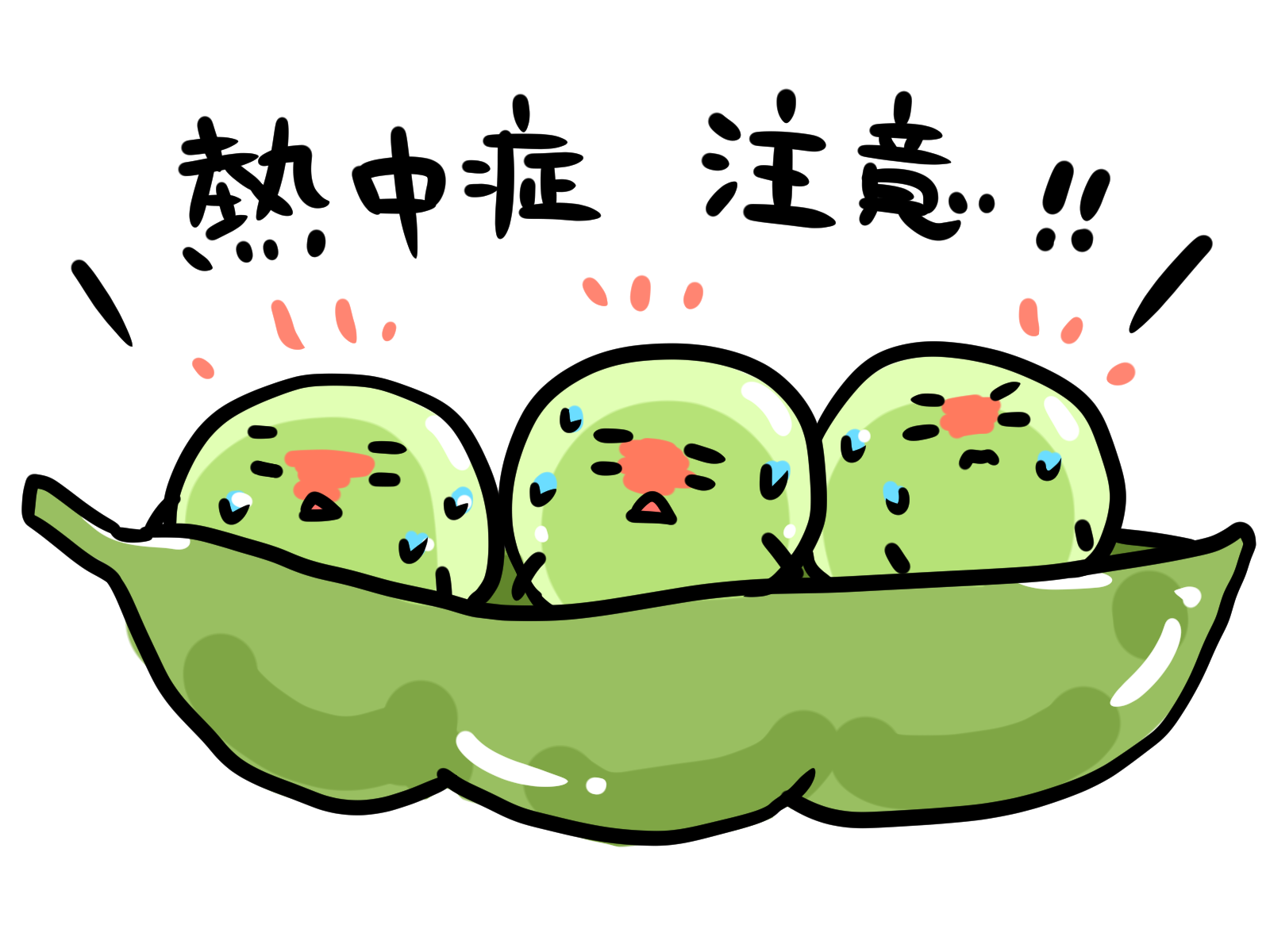市川崑(1915〜2008年)と和田
「ビルマの竪琴」「炎上」「黒い十人の女」など傑作生んだ名コンビ
光と影による映像美と大胆な映画技法を駆使した作品で知られる市川監督と、市川作品にはなくてはならない存在として活躍した夏十さん。「ビルマの竪琴」「炎上」「鍵」「野火」「黒い十人の女」などコンビによる作品は多数。夏十さんは、市川総監督による記録映画「東京オリンピック」の後は病気のため休筆したが、市川監督へのアドバイスは続けた。テレビ時代劇「市川崑劇場 木枯し紋次郎」の主題歌「だれかが風の中で」の詞も夏十さんによるものだ。
夫妻の共著『成城町271番地 ある映画作家のたわごと』
『成城町271番地』は、夫妻のエッセーを集めた共著。書名は、1950年から64年まで市川家の住まいがあった東京都世田谷区成城の住所地番から取っている。
創作のこと、日常のこと、自らを取り巻く映画界や社会のこと……。率直な筆致で記された文章からは、夫婦としての関係と共に、それぞれの表現者、個々の人間としてのまなざしが浮かび上がってくる。原本刊行時点での最新作「黒い十人の女」の絵コンテ(現在は所在不明)など貴重な資料も掲載されている。
『和田夏十の本』の編者は谷川俊太郎さん
一方、『和田夏十の本』は、83年に62歳で亡くなった夏十さんの遺稿集にして唯一の単著。2000年に出版された。未公開原稿を主に、エッセー、シナリオ、短編小説、歌詞など、さまざまな形の遺稿を収録した一冊。編者は、夫妻の盟友だった詩人の谷川俊太郎さんだ。
元の本の序文に谷川さんは<夏十さんは問い続けるひとだった>と記しているが、生きること、家庭のこと、女性であること、シナリオライターという仕事のことなど、縦横無尽に考えをめぐらせ、本質をつかみ出す文章は、読む者の心にまっすぐ飛び込んでくる。<男の人が求めている女>への違和感、<消滅することのない幼児性とのたたかいが人間の一生>という鋭い指摘も印象的だ。谷川さんは<夏十さんは時代に先んじていた>とも記しているが、確かに同書の中の夏十さんの言葉は時を経て、ますます重要に思えてくる。
「造本面での垣根」が高かったが…
この2冊の増補電子書籍版を発売したのは、ディスカヴァー・トゥエンティワン。電子書籍での復刊を企画し、自ら編集した森遊机さんは、映画研究家であり、書籍編集者。『市川崑の映画たち』『映画「東京オリンピック」1964』といった市川監督作品のたのしみを深める名著を、企画・執筆・編集してきた。
今回の復刊を実現させたのは、「お二人のみずみずしいエッセー群が、多くのファンに読まれる機会がないまま眠ってしまうことを惜しむ気持ち」から。特に『成城町271番地』に関しては、これまで何度か復刊・復刻を構想してきたが、「造本面での垣根の高さに手が出せずにいた」と森さんは言う。市川監督ならではの美的感覚、デザインセンスが行き渡った単行本(原本)の装丁・造本は、「紙による市川作品と言っていいくらい手のかかったもの」だったが、それだけに、丸ごと復刻するのは、技術的にもコスト的にも難しかったという。
だが、2022年に入って、森さんが電子書籍の出版に携わるようになり、転機が訪れた。電子書籍ならば、たとえば、原本の装丁・造本の重要パーツをカラー画像として巻頭に収録することで、本のたたずまいを視覚的に伝えることが可能だからだ。市川夫妻の長男で、二人がのこした資料の保存や作品普及を行う「崑プロ」代表の市川
渋いオリーブグリーンと黒を基調にしたカバー。布クロス装の表紙の背には、書名を刻印した桜色の四角い紙。次は赤い見返しが目に飛び込んできて、さらにページを繰れば白一色の扉ページに明朝体文字が……。電子書籍版の巻頭には、原本の造作を目で楽しませる画像の数々が収録されている。
貴重な内容、増補でさらに分厚く
電子書籍の仕様では、文字組みや写真のレイアウトは厳密に原本通りにはいかない。また、再録されなかった文章や写真もある。たとえば、原本出版時には作家の野上弥生子と三島由紀夫、プロデューサーの藤本真澄の3氏が「序文」を寄せたが、三島に関しては、電子書籍への再録は許諾しないという遺族の意向を受けて掲載されていない。
ただ、そのまま掲載された写真や図版には「黒い十人の女」の絵コンテをはじめ、本書でしか見られない貴重なものを含んでいる。
また、「別棟」と銘打った増補部分には、近年、崑プロで発見された、市川監督自身が作った本書に関する資料や写真類を初収録。さらに当時の版元の原稿用紙に書かれた市川監督直筆の未収録原稿の一部、市川家の生活について建美さんが振り返るインタビューも掲載するなど、さまざまな形で内容の厚みを増している。市川監督撮影による、成城町271番地時代の家族スナップもあるが、構図といい、光と影の生かし方といい、まるで映画の一場面のような完成度。271番地の家の前にかかっていた横長の表札も、映画のスクリーンに映し出されるメインタイトルのよう。その美意識は、市川監督の映画の世界と通底している。
『和田夏十の本』の原本は、イラストレーターの和田誠さんが装丁を担当。市川監督が描いた夏十さん愛用のライティングデスクのイラストが装画として使用されている。こちらも、原本の装丁を画像として収録した上で、電子版オリジナルの増補が加えられており、写真をはじめ、夏十さんによる四つの文章の冒頭部分の直筆原稿や、編者である谷川さんが今回新たに寄せた「思い出」という文章も掲載されている。
モノとしての本、とりわけ美しい装丁の本を手にとるよろこびは、もちろんなくしたくない。だが、過去に出版され入手困難になった本に新たな命を吹き込む上で、電子書籍だからこそできることがあるのだ。
◇電子書籍版の『成城町271番地 ある映画作家のたわごと』(2750円)、『和田夏十の本『(3300円)はいずれもディスカバー・トゥエンティワンから発売中。同社ウェブサイト(https://d21.co.jp/)の「本を探す」のコーナーから書籍名を検索すると、それぞれの詳しい情報が読める。