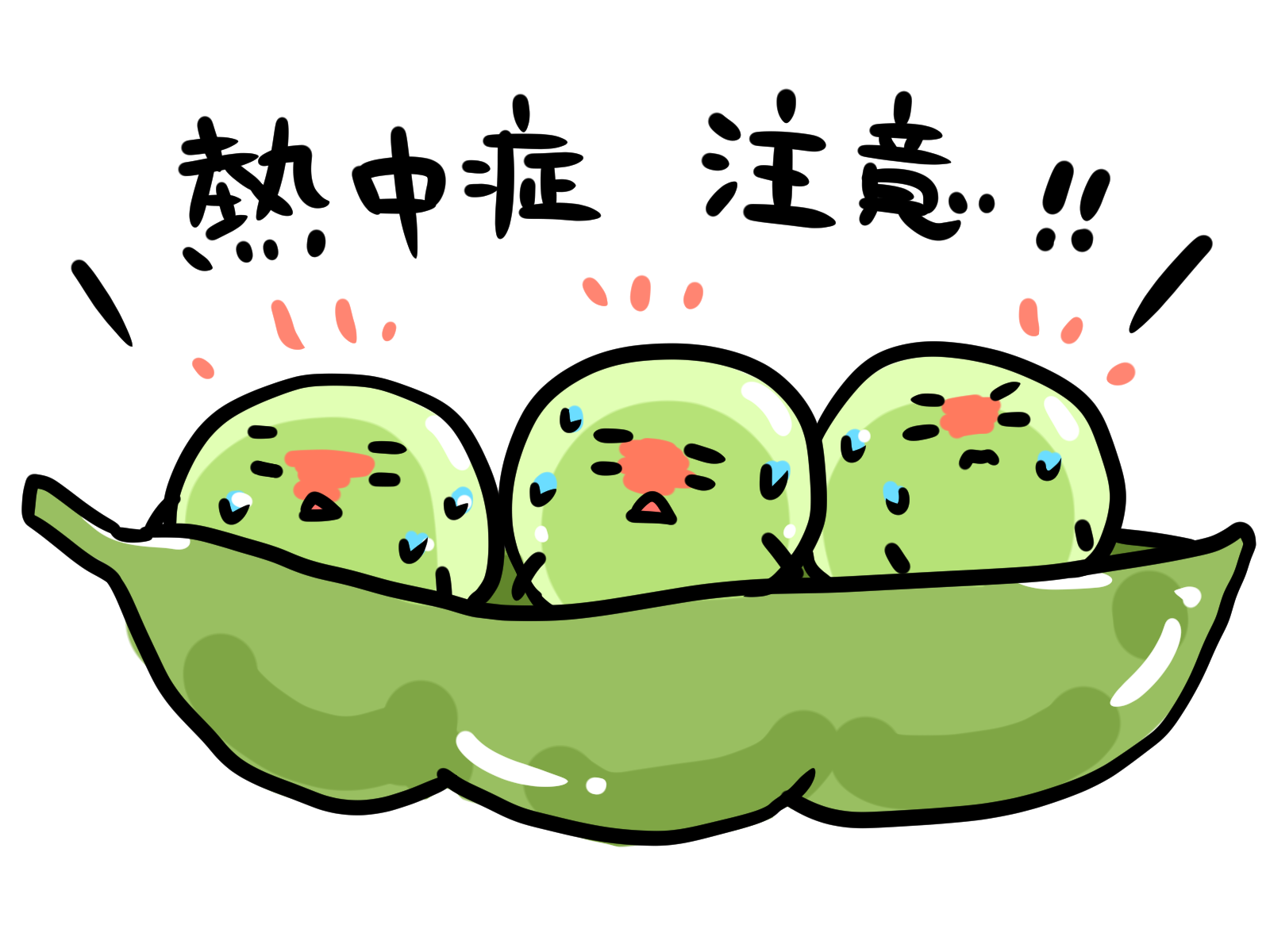日本大芸術学部映画学科の学生たちが企画した映画祭「領土と戦争」が12月2〜8日、東京・渋谷のユーロスペースで開催され、全14作品が上映される。同映画祭は今年で12回目だが、テーマ・作品選定から上映・ゲスト交渉、チラシ・パンフレット制作、会場運営に至るまで学生主導で行ってきた。学生たちに映画祭にかける思いを聞いた。
今年の映画祭を企画したのは、映画学科「映画ビジネス」ゼミの3年生14人。全体を統括する三好恵瑠さん(21)は今年のテーマ選定理由を「いちばん身近な時事問題だった」とし、2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻や沖縄返還50周年などを挙げた。
その上で、今年で国交正常化50周年の中国をはじめ、北方領土を実効支配するロシアを念頭に「日本はいまださまざまな国との領土問題を抱えている。この映画祭を通じて、領土というものが何かを考えてほしいと思った」という。
過去には女性や宗教、マイノリティー、朝鮮半島、中国などが映画祭のテーマとなった。今年は領土問題と戦争という観点から捉えた11作品と沖縄関連の3作品が上映される。
ポーランド映画「カティンの森」(アンジェイ・ワイダ監督)は、多数のポーランド人将校の遺体が発見された「カティンの森事件」が題材。日本での権利が切れていたため、矢川紗和子さん(21)がポーランドの権利元と直接交渉し、上映を実現させた。
矢川さんは「作品の中でポーランド兵を殺したのはドイツ兵ではなく、実はソ連側が虐殺していたという記録映像を見る場面が登場する。作品に込めた監督の思いとともに、映画の中に戦争という事実が刻まれており、映画が戦争を描くことの大切さが伝わる作品」と紹介した。
阪東妻三郎主演の「狼煙は上海に揚る」(稲垣浩監督)は、昭和19年に公開された国策映画で「大東亜共栄圏的な思想がきれいに透けてみえる」(三好さん)という。
「アルジェの戦い」(ジッロ・ポンテコルヴォ監督)について、毛利圭太さん(21)は「まるで自分自身がその現地に行っているような感覚になれる映像の力がある」と評価した。
高倉悠伸さん(21)は「私たちの世代からすると戦争は非日常的なものだったが、今は戦争が日常に入り込んできて、だんだんとその実感が薄れていることは良くないことだ。映画祭を通して何かしら見直すきっかけになってくれたら」と来場を呼び掛けた。
3日の「ひめゆりの塔」(今井正監督)の上映後には、作品に出演した女優、香川京子さん(90)が登壇予定など、ゲストによる作品に関連したトークイベントも開催される。
前売り券(一般・学生ともに)900円。当日券(一般)1300円、(学生・シニアなど)1100円。問い合わせは渋谷ユーロスペース(03・3461・0211)。
(水沼啓子)