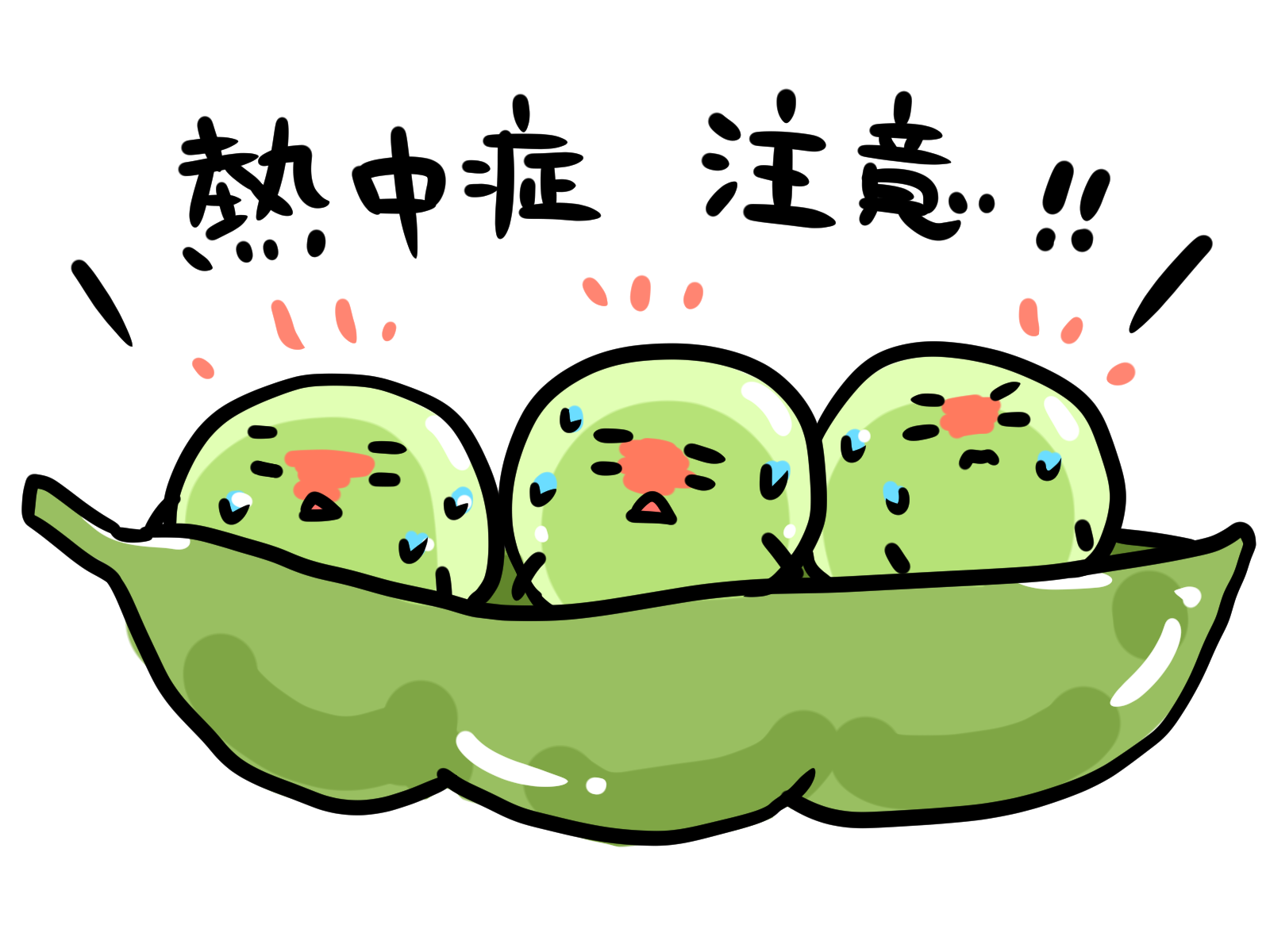世界で長編アニメーションの制作が盛んになり、扱われる題材や主題も広がりを見せている。この日行われたのは、4人の監督を招き、それぞれのアニメーションへの向き合い方と、その先にある可能性について語り合うシンポジウム。モデレーターは、アニメ評論家で東京国際映画祭アニメーション部門プログラミング・アドバイザーの藤津亮太が務めた。
アニメーションのポテンシャルを語り合うなかでは、手描きアニメの重要性ついて熱い意見が交わされた。『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』(01)や『かがみの孤城』(22)で知られる原監督は、「最近の若いアニメーターは、レイアウトを描けない人が多いんですよ。なぜかというと、レイアウトを3Dで作ってしまうことが多いんですね。ちゃんとした背景の原図を描けない人が多い」と現状を語り、「3Dでレイアウトを作ると正確なんです。正確だけれど、アニメーターってキャラクターだけ描く仕事じゃないと思うんですよね。板津くんはちゃんとレイアウトも描ける。リアルなレイアウトも、ちょっとラフなシンプルなレイアウトも描ける。それも含めてアニメーターの仕事だと思うんです。そういうところがどんどん失われていっている気がします」と持論を述べた。
『北極百貨店のコンシェルジュさん』(公開中)の監督で、原監督の『百日紅〜Miss HOKUSAI〜』(15)にも参加していた板津監督は、「アニメーターがレイアウトを描く意味というのは、正確だとか、パースが合っているとかではなくて、“カットの印象を作ること”だと思うんです。感覚から始まって、次の人に渡せるものにするというのがアニメーターの大きな仕事」と絵コンテに込められている感情や感覚をつかむことが大切だと説明。原監督は「手描きのレイアウトって、微妙に正確じゃないと思う。だけどそれが味になるし、それこそがアニメーションだと思う。多少、いい嘘をつくこと」と大きくうなずいていた。
すると『この世界の片隅に』(16)や、鋭意制作中の最新作『つるばみ色のなぎ子たち』(公開未定)の片渕監督は、「そういうことをできる人が、やたらといるわけではない。人は限られる」と苦笑い。「大事なのは自分も『やってみたい』と思う、新しい人が出てくるかどうか。一度3Dでレイアウトをやってしまったがゆえにそれがベストだと思ってしまうと、絵としてのおもしろさが抜け落ちてしまう。美術としていろいろな絵を見て感性を磨く時間を持ってほしいけれど、それをみんなに『やってくれ』という時間はない。みんな食べていかなきゃいけないし。だけど若い人たちは、それをやらないと将来的に大成しないということを理解することも大事」と悩ましい状況もある様子。
『つるばみ色のなぎ子たち』のためにコントレールという制作会社を作った片渕監督だが、そこではアニメーターの養成にも励んでいるという。「うちのスタジオはタブレットを使わずに、紙に描くことを徹底しています。真っ白なところに鉛筆を走らせたほうが、絵を描いている実感を得られるんじゃないかと思う」と実践していることを明かした。原監督は「手描きのアニメーションの伝統的な技術が失われていくと、『AIでいいじゃん』という話になる」と危機感を吐露。「片渕さんがおっしゃったように、劇場版で大変なシーンを任せられるアニメーターは本当に少ない。そういう人たちの仕事というのは、びっくりするくらいすごい。惚れ惚れとする」と例として、アニメーターの井上俊之がいまでも紙に鉛筆で描いていることに触れていた。
同映画祭にマンハッタンに暮らすドッグが友人となるロボットを自作する姿を描く『ロボット・ドリームズ』が出品されているベルヘル監督は、もともと実写映画を撮っていたとのこと。「『ロボット・ドリームズ』の原作を読んだ時に、とても感動して涙が出た。映画になっているところが目に浮かんで、アニメーションに挑戦してみようと思った。それまではアニメーション監督になるとは思っていなかった」という。本作では手描きのスタイルを採用しており、「お茶を飲む際にも量産のカップと、職人が作ったカップのどちらがいいかと言われれば、私は職人のカップでお茶を飲みたい。手描きには人間のタッチがあり、完璧さもあれば不完全さもある。そこがいいところだと思います」と熱く語った。
アニメーションの未来について、「アニメーションというのは、ジャンルではなくメディアだと思っています。限りなく、想像を広げられるメディア」と力を込めたベルヘル監督。片渕監督は「『アニメーションでこんなところにまで到達できるのか』というものを広げていくのが、僕らの仕事だと思う。『こんなこと、普通はやらない』ということをやっていくことが、(後進育成などの)役に立つという気がしています」「新しい喜びを提供したい」と新たな領域への意欲をにじませた。
原監督は「リアリズムの行き着く先って、結局おもしろくないような気もする」と言いつつも、「背景の密度があがることに惹かれてしまう自分もいる」とアニメ的なおもしろさとリアリズムの追求の間で揺れ動き、ジレンマも抱えているとのこと。「これは僕の勝手な発見なんですが」と前置きしつつ、「アニメーションにリアリティが入ったのは、宮崎(駿)さんの『カリオストロの城』で、ルパンが100円ライターを取りだした時だと思う。あれを見た時に、ここから日本のアニメは変わったんだなと思った」と思いを巡らせるひと幕もあった。片渕監督は「1971年の最初の『ルパン三世』の企画書に、タバコや車などブランドがあるものは全部はっきりとさせるというようなことが書いてあって。『カリオストロの城』はその企画書に対するパロディなんです」とにっこり。さらに「もうちょっと遡ると、『巨人の星』には読売ジャイアンツや多摩川グラウンド、後楽園や甲子園も出てくる」と現実にあるものがアニメに持ち込まれた歴史について、原監督と楽しそうに振り返っていた。
テレビアニメ「巨人の星」で主人公の星飛雄馬が大リーグボール1号を投げて、ライバルの花形満がホームランを打つカットがとても印象に残っているという原監督は、「当時、土曜日にオンエアをしていたんですが、月曜日に学校で『観たか!すごかったよな!』とみんなで真似をしていた。どうやったらあんな動きができるんだろうと。そういった技術がある限り、アニメーションの存在意義があるのではないかと思います」としみじみ。板津監督も「そのシーンをいまやるとギャグになるけれど、それを観ていた当時の小学生にとっては『そんなことをやってみたい』と思うものになった。いま僕らがやっていることも、何十年後にはギャグになっているかもしれない。演出家としては、そういったギャグになるような表現の根っこを思いつきたい」、ベルヘル監督も「サーカスを見ているように『ワオ!』と思ってほしい」とアニメーションを通して、観客に新鮮な驚きを与えたいと前のめりになっていた。
第36回東京国際映画祭は、11月1日(水)まで、日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区にて開催中。
取材・文/成田おり枝