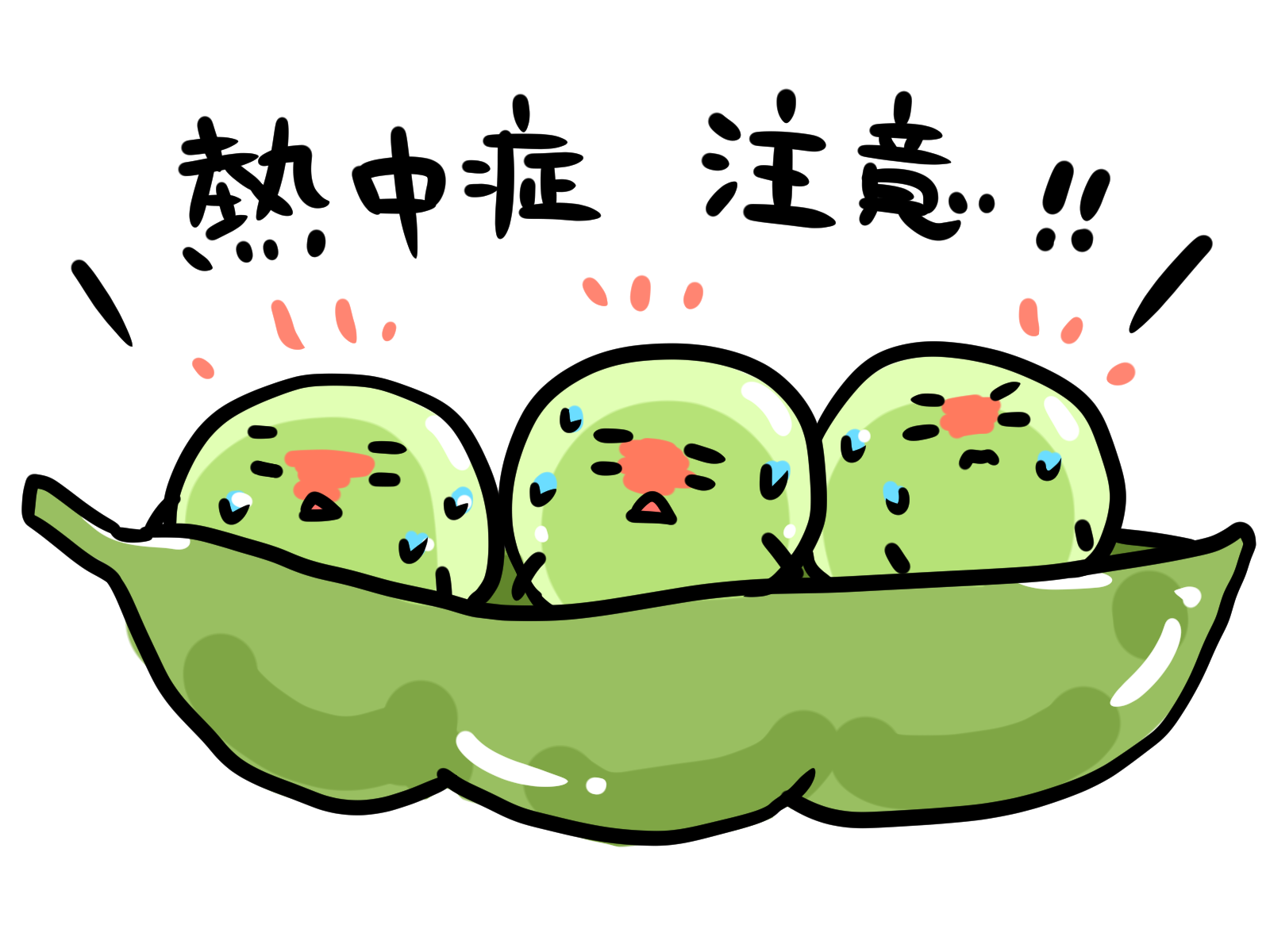阪本順治(さかもと・じゅんじ)/ 1958年生まれ。大阪府出身。大学在学中から石井聰亙(現・岳龍)監督、井筒和幸監督などの現場にスタッフとして参加。89年、「どついたるねん」で監督デビュー。「顔」(2000年)では主要映画賞を総なめにした。代表作に、「新・仁義なき戦い。」(00年)、「KT」(02年)、「北のカナリアたち」(12年)、「人類資金」(13年)、「エルネスト」(17年)、「半世界」(19年)などがある。(撮影/写真映像部・高野楓菜)
鮮烈なデビューを飾った「どついたるねん」(1989年)以来、心に何らかの“欠損”を抱えた人間を描いてきた映画監督・阪本順治さん。60代に入り円熟期を迎え、原点回帰とも言える映画を世に送り出す。
「あなた、背筋がゾッとしたことがある?」
このセリフは、監督の最新作「冬薔薇(ふゆそうび)」で、伊藤健太郎さん演じる主人公・淳が、余貴美子さん演じる母・道子にかけられる言葉だ。25歳になってもまともな職に就いたこともなく、さまざまなトラブルに巻き込まれるばかりの淳。その「じゅん」は、実は阪本順治の「じゅん」でもあった。
「僕は、映画を作るときに、主演級のキャストとは、必ず一度は2人きりで飲み食いすることにしています。男優さんなら2人きりで、いわゆるサシ飲み。女優さんの場合は、マネジャーと3人で会って、自分自身の話をしてもらう。どんなところで育って、どんな思春期を送ったのか。根掘り葉掘り聞くからには、僕自身のことも吐露します。今回、伊藤くんとも、コロナの影響で酒は挟めなかったけれど、2時間以上にわたって、いろんなお互いの恥を吐露し合いました。その上で、主人公が寄る辺なく漂う話にしようという基本線が固まって、彼と出会わなかったら絶対に書けなかった脚本ができあがった」
「映画というのは結局、自尊心を描くものだと思う」と監督は言う。淳の父・義一役の小林薫さん、義一が船長を務めるガット船(※大量の土砂や砂利を埋め立て地まで運ぶ船)の最年長の機関長・沖島達雄役は石橋蓮司さんと、名優たちが脇を固め、結果として「冬薔薇」は、「寄る辺なき自尊心を抱えた者たちの群像劇」になった。
「監督になって、たくさんのジャンルで、たくさんの俳優さんを迎えて映画を撮らせてもらっても、結局、僕自身が確固たる何かを見つけられたわけじゃない。『僕のすべてが収まっていて、もうこれ以上でも以下でもない』なんて作品にはたどり着かないわけです。俺も寄る辺のない部分を持ち続けていて、だからこそ自分の現在地を探そうとする。どこかに定住するのではなく、常に旅に出なければと思える。誰もが勘違いしながら生きていて、自分の現在地を確かめられる大人なんて少ないんじゃないかな。そもそも僕は“信念”という言葉が嫌いなんです。政治家はよく『信念は変えない』とか言いますけど、そんなもの変えていかなきゃ。信念を変えずに社会と触れ合うなら、それは、信念が古びていくことを知らずに生きているということです」
「冬薔薇」は、成長物語でもなければハッピーエンドでもない。主人公が過ちを犯し続けていく姿は観ていてもどかしいが、監督は、「映画は、人の人生の途中から始まって途中で終わるもの。主人公の人生の先が、どうなるかわからない。そのわからなさのインパクトが最大のところで終わりたかった」と語る。
「観た人に、新たな解釈をしてほしいんですよ。今の時代、解釈を客に委ねる終わり方をすると、“無責任”とか“そんなの逃げ口上だ”と言われてしまいますが、逆に僕は、『お客さんを信用しているからできるんです』と言いたいですね」
主演クラスの俳優と飲み食いをし、その人本来のキャラクターを脚本に投影させるやり方は、デビュー作である「どついたるねん」(89年)のときから続いている。
「(主人公を演じた)赤井(英和)くんとは、しょっちゅう飲み食いを繰り返していました。脚本があがって、感想を聞くために難波のビアホールで会ったときは、赤井くんが、『本当に思ったことを言っていいんですか?』と言って、『○ページのこのシーンはいらないと思うんです』と次々にカットを希望する。最後まで聞いたら、自分の出演していないシーンは全部いらなかったみたいで(笑)。『わかった、あなたが出ずっぱりのスター映画にするよ』と伝えました」
数々の賞を受賞した「顔」(2000年)では、藤山直美さんとも何回か会食をした。
「シンプルに、直美さんが舞台上でやれない役を演じてほしかった。だから、何が好きで何が嫌いか、何が許せて何が許せないかといった、世間話のような雑談のような会話をたくさんしました。そこで本音を吐露してもらうことは、僕自身のことも問われることになります。僕の映画作りには、僕の欠点や未熟さ、恥ずかしい部分が相手にバレていることが大事。最初の会食の最後に、『では一緒にやりましょう』と言ってくださったので、そこから脚本を書いて、次の会食のときに、『人殺しの役です』と伝えたら、直美さんは、日本料理屋の畳の上でドーンとひっくり返りました。僕が、『ダメですか?』と聞いたら、『前回、一緒にやりますとお伝えしました。女に二言はございません』と。直美さんは、最後まで僕のことを『ヘンタイテインメント』と呼んでいました(笑)」
31歳で晴れて映画監督になったとき、阪本さんを、新たな“背筋がゾッとする体験”が襲ったことがある。
「『どついたるねん』を作るまでは、ものを作れば批評されるということをわかっていなかった。監督として、映画にエンドマークを付けられたことは、相当な満足度だったんですが、それが批判されると、いちいち傷ついてしまって……(苦笑)。何年か後に、『阪本はもうダメだ』と書かれたときは、その評論家を駅のホームから突き落としたる、と思ったこともあります。でも、しょせんは商売人の子、実際にその評論家に駅のホームで会ったときは、『おはようございます!』と自分から挨拶しに行っていました(笑)」
>>【前編】「映画監督に必ずなる」 17歳の阪本順治を決意させたゾッとした体験
(菊地陽子、構成/長沢明)
※週刊朝日 2022年6月3日号より抜粋