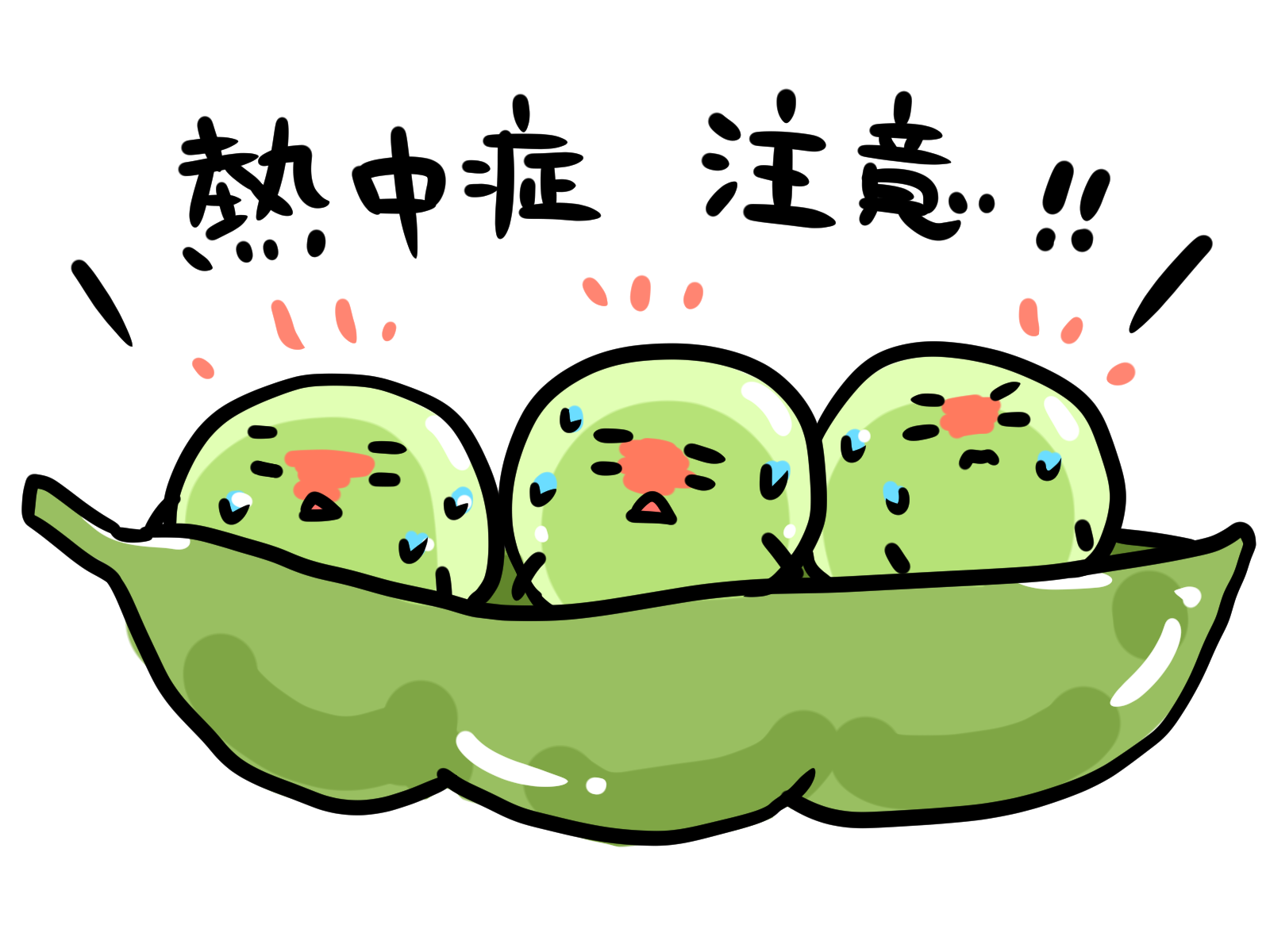■芸能界を舞台に伝説のアイドルの死にまつわる物語が展開される「【推しの子】」
「【推しの子】」は、「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」などで知られる赤坂アカが原作、「クズの本懐」などの横槍メンゴが作画を手掛ける漫画をアニメ化した作品。2020年から「週刊ヤングジャンプ」で連載がスタートし、現在コミックス11巻まで発売されている。物語は、若くして命を落とした人気アイドルのアイ(声:高橋李依)の遺児、双子のアクア(声:大塚剛央)とルビー(声:伊駒ゆりえ)が芸能界で活躍していく物語。アイの死の真相を探るミステリー要素を軸に、アイドル業界をはじめ、映画やドラマ制作の裏側も描かれることで人気を博し、数多くの漫画賞に輝いている。
■様々な視点から見たアイの姿を歌詞にした主題歌「アイドル」
本作の主題歌「アイドル」を手掛けるYOASOBIは、小説など物語を原作に楽曲を制作するユニットとして、数多くのヒット曲を生みだしてきた。「BEASTARS」第2期オープニングテーマ「怪物」は、原作者の板垣巴留による書き下ろし小説「自分の胸に自分の耳を押し当てて」、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1のオープニングテーマ「祝福」は、脚本&シリーズ構成を手掛ける大河内一楼の書き下ろし小説「ゆりかごの星」を元に制作されていた。「アイドル」は、赤坂アカによる書き下ろし小説「45510」を基にしている。
小説「45510」は、伝説のアイドル、アイが所属したアイドルグループ「B小町」の元メンバーの視点によって、アイが語られていくというもの。楽曲の歌詞は、「45510」をベースにしながら、アイの視点、B小町の元メンバーの視点、ファンの客観的な視点で構成され、アイドル=アイがなんたるかが表現されている。アクア、ルビーというワードや、アニメ第1話でアイが最期に言葉を残すシーンも引用されている。また、“アイドル様”と様付けした表現には、偶像=アイに対する、信仰と皮肉の両方の意味が込められていて絶妙。アイの生涯が描かれた第1話のラストで初めて、「アイドル」が流れた時のインパクトは絶大だった。
■アイについて語る「アイドル」と、アクアとルビーの視点で見せるエンディングテーマ「メフィスト」との対比
トラップを用いた重低音のEDMサウンドに乗せて、しゃくり上げるような独特な節回し、アイドルソング特有の掛け声などを交えながら、ダウナーなラップも繰り出される「アイドル」。ikuraのボーカルはパートごとに温度感の違いを巧みに操り、アイの飄々とした立ち居振る舞い、元メンバーの嫉妬、こうであってほしいというファンの願いなど、アイを巡る様々な視点を見事に体現している。
「【推しの子】」における物語を引っ張る実質的な主人公は、アイの隠し子であるアクアとルビーの双子だ。しかしながら、アイについて歌った「アイドル」が主題歌として、毎回物語の冒頭に流れるのがミソで、アクアとルビーの奮闘がどんなに描かれようとも、これはどうしようもなくアイが導く物語であることが、ある種の呪いのように刷り込まれていく。また、女王蜂が歌うエンディングテーマ「メフィスト」は、アクアとルビーの視点による楽曲になっており、「アイドル」との対比が絶妙。「メフィスト」もまた、「【推しの子】」を「アイドル」とは異なる視点で見事に表現している。第7話のラストで、若手俳優の黒川あかね(声:石見舞菜香)がアイをトレースして見事彼女になりきってみせたシーンでは、同曲のシングルバージョンがイントロから流れたのも印象的で、楽曲の不穏なムードとも相まってドキッとさせられた。「メフィスト(=悪魔)」が、アイかアクアか誰のことを指すのか、などを考察するのも楽しい。
■アニメと主題歌のヒットには“親和性”と“考察”が必須
近年のアニメ関連のヒット曲には「作品との親和性の高さ」に加えて、「考察する楽しみがあるかどうか」が必須となっている。LiSAが歌った『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(20)の主題歌「炎」や、Official髭男dismが歌った「東京リベンジャーズ」第1期オープニングテーマの「Cry Baby」など、どちらも劇中の登場人物の心情が巧みに織り込まれながら、作品の鍵となるものがギミックとして隠されていた。様々なメディアでそのことが取り上げられることで相乗効果を生み、社会現象と呼べる人気を博したのだ。
「アイドル」も同様だ。歌詞に込められた真意を知りたくてアニメを観始めたファンも多く、逆にアニメのキーワードが巧みに込められた歌詞にハマって、「怪物」や「祝福」などYOASOBIのほかの曲を聴くようになった人も多いと聞く。もちろんアニメだけ、楽曲だけでも楽しむことはできる。しかし楽曲に込められたギミックと伏線に触れることで、より倍増する感動と楽しみがある。「アイドル」と「メフィスト」をじっくり聴き込めば、「【推しの子】」をさらに深く掘り下げて楽しむことができるだろう。
文/榑林史章