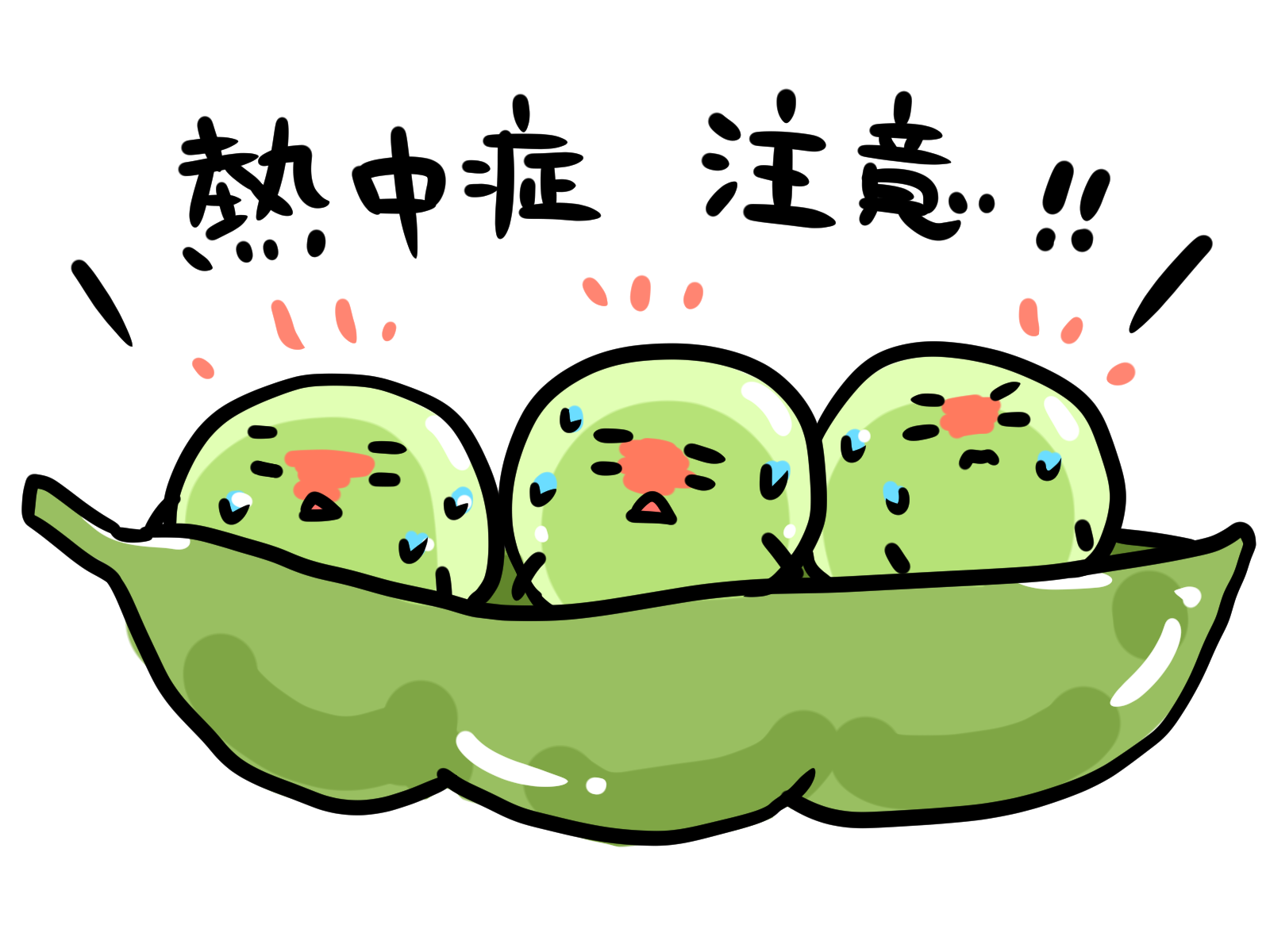しかし、このパンデミックが映画にもたらしたのはダメージだけではない。この空白期間に自分と向き合い、本当に撮りたい作品は何なのかと熟考を重ね、新たな気持ちで新作に臨む映画監督も少なくなかった。サム・メンデスも例外ではない。第一次世界大戦を舞台にした技術ノンカット映画という、大作にして離れ業的な作品だった『1917 命をかけた伝令』(19)から一転して、彼自身の記憶にある80年代を舞台にした今回の彼の作品は、いつになく親密な雰囲気が漂う。しかもそれが彼の個人史をダイレクトに反映したものではなく、海辺の町の古い映画館を中心とした多層的なドラマになっているところが興味深い。
第一のレイヤーは何と言っても、アールデコの装飾が美しいレトロな映画館エンパイア劇場だ。映画の舞台となっているのは1980年代はじめだが、その時期の映画館としてもどこか古く、ひなびた雰囲気が漂う。かつてはゴージャスであったはずのインテリアもだいぶ色褪せている。ロビーの中心に位置するカウンターにはポップコーンやチョコレート菓子を入れたガラスケースがあって、塩の味と甘い匂いが混じった古い映画館独特の匂いが漂ってきそうだ。50年代や60年代はこの街の社交場であったのだろう。規模の違いはあるだろうが、かつては世界中の小さな街にこんな映画館があった。少し寂しげな海辺の街を、そして映画館をノスタルジックに映し出すロジャー・ディーキンスの撮影が美しい。全てがまろやかな追憶の輝きに彩られていて、侘しくて寂しい風景なのに、不思議とゴージャスだ。
全盛期を過ぎた気配があっても、エンパイア劇場はまだまだ街の娯楽の中心であるらしく、老若男女がこの場所に集まってくる。ビルボードには『ブルース・ブラザーズ』や『オール・ザット・ジャズ』といった懐かしい映画の名前が並び、上映している映画のサウンドトラックが時折、ロビーまで流れてくる。しかし映画館の話なのに、映画そのものの話ではないというのが、この作品の一筋縄ではいかないところだ。映画自体の気配が希薄なこの映画館は、自分の物語をなくした中年女性の虚ろな心を象徴する場所でもある。
『エンパイア・オブ・ライト』の第二のレイヤーは、オリヴィア・コールマン演じるヒロインのヒラリーだ。自分の青春時代を投影した映画の主人公に青年ではなく、人生に惑う中年期の女性を据えた。そこがサム・メンデスのユニークなところである。
ヒラリーは無気力で、精神的な危うさが見て取れる。コリン・ファース演じる映画館の支配人ドナルドとの不毛な婚外恋愛の関係以外にも、様々な事情がありそうだ。優しさを求めても得られず、孤独が海から来る湿気のように彼女を徐々に侵食していく。こういう“壊れゆく女”はグロテスクな痛々しい存在として描写されがちだ。しかし、ヒラリーは単に枯渇し、何かを求めているだけの女としては描かれていない。コールマンを念頭に書かれた役だけあって、彼女の状況についても非常に繊細な形で表現されている。コールマンの新しい代表作とも言える名演で、この映画のコールマンは彼女と同い年の頃のグレタ・ジャクソンやアン・バンクロフトをどこか彷彿とさせる。
ヒラリーの救いは詩だ。クロスワードパズルを解くノーマンにさらりとT・S・エリオットの「荒野」の一節を教える。エリオットは「荒野」をこの映画が撮影されたケント州北岸の町マーゲイトで書いたという。新年の際にはテニスンの詩を朗読する。ボブ・ディランやジョニ・ミッチェルといった音楽のセレクトからも、彼女の言葉への愛が伝わってくる。彼女には本来、豊かな内面が備わっている。でも長い間、真心を踏みにじられて、荒んで空っぽになってしまった。
ヒラリーは、新人のスタッフとして劇場にやって来たスティーヴンに映画館の閉鎖されている最上階の美しいサロンを見せるが、そこは彼女の隠し持った本質を物語る場所でもある。二人はそこで傷ついて迷い込んだ鳩を助ける。この鳩の姿はもちろん、いつか映画館から旅立っていくスティーヴンの姿を暗示している。
2トーンズの音楽を愛し、年上のヒラリーに寄り添う青年スティーヴンを演じたのは、マイケル・ウォード。スティーヴ・マックィーンのオムニバスドラマ「スモール・アックス」では、ジャマイカ系の若者たちが集まるパーティを描いた名作回「ラヴァーズ・ロック」で主演格を演じて注目された。80年代の音楽シーンとサッチャー政権下の黒人差別問題がリンクしているという点で、「スモール・アックス」の彼の出演回と『エンパイア・オブ・ライト』は不思議とリンクしている。スティーヴンと彼の愛する音楽が、この映画における重要な第三のレイヤーである。サム・メンデスとこの映画で映写技師を演じるトビー・ジョーンズが若くからの友だちで、二人で地元の2トーンズのイベントに踊りに行っていたという話を知って、嬉しくなった。若かりし日の彼らはスティーヴンと同じようなファッションで決めて、いそいそとパーティに出かけたに違いない。
ヒラリーにとってスティーヴンは可能性の溢れるまぶしい存在だが、近づくと黒人差別に悩み、シングルマザーの家庭で育ち、小さな港町で数少ない未来の選択肢を模索する彼の苦悩が見えてくる。自分のことしか見えていなかったヒラリーが新しい世界に触れる瞬間だ。そこには光だけではなく、闇もある。映画のフィルムも同じだが、映写機を回すノーマンは言う。「観客が見るのはまばゆい光だけだ」。
長年、映画館に勤めていたのに上映作品をろくに見たことがなかったヒラリーは最後、ノーマンに自分のために映画をかけて欲しいと頼む。彼女のためだけの特別上映でかかる映画がハル・アシュビーの「チャンス」(79)だというのが嬉しい。長い間、大富豪の庭師として暮らして外に出たことがなかった男が、雇い主の死をきっかけに世間に出ていく話である。空っぽの廃墟のようだったヒラリーの心に、新たな物語を宿す映画としてふさわしい。
ヒラリーはそのチャンスをくれたスティーヴンに、彼女らしい贈り物をする。英国の詩人フィリップ・ラーキンの詩集である。その中のTreeという詩にスティーヴンは目をとめる。五月になって新緑が盛りになる様子に、死んでいくものの悲哀と新たに生まれいずる希望を描いた詩の中に、二人のロマンスの欠片が潜んでいる。年齢の離れた男女の恋を表すMay- December Romanceという言葉がある。二人の関係も当てはまる言葉だが、若者だけに五月が巡って来るわけでも、年齢を重ねた人間だけに厳しい冬がやって来るのでもない。冬から夏を経て、更に春へと巡っていく二人の関係は、それぞれが希望を見つけるところで終わる。
文/山崎まどか