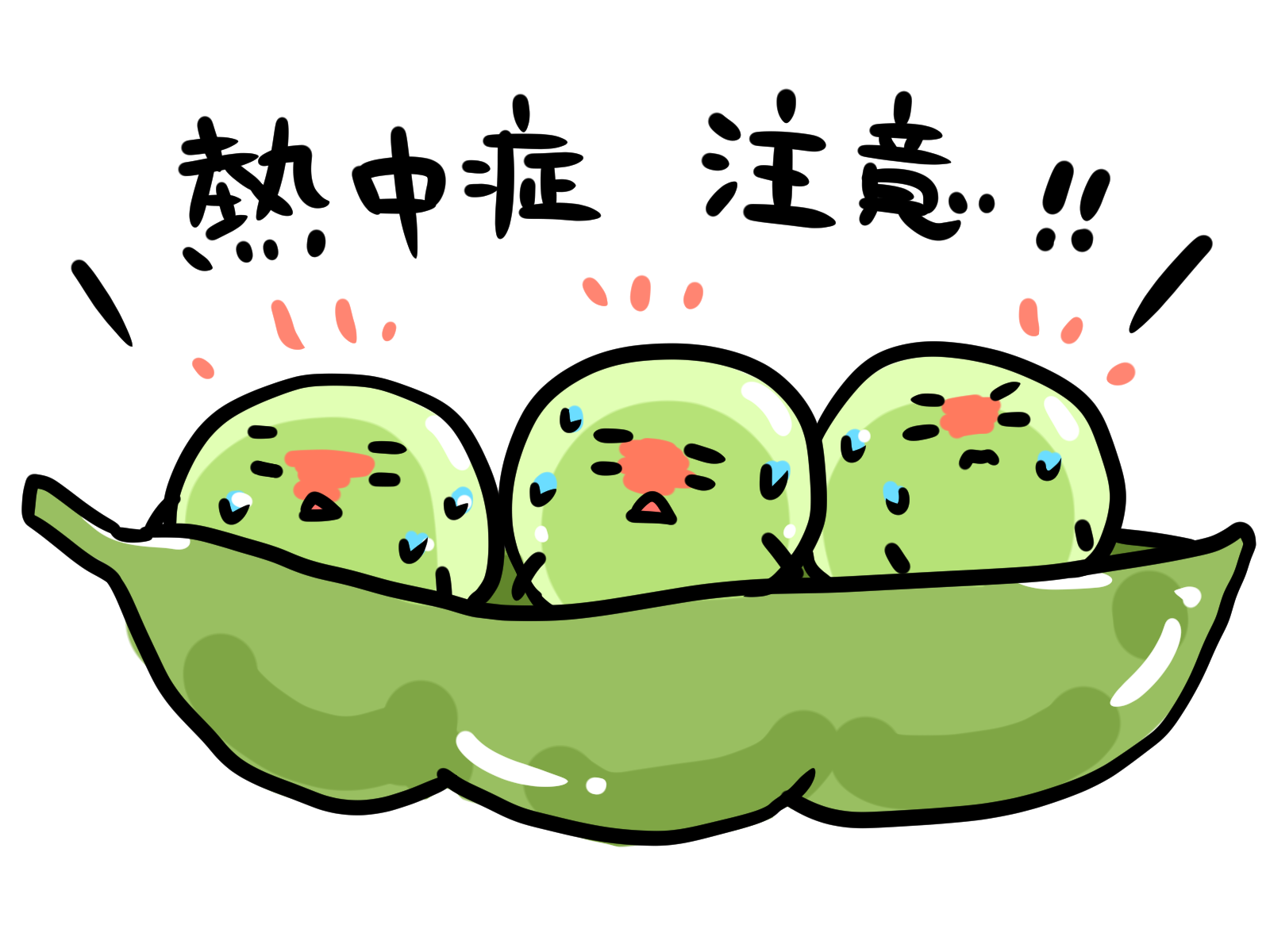『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』(05)の10年後が描かれる本作では、自分のパダワン(弟子)だったアナキンが、ダークサイドに堕ちたことに自責の念を抱くオビ=ワンの葛藤と苦悩が深掘りされつつ、10歳のレイア姫との深い絆が紡がれていく。監督は、「スター・ウォーズ」初の実写スピンオフドラマ「マンダロリアン」にも参加していたデボラ・チョウで、全6話を手掛けた。
■「新三部作の一番の違いはテクノロジーで、役者にとっては大きな違いがあった」(マクレガー)
――新三部作との大きな違いの一つは、ジョージ・ルーカスが現場にいないことですが、物語を継承していくために、現場ではどんなふうに動かれたでしょうか?
マクレガー「確かにジョージはいませんでしたが、デボラ・チョウというすばらしい監督に恵まれたし、幸運にも全話を彼女に監督してもらうことができました。シリーズには懐かしいキャラクターも新しいキャラクターも登場しますから、前とはまた違う新しさを感じたし、ワクワクしました。
また、一番の違いはテクノロジーだとも思います。新三部作と比べると、テクノロジー的にも20年分の進化がありますから。今回は“ステージ・クラフト”というシステムを使って撮影をしました。セットを覆う、巨大なドーム型のスクリーンにすべてが映し出されるので、背景などを後で足す必要がなく、すべてをカメラで実際に撮ることができます。ブルーバックやグリーンバックではなく、すべてが目の前にあることが役者にとっては大きな違いで、すごくリアルな環境で演技ができたことがうれしかったです」
クリステンセン「いろいろな意味で新三部作とは違いました。慣れ親しんだ部分もたくさんありましたが、ユアンが言っていたテクノロジーの違いもあるし、ストーリー自体が新三部作とは違う時代が舞台で、ストーリーテラー(デボラ監督)も新しい。僕も、よりダース・ベイダーと時間を過ごしましたし、そのことで役者として役に要求されるものもかなり違いました」
――第3話の対決シーンや第5話での回想シーンなどでのオビ=ワンとアナキン2人によるファイトシーンがすごく話題になりましたが、同シーンの撮影はいかがでしたか?
クリステンセン「オビ=ワンとダース・ベイダーの対決は、僕にとって間違いなくハイライトの1つでした。ライトセーバーでの戦いはどれも最高に楽しかったです。『エピソード2』の撮影時に、ユアンと僕は一緒にかなりトレーニングをしたのですが、お互いと戦うことはなかったです。ようやく『エピソード3』で直接対決のシーンがあり、あれは本当に楽しかったし、すごく記憶に残る経験でした。今回『オビ=ワン・ケノービ』で再び相まみえることができただけでなく、フラッシュバックでも対峙するシーンがあり、まるでタイムトラベルをしているようなすごく不思議な感覚でした。再びセットでこのキャラクターたちを演じているのに、時間がまったく経過していないような感じがしたんです」
マクレガー「僕も同感です。ヘイデンと仕事ができること自体が本当にすばらしいことでした。同じキャラクターをヘイデンと一緒に再び演じられることは、故郷に戻ってきたような感覚でした。当時、オーストラリアでニック・ギラード率いるスタント・チームに、複雑な殺陣を教わったあの時間は本当に楽しかったし、雰囲気もとても良かったです。それをまた今回も経験できたのは最高でした。また、みなさんも僕らが対決するのを楽しみにしてくれていることがわかっていたから、エキサイティングだったし、撮影にも熱が入りました」
■「本作のダース・ベイダーは、まだオビ=ワンに対する恨みの感情に飲み込まれている」(クリステンセン)
――第5話はスペシャルな回で、オビ=ワンがアナキンに対してまだ諦めきれてないことが垣間見える瞬間が描かれました。『エピソード3』から10年経ち、オビ=ワンとアナキンのお互いに対する想いが、このシリーズでどう変化していくのかを考えて役作りをされたのでしょうか?
クリステンセン「『エピソード3』の最後の戦いは悲劇的なものでした。観客は2人の歴史を理解しているし、お互いを兄弟のように愛していたことをわかっているからこそ、死闘を繰り広げる彼らを見ると、心が打ちのめされてしまいます。
今作のダース・ベイダーは、まだオビ=ワンに対する恨みの感情に飲み込まれているんだと思います。ジェダイに惑わされ、裏切られたと感じている。それはもちろん彼の主観ですが、オビ=ワンを恨む気持ちは深いけれど、それもまた仲たがいをする兄弟のような感じでもあり、その底流にはまだ相手に対する大きな想いが残っています」
マクレガー「昨日の夜、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』を観始めたんだけど、ヨーダとドゥークー伯爵との関係に近いものがあるよね?」
クリステンセン「確かに!」
マクレガー「戦っているんだけど、いろいろな感情がチリチリと焼けるように交錯するし、それと同時に師弟という関係性もぬぐえない」
クリステンセン「その通りですね」
――マクレガーさんは、オビ=ワンのアナキンに対する気持ちはどう捉えましたか?
マクレガー「オビ=ワンは、アナキンのことを諦めることができないんだと思います。その人の心に善があると知っている限り、その人らしくない状況に堕ちてしまったり、以前とは違う人になってしまったとしても、過去を切り捨てることはできないんじゃないかと。逆にそうするためには、相当極端な状況まで行き着かなければいけないけど、オビ=ワンはまだ、そこまでは行っていないと思います。
オビ=ワンはアナキンを愛しているし、ダークサイドにアナキンを追いやった責任だけではなく、彼の命を自ら奪ってしまったという自責の念を抱えて生きてきたんです。でも、アナキンが生きていることを知った時、オビ=ワンの中には様々な感情が渦巻いたのではないでしょうか。もしかしたら、アナキンを取り返せるかもしれない、救えるかもしれないと、希望をも感じていると思います」
――回想シーンのお2人の若さにびっくりしましたが、あのビジュアルに至るまでにかかった時間や、若作りの秘訣を教えてください。
マクレガー「仲間からたくさんの助けを借りました(笑)」
クリステンセン「デジタル界の仲間からね(笑)」
――衣装など、特に記憶に残っていることはありますか?
マクレガー「オリジナルの衣装に身を包んであのセットに戻れるというのは、やはり特別な経験で、スタッフからも熱い想いを感じたし、現場の雰囲気もすごかったです。すてきだなと思ったことの一つに、スタッフの多くが新三部作世代で、正真正銘の『スター・ウォーズ』ファンだったこと。現場は常にワクワク感であふれていたし、ベイダー姿のヘイデンがいると、それが最高潮に達します(笑)。でも昔ながらの姿をした僕たちが登場した日の衣装は『エピソード2』のものだったよね、ヘイデン?」
クリステンセン「そうそう」
マクレガー「(このシーンを撮影した日の)現場は、明らかにざわついていましたね(笑)。それに僕らもお互いと戦うことができたし。撮影も確か第3話での戦いの前に行われたので、本当にエキサイティングでした」
クリステンセン「本当に、とても特別な日でした。あのシーンを僕らで演じられるなんて!と、思いながら演じていました。デボラ監督が『アクション!』と言うたびに、僕らは戦闘の位置に立ちますが、『最高にクールなことをいま、僕らはしているんだ!』という気持ちを共有している感覚がずっとありました。本当にすばらしい経験でした」
――マクレガーさんは、フラッシュバックのシーンで、オビ=ワンとダース・ベイダーが、ライトセーバーを手にして対峙する場面が、すごくエモーショナルでしたが、その時の感想を聞かせてください。
マクレガー「僕は『エピソード4』が大好きで、公開当時、あの作品に圧倒された6、7歳の幼い自分に直接リンクしている瞬間が何度かありました。その一つが、ベイダーが初めて自分に向かってくる瞬間でした。あんな気持ちになるとは思わなかった(笑)。あのヘルメットで、あの衣装と体躯。それだけで7歳の自分に戻ったかのように反応してしまい、本物の、リアルな恐怖心に襲われました(笑)。ホラー映画を含め、いろいろなタイプの映画に関わってきましたが、仕事で怖いと思ったことはいままでなかったのに、ダース・ベイダーの顔が迫ってきた時、初めて『こわっ!』となりました(笑)」
クリステンセン「アハハ」
――クリステンセンさんは、ケガを治癒させるバクタ・タンクのなかでああいう姿で出てくるという経験は初めてだったと思いますが、あのベイダーを演じてみての感想を聞かせてください。
クリステンセン「バクタ・タンクで撮影させてもらえたのには感謝しかないです。『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』でのシーンが大好きだったから、自分があれを演じられるということはクールな体験でした。でも特殊メイクのためにメイク用の椅子に座っていなければいけない時間は長かったです(笑)。撮影も確か数日かけて行われました。どのショットもあらかじめ細かくデザインされていました。でも、あのシークエンスは大好きだし、演じるのも楽しかったです」
■「レイア役のヴィヴィアンはとてもすてきな女の子で、僕たち全員を驚かせました」(マクレガー)
――10歳のレイア役のヴィヴィアン・ライラ・ブレアさんが、まさにレイアそのもので、日本でも大反響となりましたが、共演した感想を聞かせてください。
クリステンセン「『オビ=ワン・ケノービ』のファンとして、そしてシリーズを観ているなかで、若かりしレイアのキャラクターはすごくいいなと思っています。ヴィヴィアンは、レイアをすばらしいキャラクターたらしめている本質や資質をものすごくよく捉えていて、本当に楽しませてもらっています」
マクレガー「彼女はとてもすてきな女の子で、僕たち全員を驚かせました。あれだけの大役を演じるには、彼女はまだとても若い。でも、それをものすごい活気でやってのけた、本当にすばらしい役者さんです。また、優れた監督であるデボラ・チョウの力も大きかったです。特に子役から最高のものを引き出すためには、監督に繊細かつ巧みな手腕が求められる。そういった意味でもデボラは、ヴィヴィアンという若い役者にとって、すばらしい監督だったと思います」
――レイアがなぜ息子を「ベン」と名付けたのかがわかりますが、撮影している時に、これはファンが驚くだろうと思いながら撮ったシーンや、逆に後から、そういうことだったのか!と驚いたことがあれば教えてください。
クリステンセン「ジョビー・ハロルド(プロデューサー兼脚本家)やデボラ・チョウが、みんなが楽しめるように巧みにいろいろと仕込んでいるので、何度か見直したりして、新しい発見をしてもらえればと思うから、そこはノー・コメントで。最終話にも楽しいイースター・エッグがあるので期待して!」
マクレガー「実は『スター・ウォーズ』とはまったく関係がないけど、僕個人のイースター・エッグを入れています。これはまだ誰にも言っていません。去年、僕のモーターサイクル界のヒーロー、バレンティーノ・ロッシがレースを引退したんですが、ロッシの降車の仕方はすごく独特で、それをオビ=ワンがイオピー(クリーチャー)を降りる時にやりました(笑)」
クリステンセン「え、ホントに!?」
マクレガー「普通は後方から足をまたいで降りますが、ロッシは前から足をまたいでバイクを降りるんです。だから僕も、イオピーを降りる時、イオピーの首を足でまたいで降りたんです。僕のヒーロー、バレンティーノ・ロッシへのちょっとしたオマージュです(笑)」
クリステンセン「最高!」
■「誰もが自分のなかにダークサイドとライトサイドを抱えている」(クリステンセン)
――コロナ禍で、ダークサイドに陥りそうになった人も多かったと思いますが、お2人もそういう経験はありましたか?そういう時に、自分の支えになるものはなんですか?また、ダークサイドに陥らないようにする秘訣も教えてください。
クリステンセン「誰もが自分のなかにダークサイドとライトサイドを抱えているのではないでしょうか。個人的には、父親になったことが僕をライトサイドにしっかりと留めてくれているように思います。でも、『スター・ウォーズ』がここまで心に強く響くのは、誰もがその両方を持っているからだと思うんです」
マクレガー「パンデミックは僕らを試したし、混乱させました。未来や未来の形に対する展望も、ある意味変えてしまった。僕はそれまでそういう感覚を味わったことがなかったし、それは新しいことで、怖くもありました。また、同時に、コロナ禍で家族と一緒に隔離生活を送れたことは、とても恵まれていたとも思っています。妻と子どもたちと一緒に過ごすなかで、仕事をしないことが、思っていたより得意なんだと気づきました(笑)。家族と過ごす時間をいかに愛しているかを含め、僕にとって、そういった気づきこそが、ライトサイド側に僕を留めてくれるものになっている気がします」
――「スター・ウォーズ」ファミリーになって約20年、喜びも苦しみもあったと思いますが、これからもファミリーでい続けることの覚悟を聞かせてください。
マクレガー「一旦足を踏み入れたら、そこからは仲間という感じですが、そういうファミリーになれたことは、前からとてもすてきなことだと思っています。新三部作での僕らの仕事もすごく気に入っていますが、『スター・ウォーズ』の伝説や世界の一部になれることは本当に名誉なことだと感じます。だから、こうやって引き続き背負っていけることには、格別の想いがあります」
クリステンセン「まったく同じ気持ちです。新三部作に参加し、あのキャラクターたちを演じることができたことは、本当にすばらしい機会でした。僕としても、ジョージ・ルーカスやユアンをはじめ、ものすごい才能を持った方たちと一緒に仕事ができるなんて、夢のようでした。そしていま、これだけの時を経て、また戻ってくることができて、また彼らの物語を紡ぐことができました。こんなに特別なことはありません」
取材・文/山崎伸子