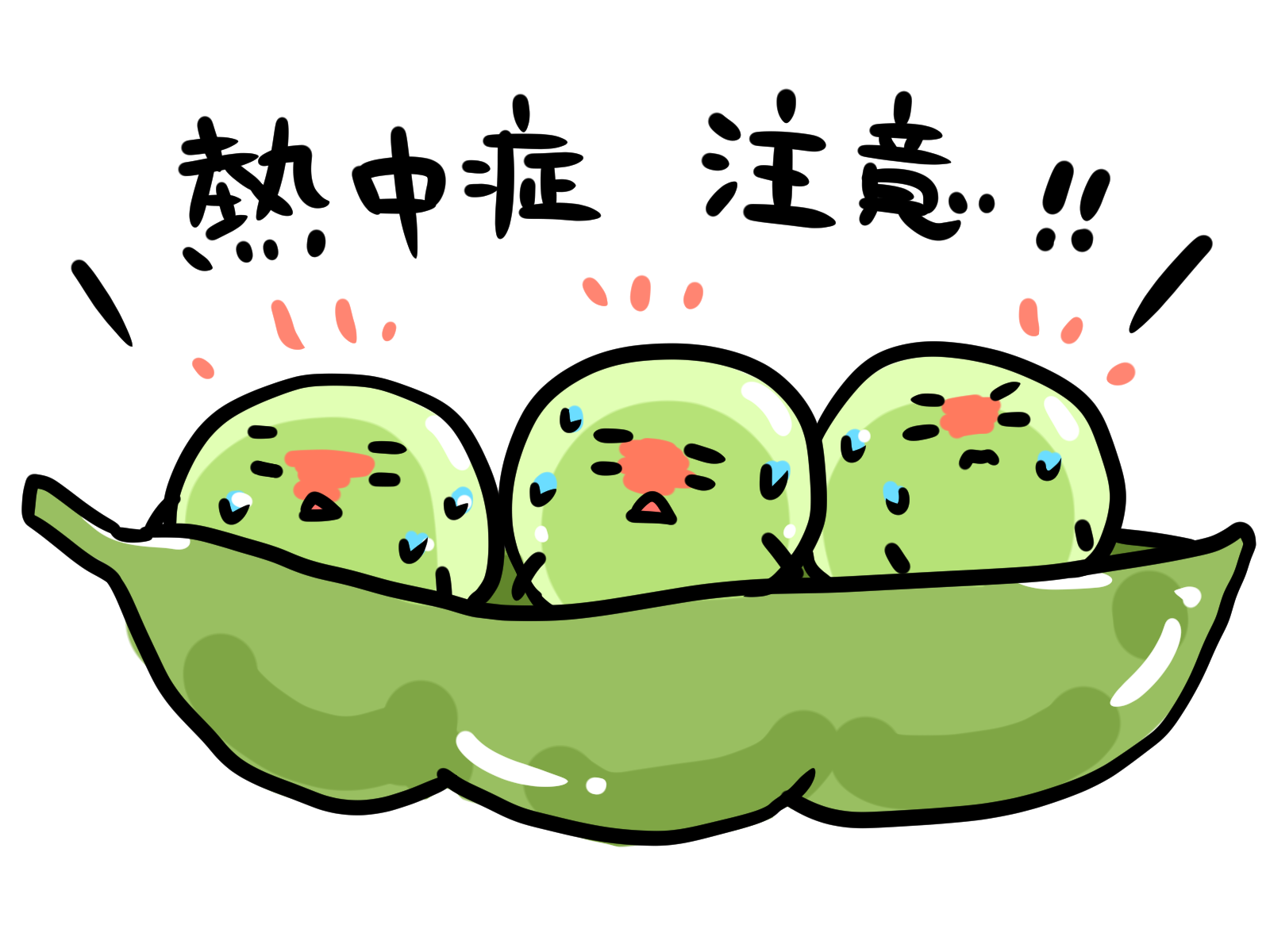■長きにわたって親しまれてきた「アーサー王伝説」と円卓の騎士、ガウェイン
「アーサー王伝説」は、5世紀後半から6世紀初めに実在したと言われる、ブリテン島(イギリス)に侵略してきたサクソン人との戦いで活躍した英雄を謳った民間伝承や創作からなる物語群(諸説あり)。15世紀後半にトマス・マロリーによって書かれた「アーサー王の死」が最も有名で、現在までに小説や映画、アニメーション、ゲームの題材として親しまれてきた。ディズニー作品の『王様の剣』(63)やテリー・ギリアム監督の『モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル』(75)、『エクスカリバー』(81)、『トゥルーナイト』(95)のほか、設定や登場人物の名前に影響が見られる「キングスマン」シリーズや『トランスフォーマー 最後の騎士王』(17)といった具合に、映画だけでもタイトルを並べればキリがない。近年では、ノーベル賞作家、カズオ・イシグロの「忘れられた巨人」にも老いたガウェインが登場するほか、ゲーム、アニメファンには様々な英雄や偉人が活躍する「Fate」シリーズでおなじみかもしれない。
アーサー王の物語は、危険な冒険や戦いに臨む英雄譚から高潔な騎士道精神、情熱的なロマンスなどの要素に満ちており、王を支える円卓の騎士たちも魅力的なキャラクターばかり。メジャーなところでは、“円卓最強”と称されながらアーサー王の妃、グィネヴィアと不義を結んでしまうランスロット、ランスロットの息子である聖杯探求の英雄、ガラハッド、悲恋に翻弄されるトリスタンなどが人気。アーサー王の甥で、勇猛果敢で優秀な騎士であるガウェインもまた、騎士道を重んじ気品にあふれている。さらに、朝から正午にかけて力が3倍になるという特性を持ち、”ガラティーン”という名の剣を愛用していたという伝説も。
一方で、ランスロットが人気のフランスで書かれた物語や、その影響を受けたマロリーの「アーサー王の死」などにおいては、引き立て役になることが多く、性格は俗っぽくなり、女たらしとして描かれるように。また、親友だったランスロットに3人の弟を殺されたことから復讐心を募らせ、彼との一騎打ちに挑むも敗北。この時、ランスロット討伐を激しく主張していたことから、円卓の騎士がアーサー派とランスロット派に二分され、その後のキャメロット王国の崩壊にもつながる原因を作ってしまったという見方もできる、負の側面が強調されている。
■緑の騎士との対決に挑み、誘惑や死の恐怖にさらされるガウェイン
そんなガウェインの高潔さと人間的な弱さの両面が描かれるのが「サー・ガウェインと緑の騎士」。物語は、ある年のクリスマスから始まる。新年を祝してキャメロット城では、馬上槍試合や馬上競技会、聖歌、宴会が15日間にかけて行われていたが、そこへ突如として衣服や髪、髭、皮膚、跨る馬にいたるすべてが緑色をした大男“緑の騎士”が現れる。騎士はその場にいる者たちに向かって、手にする巨大な斧で自身の首を斬ってみろと“首切りゲーム”をもちかけ、この挑発を受けたガウェインが見事な一振りでその首を切断。しかし、騎士は絶命しておらず、転げ落ちた自身の首を拾い上げると、「1年後、緑の礼拝堂で待っている。今度はお前が私の一撃を受けるのだ」と言い残し、笑いながら馬で去ってしまう。季節は過ぎ行き、約束を果たすため、ガウェインは緑の礼拝堂を目指して旅立つ。
旅の途中でガウェインは、ある城に数日の間宿泊することになる。城主からの歓迎を受け、礼拝堂へ向けて出発する日まで、城内でガウェインが手に入れたものと、城主が狩りで仕留めた獲物を交換し合うという約束を交わす。一方で、ガウェインは城主の奥方からの度重なる誘惑を受けることになるのだが、礼節をもってこれを固辞し続け、彼女から口づけを受けた際には、城主に口づけを返すことで約束を守っている。しかし、奥方から贈られた身に着けることで“決して死ぬことがない”腰帯は返さずに城をあとにする。
かくして、緑の礼拝堂にたどり着いたガウェインは、緑の騎士から一撃を受けるために自身の首を差し出す。しかし、騎士は大斧を振り上げると、二度寸止めしたあと、三度目で首をかすめるように振り下ろし、ガウェインはわずかな鮮血を流すのみで生還する。実は緑の騎士の正体は城に住む魔法使い、モルガンによって姿を変えられていた城主であり、すべてはガウェインの度量を試すためのワナだった。城主との約束を守って交換に応じ、奥方の誘惑にも耐え抜いたので二度は寸止めしたのだが、不死の力を持った腰帯を身に着けたままだったので、首にかすり傷を負わせたのだ。腰帯を城主に返さなかったことを恥ずかしく思い、「臆病で貪欲」と自責の念に駆られるガウェインに対し、それも命を惜しんだことが理由で大した罪ではないと諭す緑の騎士。腰帯を返却し、代わりに騎士が身に着けていた腰帯を、己への戒めのために受け取ることにしたガウェインがキャメロット城へ戻ったところで物語は終幕する。
前述の通り、フランス発の物語やマロリー版の影響もあり、女性に対してだらしないキャラクターが浸透しているガウェインなのだが、この作品では頑なに奥方からの誘いを断り続けている。また、件の腰帯のことで死への恐怖心を露わにしながらも、緑の騎士がその武勇や功績を褒め称えるように、彼が立派な騎士道精神を持った人物であることは明らかであり、改めてその偉大さが伝わる重要なエピソードとして捉えることができる。
■モラトリアムから抜け出そうともがく未熟なガウェインにシンパシー
この「サー・ガウェインと緑の騎士」は過去にも『まぼろしの緑の騎士』(73)や『勇者の剣』(84)で映像化されており、後者ではショーン・コネリーが緑の騎士を演じている(コネリーは『トゥルーナイト』にもアーサー王役で出演)。また、『エクスカリバー』では若かりしころのリーアム・ニーソンが、『キング・アーサー』(04)ではジョエル・エドガートンがガウェイン役に扮していた(エドガートンは本作にも城主役で出演しているのだが、ロウリー監督によると意識しての配役だそう)。
そして、新たに映像化される『グリーン・ナイト』では、『スラムドッグ$ミリオネア』(08)や『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』(16)のデヴ・パテルが主演を務めている。ストーリーや主人公ガウェインのキャラクターにはアレンジがなされており、原作では成熟した大人の騎士だったのに対し、本作ではまだ見習いの身で、娼館に入り浸るなどうだつが上がらない日々を過ごしている。
緑の騎士との首切りゲームを受け、人々から英雄視されるようになったガウェインだが、迫る旅立ちの日を憂鬱に思い、まるで気が進まない。やっとのことで旅立つも早々に盗賊に襲われ、縛られて所持品も奪われるなど、とにかくヘタレで情けない面が目立つ。また、原作にはないエピソードとして、ある廃墟で少女の霊に出会った彼が、近くの湖から彼女の斬り落とされた首を見つけてほしいと頼まれるのだが、その際になにか見返りを求めようともしている。
「アーサー王伝説」が好きな人にしてみれば、”こんなガウェインは嫌だ”を地で行く本作のガウェイン。こうしたダラダラ感は、進むべき道を定められず鬱屈したモラトリアム期間にいる現代人にも通じるところがあり、ロウリーが「いまっぽい」と語るように、観客がよりシンパシーが持てるキャラクターになったとも言えるだろう。一方で、女性関係に奔放で俗っぽさもあるところは、脈々と語り継がれるなかで様々な変遷があったガウェインの弱い部分を映しだしている?と想像できるところもおもしろい。
ガウェインの苦難の旅だけでなく、アイルランドで撮影された広大な自然が広がるロケーション、本物の城が使用されたキャメロット城の重厚感に、巨人の群れや旅のお供となるしゃべるキツネなど、ファンタジー作品らしい世界観でも楽しませてくれる『グリーン・ナイト』。もちろん、そのままでも十分に楽しめるが、原作やほかの「アーサー王伝説」の物語群にも触れてみると、作品への理解がより深まるはずだ。
文/平尾嘉浩