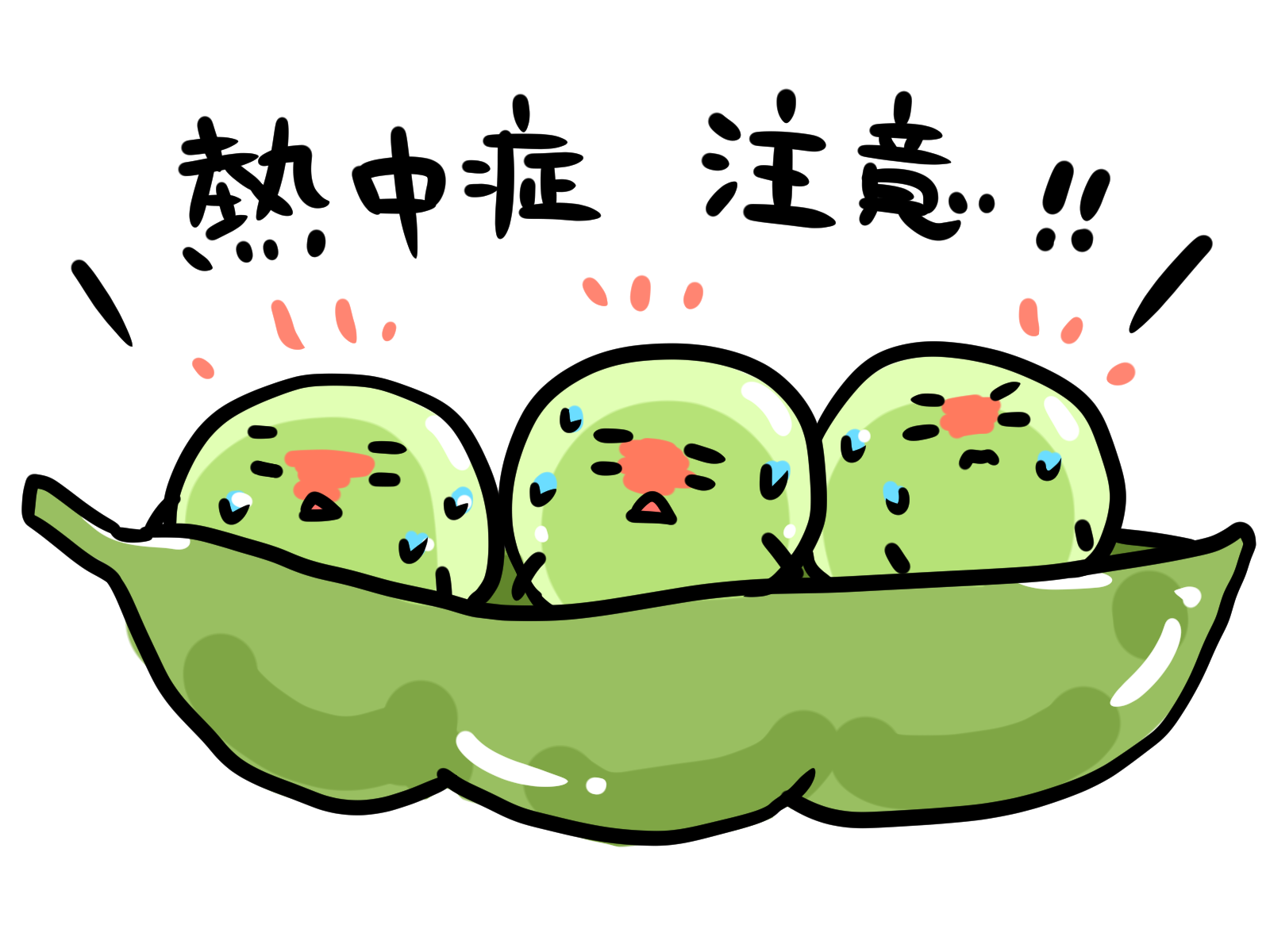ウォン・カーウァイ監督作の特徴であり、特にこの5作品にはそれぞれの“瞬間”や“時”は交錯しながらも、それらは戻らないことがテーマとして描かれている。だから、監督はこれらのレストア作品を、ただ時計を戻すような「単なる焼き直しではなく」「新たに生まれ変わった」作品と位置づけているという。20年もの時間を経たら観る側のわれわれも変わっているもので、これらの作品がどこか懐かしいような、けれど新鮮な印象を与えるから不思議だ。特にファッションに注目してみると、改めてその魅力が鮮烈に映る。
ウォン・カーウァイ作品にとってのファッションとはなにか。結論から言えば、それは“美術”である。美の視覚的表現を目指す芸術の一つ。監督は、テレビ番組制作や映画界でその手腕を発揮する前の学生時代にグラフィックデザインを学んでいるし、監督作品のほとんどに参加して衣装を担当したウィリアム・チャン氏は、編集や美術チームにも欠かせない一員だ。ファッションは、美しさの芸術表現においてなくてはならない最重要項目といっても過言ではないだろう。
■人物の心情や物語とリンクする巧みな色使い
アジア映画史において、LGBTQ映画の金字塔との呼び声も高い『ブエノスアイレス』では、トニー・レオン演じるファイとレスリー・チャン演じるウィンのカップルが、すれ違ったり、愛し合ったり、傷つけ合ったりするストーリー。香港からブエノスアイレスに舞台を移した物語の序盤、2人の世界はモノクロだったのに、再会を果たしてやり直しが始まるころには、彼らのファッションに色彩が添えられていることに気づく。ファイはレッドで、ウィンはイエローなど。たしかに、恋に落ちた瞬間にこれまでの景色が違って見えたり、急に色鮮やかに世界が写って見えたりするものだが、それらがファッションを通じて表現されているのである。知られているとおり、赤は情熱を表す色。2人の関係性が情念に包まれるにつれ、画面やファイのファッションは赤が強調されていく。そして2人がすれ違っていくたび、彼らのファッションは冷静を表す青などの寒色系で染まっていくのだ。
最も興味深いのは、同作の中一番アイコニックなシーン、2人がタンゴを踊るところで赤は使用されていないところ。仕事にいそしむファイはタンクトップにブルーデニム。自由奔放なウィンは派手なシャツを着る。彼らの日常の一部であろう、それぞれが一番“らしい”ファッションに身を包んでいる。2人は、自分が自分でいられる、そのうえで相手を愛することのできる、恋愛の頂点にいるのだ。必要なのは自分と相手であって、ほかにはなにもいらない。
『2046』においても、台詞の代わりにファッションが登場人物たちの感情を雄弁に語るところが随所にみられる。タクを演じる木村拓哉や、ワン・ジンウェンを演じるフェイ・ウォンのキュートさも見どころなのだが、美しいチャイナドレスに身にまとったチャン・ツィイー(バイ・リン役)やコン・リー(スー・リーチェン役)と現実世界の主人公チャウ・モウワンを演じるトニー・レオンのやり取りが、非常にエロティックでいい。職業柄、煌びやかなドレスを身に着けるバイ・リンはチャウと出会った時、まるで鎧かのように着飾っていて隙がない。だが、相手がどうであろうと、“私はあなたを愛しているから”と嘆くころには、彼女は文字どおり、身も心も裸にされてしまっていて、“身ぐるみはがされた”状態だから、彼だけの前では彼女はよりシンプルな装いになっていく。
バイ・リンやスー・リーチェンらが登場するシーンは、香港のホテルや社交場などのカラフルな背景だから、それとは対照的に彼女たちのドレスはブラックだったりして、センシュアルでミステリアスな雰囲気の演出に一役買っている。一方、周りの景色や状況、そしてどんな色を身にまとった幾多の女性が通り過ぎても、変わらないのがチャウだ。チャウは、イギリスの紳士のように常にきちんとネクタイを締めており、しかもノットはいつも小さくて上品で、ディンプルの華麗さや清潔感が、彼がなぜモテる男であるのかを、おおいに語るのである。
■「たくさんを見ることは、なにも見ていないのと同じ」
ウォン・カーウァイ監督作品においてファッションを通じた視覚的な美術の表現として、カラーパレットの有効的な使い方がその代表だが、それが最も顕著に表現されている作品と言えば、『花様年華』だろう。主人公の2人は、お互いの配偶者の裏切りと寂しさから結ばれた絆でつながる。2人が互いの存在を必要とするころには、それぞれのファッションもリンクし始める。少し赤みがかったドレスとバーガンディのネクタイ。逢瀬を重ねる相手の部屋とどこかマッチしたデザインがあしらわれたファッション。好きになった相手の好きなものや趣味に、自分を合わせて変化していくことはよくあることだ。だけど、やっと大人一人ずつがすれ違うことができるアパートの階段や廊下、薄いグレーのような背景は変わらない。移り変わっていくのは、恋心を含む人間だけなのだ。
『花様年華』でのその風雅な表現は、映画界のみならず世界中から称賛を浴び、2015年ニューヨークのメトロポリタン美術館で、「China:Through the Looking Glass」と題された展示を実施するにあたり、この展示を協賛するVOGUEのアナ・ウィンター氏と同美術館コスチュームインスティテュートのキュレーター、アンドリュー・ボルトン氏の目にとまったことで、ウォン・カーウァイ監督は、同展示のアーティスティックディレクターに就任した。その経緯や開催までの苦悩に密着したドキュメンタリー映画『メットガラ ドレスをまとった美術館』(原題The First Monday in May)で、監督がとあるミーティング中に放った言葉は胸を打つ。
「(観客へ)見せるもの、つまり展示をせわしないものにしないことだ。なぜなら、たくさんを見ることは、なにも見ていないのと同じことだから」。監督自身の言葉で、作品でのファッションを通じた視覚的な美術を、これほど的確に表現したものはない。監督は、人の目やセンスがどのように心をとらえるかを熟知しており、そのために「引き算の美学」を、作品を通じて問うことのできる稀有な監督なのだ。
文/八木橋恵