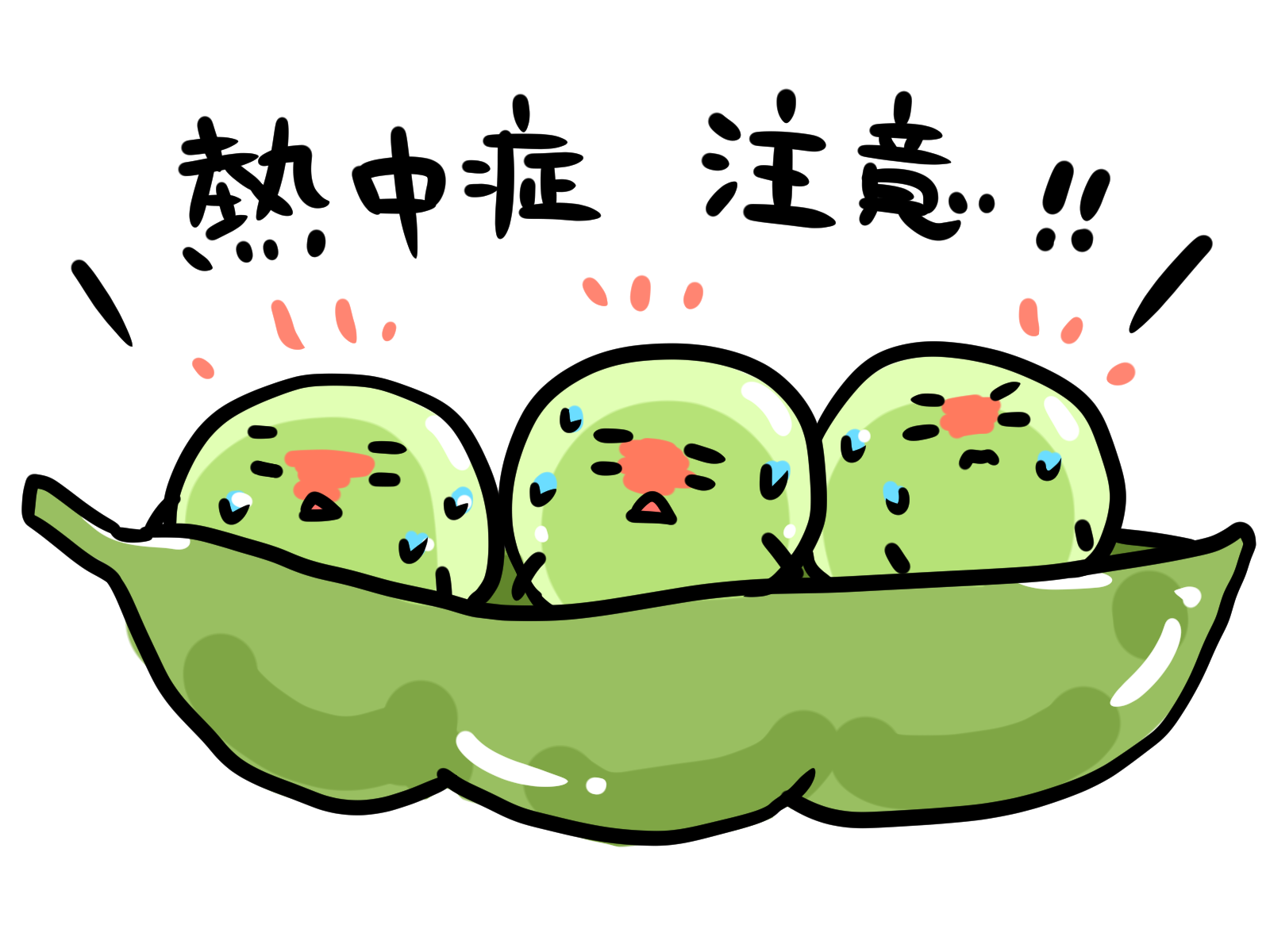そんな本作を監督したのが、実話ベースの犯罪ドラマ『凶悪』(13)や暴力団と警察の死闘を描いた「孤狼の血」シリーズなど、数々の衝撃作を手掛けてきた白石和彌監督だ。容赦ないバイオレンス描写や、人間の弱さや愚かさを見つめる作風で高く評価されている白石監督が、ヒーローや怪人たちを取り巻く環境や生き様をどう描き上げたのか?過去の代表的な監督作を参照しながら、“白石ワールド”が本作に与えた魅力をひも解いていきたい。
■善と悪が複雑に絡み合う…『孤狼の血』にも通じる世界観
本作は、1987年から放送された「仮面ライダーBLACK」のリブート作。2人のライダーの激突や、歴史の裏側で暗躍してきた邪教集団との戦いなど、オリジナル版で展開された世界観をベースにブラッシュアップし、差別や不寛容といった現代社会が抱える問題に向き合う展開、西島や中村をはじめとする演技派俳優の共演など、大人に向けたエンタテインメントとしての要素が詰め込まれた作品になっている。
正義を掲げる者が、悪の組織に立ち向かう——。この図式でまず思い浮かぶ白石作品といえば、昭和63年の広島を舞台にした『孤狼の血』(18)だろう。激化する暴力団同士の抗争を止めるため奔走する刑事たちを描いたこの作品は、暴行や金銭授受など暴力団顔負けの捜査を行うベテラン、大上巡査部長(役所広司)と正義漢の強い新米刑事、日岡(松坂桃李)の姿を通し、正義とはなにかを問いかける骨太エンタテインメント。
目的のためには手段を選ばぬ大上の強引な捜査手法、様々な思惑や欲望が渦巻く暴力団や警察の組織の歪みなど、善と悪が絡み合う混沌とした世界観は、『悪とは、何だ。悪とは、誰だ。』というキャッチコピーを持つ「仮面ライダーBLACK SUN」にも継承されている。力任せに敵の肉体を引き裂くブラックサンの戦いぶりや、民間人による怪人たちへの差別描写は、あまりの壮絶さに痛快感すら漂うアクションシーンや、マイノリティの衝突による悲劇が盛り込まれた続編『孤狼の血 LEVEL2』(21)を思わせる。
ちなみに、『孤狼の血』には血の気の多い暴力団構成員役で中村が出演していた。それ以来の白石作品出演となる中村だが、4年間の時を経て、より演技力に磨きをかけた彼のさらなる進化も楽しみたいポイントだ。
■『凪待ち』『彼女がその名を知らない鳥たち』と呼応する、奥深いキャラクター像
暴力的な取り立てなど裏家業でその日暮らしをしていた光太郎は、14歳の少女を殺す案件を請けたことからヒーローとして覚醒していく。社会から距離を置き、金のためならなんでもする——そんな光太郎の姿と重なるのが、『凪待ち』(18)の郁男(香取慎吾)である。定職に就かずギャンブルと酒に明け暮れていた郁男は、同棲中のシングルマザー、亜弓(西田尚美)の故郷である宮城県石巻市で人生の再スタートを切った。周囲の人々に支えられ平穏な日々を取り戻したように思えた郁男だが、またもギャンブルにのめり込み、取り返しのつかない“事件”を引き起こす。喪失感を乗り越えようとする郁男のキャラクター性は、いわば光太郎のプロトタイプ。あらゆることから目を背け、墜ちきった男の復活劇には、誰もが心打たれることだろう。
このように、ヒーローとはほど遠い佇まいで登場するブラックサン=光太郎。その多面的なキャラクター造形はいかにも白石監督らしいが、“異色ヒーロー”の最右翼といえば『彼女がその名を知らない鳥たち』(17)の陣治(阿部サダヲ)ではないだろうか。かつての恋人、黒崎(竹野内豊)を思い続ける15歳年下の十和子(蒼井優)と暮らす陣治。彼は十和子に罵倒されても、妻子持ちの水島(松坂桃李)と浮気をしても「十和子を幸せにできるのは僕だけ」と献身的な愛を注ぎ続けていく。命懸けで彼女を守るその歪んだ愛は悲劇へと突き進んでいくが、その先に迎えるラストシーンは、まさに“ヒーロー誕生”のカタルシスに満ちている。建築現場で働く陣治はいつも汚れた作業着を着ているが、その背中に抱えた苦悩や孤独感は、光太郎の寂しげな眼差しと重なって見える。
■『凶悪』に代表される、我々の倫理観への問いかけ
本作に登場する怪人たちは、人間と野生生物のハイブリット。普段は人間の姿をして暮らしているが、自分の意思や感情が振り切れた時に怪人の姿に変わってしまうという特性が描かれている。複雑な内面を持つ人間のメタファーでもある怪人が想起させるのが、白石監督の長編商業デビュー作となった『凶悪』だ。獄中の死刑囚の須藤(ピエール瀧)は、雑誌記者の藤井(山田孝之)に発覚していない3件の殺人事件を告白。しかも首謀者は別にいると言われ、藤井は不動産ブローカーの木村(リリー・フランキー)を独自に調査していく。気さくで人当たりがよいが金のためなら容赦なく人を殺めていく木村、情に厚いが一度キレると見境なく暴れだす須藤。そして、真実を求め木村を追う藤井ですら、社会正義を盾にした歪んだ一面が顔を出していく。
このように、社会が規範とみなしている倫理観など、様々な価値観に疑問を投げかけていくスタイルは、まさに白石作品の真骨頂だが、「仮面ライダーBLACK SUN」では、怪人と人間の対立を描くことで、どのような一面があぶり出されていくのだろうか。
■直球エンタテインメントとして完成した、新たな“白石ワールド”
本作で怪人を生みだす“悪の組織”は、総理大臣の堂波真一(ルー大柴)率いるゴルゴム党。そんなところにも、反骨の巨匠、若松孝二監督に師事した白石監督らしい体制や権力に対する姿勢が見て取れる。また、脚本に『凶悪』の共同脚本を務め、昨年は『東京リベンジャーズ』(21)のヒットが記憶に新しい高橋泉、美術にはキャリア半世紀を数える邦画界の重鎮であり、多くの白石作品にも参加してきた今村力という、白石監督からの信頼も篤いスタッフが参加。本作のテーマを“怪人たちの群像劇”とコメントした高橋が全10話で紡ぎだす重層的な世界観と、カメラに映らない細部まで徹底した作り込みを行うことで知られる今村が、その世界観をどう具現化しているのか。ぜひ画面の隅々まで目を凝らして見てほしい。
キャラクター誕生から半世紀。意欲的な布陣で新たな「仮面ライダー」の創造という難題に挑んだ「仮面ライダーBLACK SUN」。そこには、白石監督がこれまで取り組んできた、社会や人間の暗部からも目を背けないという創作姿勢が確固として息づいている。このように本作の本質は決して奇をてらった変化球ではなく、時代を反映しながらも普遍的な人間の有り様に迫る、直球のエンタテインメントなのだ。
文/神武団四郎