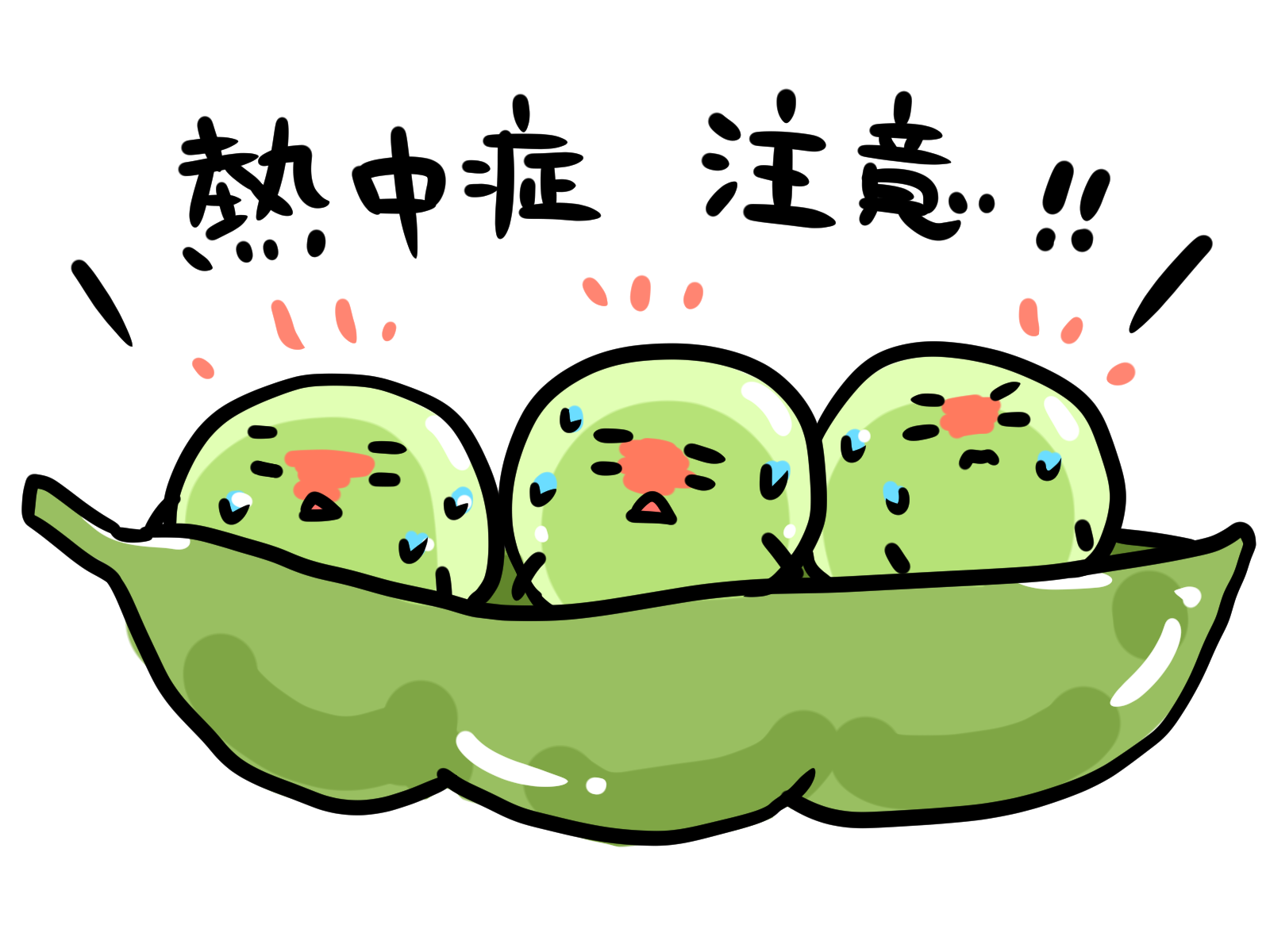各作品の監督たちは喜びの声を上げ、国際コンペティション審査委員長の白石和彌監督や、国内コンペティション審査委員長の横浜聡子をはじめ、審査員を務めた俳優の川瀬陽太、映画プロデューサーのメイスク・タウリシアら審査員たちからはお祝いのコメントが寄せられた。
国際コンペティション部門最優秀作品賞に輝いた『日曜日』のショキール・コリコヴ監督は「この映画祭で最優秀作品賞を受賞でき非常にうれしく思っています。この映画祭のおかげで初めて日本を訪問することができ、とてもうれしいです。映画は1人で作るものではなく、大勢の方、チームの力で作るものなので、私だけの賞ではなく、このチームとして受賞できたことを光栄に思います。またこの賞は、ウズベキスタンの方々の賞でもあります」と胸を張った。
同部門の審査委員長である白石監督は、本作について「ウズベキスタンの田舎の老夫婦の日常を綴っていく作品で、ほぼ中庭だけで展開していくその構成にもびっくりしましたが、なんでもない日常が、これほど愛おしいと思える時間が続くこと、それがこれだけ心を打つのだと感じた作品です。ユーモアがありながら、時に残酷で、現代社会のメッセージが込められた、美しく心洗われるスケールの大きな映画。副賞の賞金があれば、次作への力にもなるだろうと思い、また作品をつくって日本に持ってくることができるよう、審査員一同心から応援しています」とエールを贈った。
同部門の監督賞を受賞した『連れ去り児(ご)』のカラン・テージパル監督は「この映画の着想自体は遡ること10年前で、その後企画が始まったのは2019年なので、今日という日を迎えるまでに足かけ5年も経っています。どの映画監督にとってもやはり初の長編作を撮れるということ自体がすばらしいギフトです」と感無量の様子だった。
同部門の審査員特別賞は谷口慈彦監督の日本映画『嬉々な生活』が受賞。谷口監督は「この作品は1年前くらいに撮ったが、どういうふうに受け入れられるのか、どういう印象を持ってもらえるのかわからないまま、初期衝動で突っ走って制作し、完成まで持っていきました。今回初めて上映し、貴重な賞とご意見をいただいて、作ってよかったという想いをかみしめています。出演者の子どもたちも、これから未来へ羽ばたいていく世代なので、この賞がその子たちの励みにもなればと思います」と喜びを口にした。
国内コンペティション優秀作品賞(長編部門)を受賞した『折にふれて』の村田陽奈監督は「この作品は、大学の卒業制作としてみんなで撮った作品。やれることを全部やり切って卒業しようという気持ちで作った作品が、映画祭という場で観ていただけて、賞までいただけたことを光栄に思います。大学の教授で俳優でもある鈴木卓爾さんが『この映画はみんなの場になる作品だね』と言ってくださったのが心に残っています。今後も、この映画がみんなの場になって心に留めてもらえるような機会を作れるよう、作品と共に歩んで行きたいです」と語った。
同部門の審査員を務めた川瀬は「よくいう陳腐な言葉ですが、受賞を逃した方々も『選ばれなかった』ということではありません。かけがえのない瞬間がどれだけ映っているかなど、非常に主観的なで感覚で話し合った結果、この作品になった。『折にふれて』は、そういう『かけがえのない瞬間』が映っていたと思います。1本目の作品というのは、当たり前だが2度と撮れない、そういう光のようなものが映っていました」と評価した。
続いて国内コンペティション優秀作品賞(短編部門)を受賞した『はなとこと』の田之上裕美監督は「仕事もあるなか、キャストやスタッフのみんなが自分の時間を割いて参加してくれて、しかも初めてのロケ撮影や泊りがけの撮影で、自分も監督の仕方がわからないなかで、みんな一緒に考えてくれて、この作品をつくって本当によかったと思います」とチームの全員に感謝した。
同部門の審査員を務めたメイスク・タウリシアは「この作品は、非常に若い時にしか経験できないような自由さやナイーブさ、その責任が伴わない貴重な年月を、光をたっぷり当てて明るく捉え、そこで人生という重たい荷物を背負う時期がやってくるという情景を描いています。我々審査は非常に貴重なものを見ている感じがしました」と称えた。
また、SKIPシティアワードも受賞した『嬉々な生活』の谷口監督は「映画の上映に際して様々な意見を聞かせていただき、ほかのいろいろな作品を観たりと、とても充実した1週間を過ごさせていただきました。そのうえでこういったすばらしい賞をちょうだいし、さらに横浜監督からもコメントをいただきとても興奮しています。この賞に恥じないよう、これからいい映画をつくっていきたいと思っています」と語った。
同作について審査員の横浜監督は、審査員の満場一致で決定したことを明かし「すごく上手な映画作りをされる監督です。1つのシーンの結論を描くのに、直線距離ではなく可能な限りの遠回りをしながら、いろいろなものを取り入れながら最終的に描きたいことを描く方なんだなと。『1つのことを描くのに4つのおもしろいことを取り込みなさい』という有名な監督の言葉を思い出しました。遠回りしているからこそ、自然で無理のない構成の連続であることに大変驚きましたし、私自身も勉強になりました」と称えた。
また、映画祭自体の総評について、白石監督は「受賞の有無に差はないと思っています。参加された方々にとっては、この映画祭で受けた刺激が今後活きてくると思いますし、どの作品もすばらしく、我々も毎日胸をワクワクさせながら拝見しました」と全員を称賛。
「『マリア・モンテッソーリ』(レア・トドロフ監督)は、美しくてパワフル。彼女の生き方に圧倒され、かつそれを見ているお前は一体どういう生き方をするんだと問い掛けられているような作品で、まさに生き方に多様性が求められる現代に向けた映画になっていました。『子を生(な)すこと』(ジュディス・ボイト監督) は、愛があれば色々な困難を乗り越えていけるということを私たちに投げかけてくれました」。
さらに「過去の戦争や紛争を題材にした作品も印象的で、残念ながら過去の教訓に学ぶことができていない現状ですが、たとえ過去の戦争を描いていても、現代の紛争を生きる人々にメッセージを届けるという重要な役割が映画にあることを示してくれました。自分自身、これからなにをテーマにしていくかということを問い掛けながら『マスターゲーム』(バルナバーシュ・トート監督)と『Before It Ends』(アンダース・ウォルター監督)を拝見しました。最後に『別れ』(ハサン・デミルタシュ監督)が個人的に最も印象に残りました。映画祭のQ&Aセッションで、監督がおっしゃっていたのは『伝書鳩になってクルド人の生活や文化を世界中の人に届けることが自分の役割だ』ということ。すべての始まりになるのは相互理解だと思います。そういう意味では映画の役割も非常に大きくて、監督の気持ちに心を打たれました」と熱い想いを口にした。
文/山崎伸子