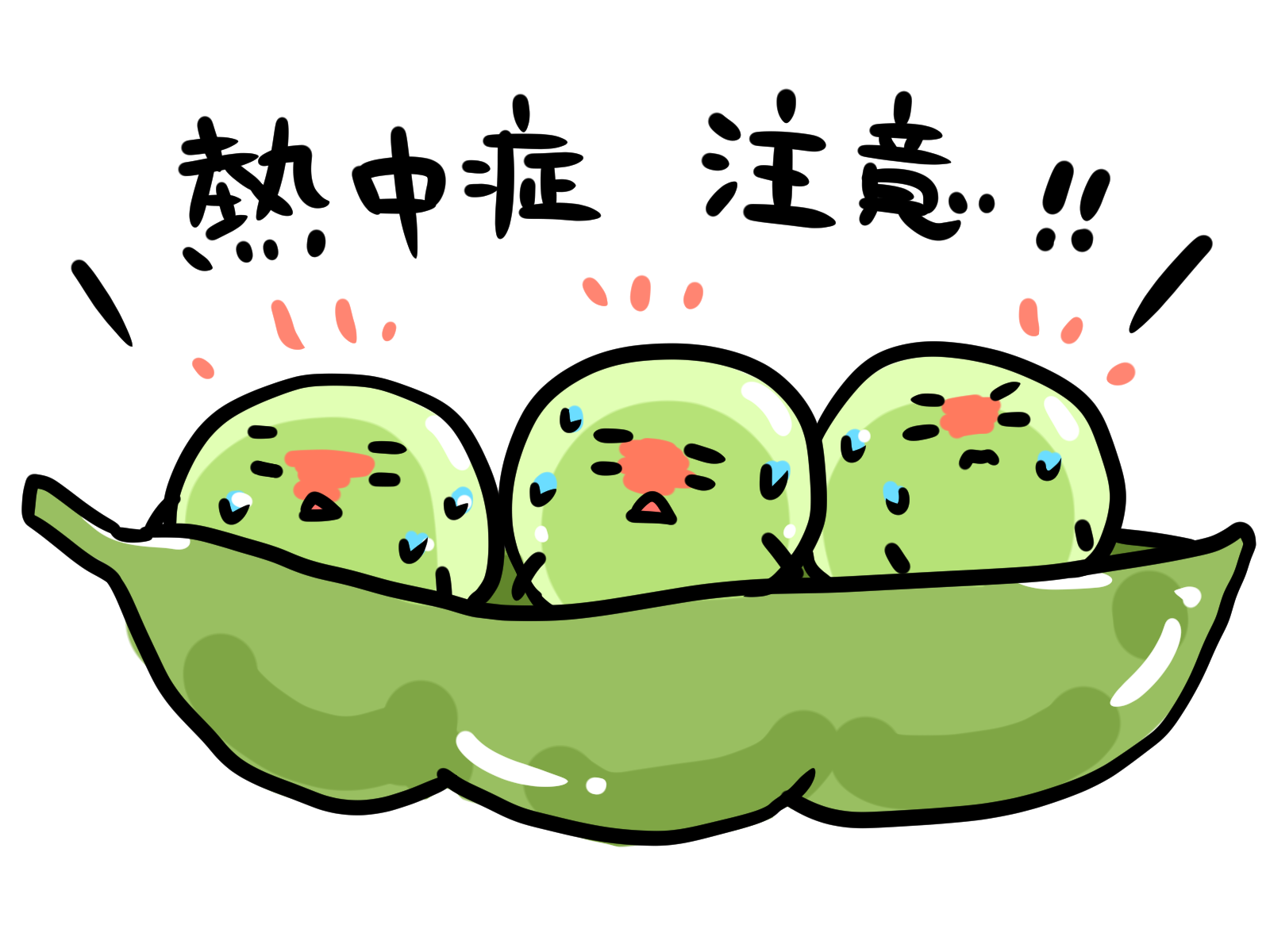おしゃれでかわいらしい少女の絵で、世の女の子たちの心をつかんだイラストレーター、田村セツコさんは、85歳のいまも現役だ。ひとり暮らしを楽しむ田村さんに心のありようを尋ねたら、カワイイの内側に、予想外にハードボイルドな一面が隠れていた。(シングルスタイル編集長 森川暁子)
かかわりのあった人は「応援団」
――最初の著書が山梨シルクセンター(現サンリオ)から出したミニブック「ひとりぽっち」(1969年)でした。昔から孤独に関心があったのですか。
「知らず知らずのうちにテーマになっていました。ひとりぼっちの、しょんぼりしてる女の子にウィンクして『OKOK、大丈夫よ』っていう気持ちで描いてます」
――よく「周りに応援団がいる」っておっしゃいますね。
「アスリートが『応援よろしくお願いします』って言うみたいに、お世話になった人や亡くなった方や、ちょっとかかわりのあった方を思い浮かべて、いっぱい応援団がいてラッキーと思うようにしてるんです。アパートの管理人さんも、話をした工事現場の人も、気が付けば応援団だと思えるし、気が付かなければ、誰もいない」
「孤独な人が陥りがちなわなは、自分だけだと思うこと。
――19歳で銀行をやめてこの世界に入り、最初はお仕事がなかったとか。
「小さいカットの仕事しかなくて、時間だけはあるから神保町の古本屋街をさまよいました。帰りのバスの窓ガラスに、やせて悲しそうな顔が映ったのを、もうひとりの自分が『あらまあ、こんなにやつれて。大丈夫。任せなさい』って励まして。すごくリアルな記憶です」
「ひとり会議」で仕事を選択
――もうひとりの自分は頼もしいですね。
「そうね。芯がね、ちょっとハードボイルド。もうひとりの自分は、両親とか応援団とか、本棚の尊敬する人々とか、いろんなとこから栄養をもらってできてるのかな。内面につっかえ棒がある感じ」
「家庭を持つかどうか迷ったときも、もうひとりの自分が『優しく温かいお母さんになろうと思ってるかもしれないけど、仕事の締め切りが迫ったら家族を我慢させたり悲しませたりすることが絶対ある』って。なるほどと思った。両方ちゃんとやる自信がなかったのね。で、仕事する道を選びました」
――ひとり会議ですね。
「そう。『どう思われますか』『ううむ』みたいな。後悔は、なくはないけど、やっぱりもうひとりの自分が助けてくれたんじゃないかな。『自分で選んだ道だからね!』って」
「ほかの人の幸せをうらやましいと思わない点は、自分でも気に入ってるの。よそに赤ちゃんが生まれて育つことが、自分の赤ちゃんのように思えてうれしい」
「私物化、じゃないけど、代々木公園を自分の庭みたいに思ったり、電車の中を自分の部屋だと思ったりしています。昔『屋根裏部屋のひとり暮らし』が夢でした。心の屋根裏部屋が至る所にあるっていうわけです」
――想像力……。
「もうね、みなさまもぜひ自由気ままに妄想してほしいと思います。『赤毛のアン』じゃないけど、想像力は栄養になります」
母と妹を介護、とにかく褒めまくった
――ご実家で6年介護をされたそうですね。
「周りには『共倒れになる』って言われましたが、母が『自宅で』と望んだので、育ててもらった恩返しのビッグチャンスだと思って。こっち(東京都渋谷区の自宅)で仕事をして、リュックをしょって毎日実家(町田市)に通いました。デイサービスやヘルパーさんにお世話になりながら。意外と楽しかったんですよ」
「お下の世話をされるのをいやがる母に『ベルサイユ宮殿のお姫さまはそういうことは平気なのよ。なんでも召し使いにやってもらうの』ってなだめたり、『お姫さまは子供のときから慣れてるけど、わたしはそうじゃない』って言われて『よく気がついたわね、さすがよ』って褒めたり。とにかく褒めまくりました(笑)」
――同時期に妹さんも介護されたとか。
「両側の部屋に母と妹が寝てて、真ん中の部屋で絵を描きながら世話してました。大変みたいだけど、あてにされるのがうれしかったのかなあと思います。ひとり暮らしだから、自分を待っててくれる人のことを考えるのが」
「2人が前後して亡くなり、張り合いがなくなりました。今も実家に風を入れに帰るんですけど、こんなに遠かったかと思います。世話をして喜ばれるのは、こちらも幸せになることなんだってよーくわかりました」
――キッチンに「お父さん、お母さん、○○さん……」と、亡くなった方のお名前を書いて置いているのですね。
「朝、名前を口に出して読むと顔が浮かびます。気持ちがふわっとあったかくなって、ああOKだなと思います。おすすめです。仲のいいお友達も亡くなるとつなげて書くでしょ。するとその中で交流ができたみたいでうれしい。去年は3、4人いましたね。増えちゃって唱えるのに時間かかるようになりました」
――年をとることを、どんなふうに捉えていますか。
「きっちり巻いたねじがちょっと緩んできた感じだから、もう自由な、大げさにいえば不思議の国に一歩踏み出したような感じ?」
「物忘れとか、口が回らないことがあっても、欲張らなければハッピーです。今のところ手と足が動いて、歩くと前に進めてうれしい。それもできなくなったら、そのとき考える。前もってくよくよしない。新しい考えが浮かぶかもしれないし、例のハードボイルドが何か言ってくるかもしれないし(笑)」
――今も、絵を描くことは喜びですか。
「はい。先日、展覧会のために物置から絵を出して並べたら、忘れてた絵がいっぱいあって、よく働きましたねーって自分であきれました」
「どんな景色の絵にも、ひとりの女の子が登場します。だんだん白髪になっておばあさんになっても、その人の中にかわいい乙女が現役で入ってる。そう思うと楽しい」
――今後のテーマは。
「死ぬことをどう思ってるか、とか人から聞かれて困っちゃって。みなさまもそうだと思いますけど、生きてるときにいっぱい楽しんだり、いっぱい発見したり、ちっちゃなことに感激したりなんかしていたら、悔いがないと思います」
たむら・せつこ 1938年東京生まれ。少女雑誌「りぼん」や「なかよし」のおしゃれページで注目され、文具などの「セツコ・グッズ」が大人気に。「おちゃめなふたご」シリーズ(ポプラ社)など物語の装画、挿絵も手がけた。近年も「白髪の国のアリス」(集英社)、「85歳のひとり暮らし」(興陽館)など著書多数。9月14〜20日、東武百貨店池袋本店で個展を予定。