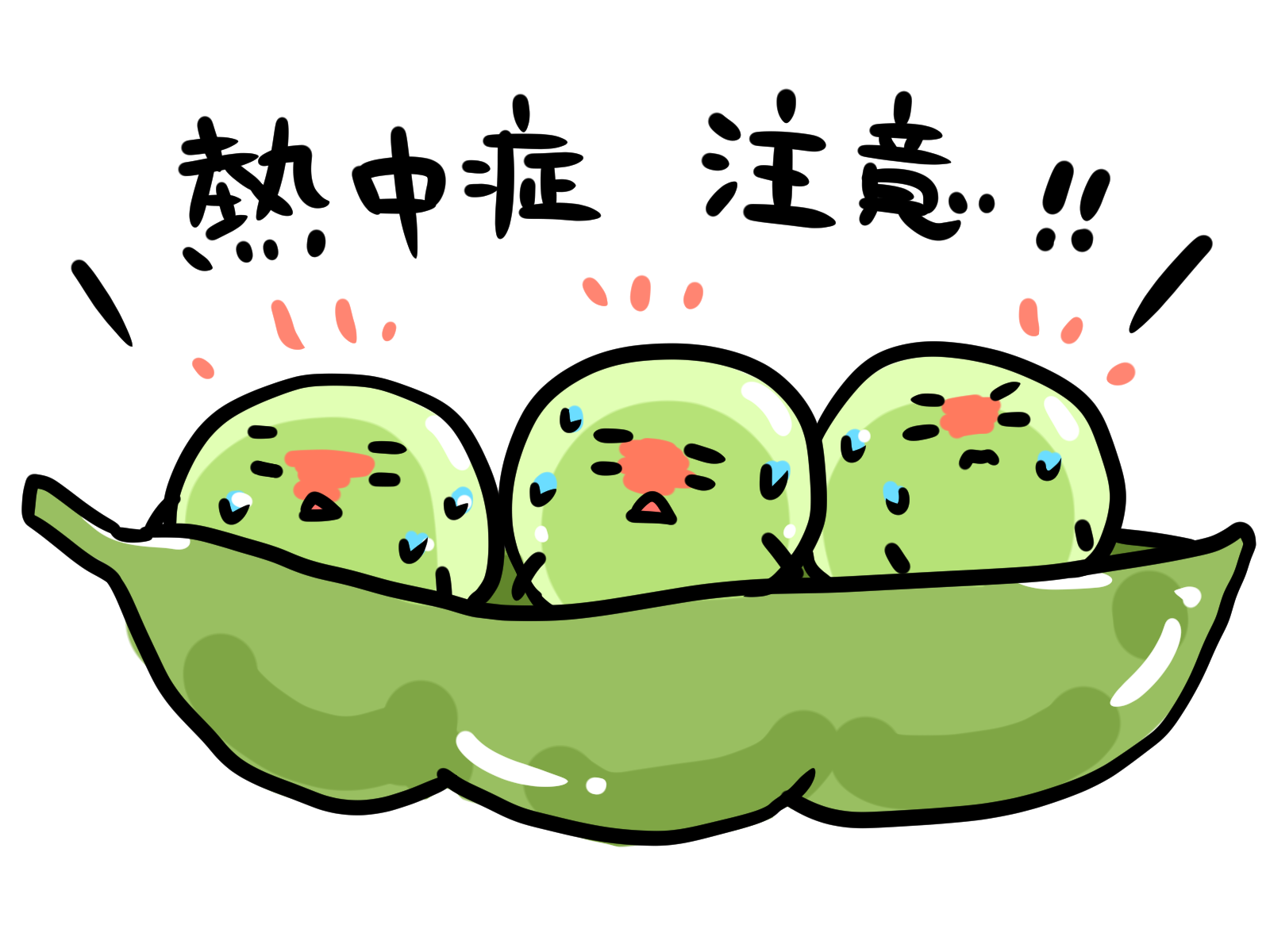『最新研究で判明したヤバい人から身を守る新知識』&『新生活で誰もが気になる第一印象を劇的に良くする方法』を学ぶ!
『ウソは体の〇〇に出る!?忍び寄る“オオカミ少年脳”の見分け方』
新生活を迎えるこの時期、新たな交友関係が広がることも多いだろう。その中で接する可能性のあるヤバい人から、どのように身を守っていけばいいのだろうか。
人間関係と切っても切れない関係にある『ウソ』。とある研究によると、人は1日に1〜2回ほどウソをついているという。「ウソのつき方によっては、脳がウソをつくことに慣れてしまい、ためらいなくウソをつく“オオカミ少年脳”になってしまう」と人間環境大学講師の新岡陽光は警鐘を鳴らした。
そもそも人はウソをついている時、脳の中でも理性や論理を担う働きのある『前頭前野』および、記憶を管理する働きのある『右の側頭領域』が活発になるという。これらの活動により、ウソをついた人はそれがばれないように取り繕おうと記憶をたどりながら、ウソを重ねていく。
また、ウソのつき方の傾向は男女によって異なる。脳の反応などの分析により、女性は他者を傷つけない『利他的なウソ』をつく傾向があるのに対し、男性は自分が得をする『利己的なウソ』をつく傾向があると明らかになっている。つまり女性は他人を気遣うウソをつき、男性は自己中心的なウソをつきやすいというのだ。これらは男女で種の存続のためにとった生存戦略に差があることが原因だという。そして、ウソの中でも自分の身を守ることにつながる利己的なウソを重ねることで、人は先述のオオカミ少年脳に陥ってしまう可能性がある。
利己的なウソをつくと、脳の中でも不安や罪悪感などに関係する『扁桃体』とよばれる領域の活動が低下する。利己的なウソにより、自らは報酬を得る一方で、特段罰を受けることもないという成功体験がもたらされると、人は扁桃体の活動が低下し、利己的なウソをつくことに慣れていくという。オオカミ少年脳に陥りやすい環境として、新岡氏は「周りがイエスマンばかり」の状態を挙げる。人はウソが周囲にばれていないと思うと、より多くの報酬を求めてさらにウソを重ねてしまうからだという。
最新の研究で、人はウソをつくと鼻先の温度が低下することが明らかになっている。これは焦りや不安を抑えるために副交感神経が働くからだと考えられている。そのほかにも、ウソをついた際、体の表面に現れる変化はいくつかあるらしく、一部は犯罪捜査などにも使われている。
ただし、それらの反応を肉眼でとらえることは難しい。周囲の人がオオカミ少年脳に陥らないように、日頃から利己的なウソをつく必要がない人間関係を築くことが大切と新岡氏はアドバイスした。

人間環境大学・講師
新岡陽光
『国民の2割は感染!?脳を操りキレさせる「トキソプラズマ」』
「怒りやすい人って周りにいませんか?」と投げかけ、怒りの感情をテーマに講義を行ったのが大阪大学微生物病研究所教授の山本雅裕。山本氏は、怒りっぽい人は寄生虫に感染し感情を操られている可能性があると指摘する。それが『トキソプラズマ』だという。
世界人口の約3分の1、さらに日本国民の約2割がトキソプラズマに感染している。この感染が、『間欠性爆発性障害』という急激に怒りや感情が爆発し、他者を攻撃してしまう疾患と相関がある。
トキソプラズマは猫との接触や、生肉を含む加熱不十分の肉によって感染し、1度感染すると、生涯感染状態がつづく(※感染は一生涯だが、インフルエンザのような発熱と体の痛み等の発症が時々あり、免疫が通常であれば一時発症し、また健康状態に戻る)。特に、外で飼われている猫から感染するリスクが高いという(※猫全てが危険ではなく、また現在ペットショップや保健所でもトキソプラズマ検査が推奨されている)。感染者全員に症状が出るわけではなく、怒りっぽい人が必ずしも感染しているともいえないが、急激に感情の制御が難しくなった場合、感染の疑いがある。
トキソプラズマが人体に入ると、腸内で好中球という免疫機能に潜伏する。好中球に潜んだまま脳に到達することで、脳内の神経伝達物質の分泌量が変化し、怒りっぽくなってしまうことが明らかになっている。ドーパミンというホルモンが過剰に分泌されることで、“怒りの防波堤”でもある前頭前野の働きを弱め、本来であれば抑制できていた不安や怒りの感情が制御できなくなる。ちなみに感染者は、交通事故に遭う確率が2.7倍、自殺率が2倍に増加するというデータもある。
一度感染すると、体内から完全に排除することはできないトキソプラズマだが、症状が出た際にそれを抑える薬がすでに開発されている。早期発見することができれば、トキソプラズマの増殖を止める薬で悪化を食い止められることもあるそうだ。現在、多くの医療機関で自身が感染しているかどうか検査を受けることができる。

大阪大学微生物病研究所
教授 山本雅裕
『他人の不幸は蜜の味 黒い快楽「シャーデンフロイデ」』
近年、SNSなどでの誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)が大きな社会問題になっている。これらの書き込みには、“黒い快感”『シャーデンフロイデ』があふれていると東北大学准教授・細田千尋は指摘する。
ドイツ語で“他人の不幸や失敗を喜ぶ感情”という意味の造語である、シャーデンフロイデ。自分が持っているものを失う不安によって芽生える嫉妬の感情や、自分が持っていないものをうらやましくほしがる妬みの感情とは、性質が異なるという。そして、このシャーデンフロイデが、人を黒い奈落へ誘う怖い感情だと細田氏は語る。
人がこの感情を抱いてしまう原因として、ほとんどの人が持っている『Better than average効果』とよばれる自分は平均よりも上だと思う心理が考えられる。国民性や文化差に関係なく、多くの人は周囲よりも自分が少しだけ優秀であると自己評価しているのだそうだ。
この心理状態により、自分は周囲より少しだけ優秀であるにもかかわらず、自分よりも劣っているはずの人が自分の持っていないものを手にしていることに対する妬みが生まれ、シャーデンフロイデが起こる。脳の観点でみると、妬みを感じた時の脳は、体が痛みを感じた時と同じ“前部帯状回”が活動するのに対し、シャーデンフロイデを感じた時の脳は、喜びを感じた時と同じ“線条体”が活動する。妬みで感じた痛みを快楽に変化させようと他人の不幸を望んだ時、私たちはシャーデンフロイデを感じるという。
この感情がエスカレートし、実際に他者を不幸に陥れる直接的な言動をとるようになると、シャーデンフロイデは不幸の作り手である『シャーデンマッハー』とよばれる状態へと変化する。例えば、SNSでの誹謗中傷や、それらの投稿を拡散するという行為がシャーデンマッハーに該当し、特に現代人はこの状態に陥りやすくなっている。他人をおとしめようという感情は、怒りや復讐心(ふくしゅうしん)が強く、やがて相手だけが幸せになるのが嫌になり、ストーカー行為などに姿を変えてしまう危険があるという。
細田氏は、必ずしもシャーデンフロイデが悪いものではないとしたうえで、頑張っているからこそ生まれる他者への妬みは、自分のパフォーマンスの向上につながると補足。妬みとの適切な向き合い方が、人生の活力になりうると締めくくった。

東北大学
准教授 細田千尋
「鍵はあなたの内受容感覚『疑似心拍で緊張を解き放つ方法』」
人前に立つ時など、さまざまな場面で感じることのある緊張。その発生のメカニズムは、脳→体→脳の3ステップであると、慶應義塾大学教授・皆川泰代は語る。
まず感情の元になる情報が視覚的・聴覚的に脳に入り、そのような情報に『扁桃体』や『視床下部』が反応してアラートを体に出す。すると、数秒間のうちに心拍数が上がる・発汗といった身体症状が現れる。その後、感情を司る部位である脳の『島皮質』が身体情報をモニタリング。こうして初めて「自分は緊張している」という感情が生まれてくるのだという。
心臓がドキドキして緊張するループが継続すると、過剰なノルアドレナリンで前頭葉の機能が停止し、頭が真っ白な状態が生まれるのだ。
また、緊張する人としない人の差について『内受容感覚』が大きな原因の1つだという。人間の感覚は視覚、聴覚、嗅覚といった“外受容感覚”と、空腹感、心拍、尿意など体内の変化に関する感覚である“内受容感覚”に分かれる。このうち、内受容感覚が鋭い人は自身の心拍に敏感になり、また不安傾向が高いこともあり、緊張しやすくなるのだという。
内受容感覚が高いことは、緊張を生じさせやすくする一方で、利点もある。内受容感覚が正確でないと、自分自身の身体状態に気づかないため、病気の進行や感情の変化に気づかない、ということが起こり、うつ傾向が高くなる可能性がある。
緊張だけでなく、うつや病気にも関連してくる内受容感覚の正確さ。自分の心拍をどれだけ正確に把握できているか、ということは、「1−{(実際の心拍と自分で数えた心拍の差)/実際の心拍}」で測定可能で、この値が1に近いほど内受容感覚が鋭い。
そして、誰もが気になる緊張解消方法だが、この内受容感覚を逆手にとったものがあるという。それは、実際の心拍よりも少し遅い振動をスマートウォッチやアプリ等で流し、リラックスしているといった感覚を脳に伝えることだ。島皮質が疑似心拍をリラックス状態と認識し、緊張が消えるという。※内受容感覚により効果に個人差がある。

慶應義塾大学
教授 皆川泰代
「第一印象は脳が2秒で判断!人見知り度を決める『DRD4遺伝子』」
「第一印象がどのくらいで決まるかというと、実は2秒」そう語るのは、脳神経科学の第一人者、早稲田大学教授・枝川義邦。初対面の際、人見知りをしてしまう人は遺伝子や脳に特徴があり、どうコミュニケーションをとったらいいかを提案した。
20世紀の心理学者、カール・ユングによれば、人間は大きく分けて内向型か外向型、どちらかよりの気質を持って生まれてくるとされ、人見知りや口下手な人は内向型に多いのではないかと考えられている。
内向型は、感情や思考など自分の内側に興味のベクトルが向かいやすく、外向型は、自分の外側の出来事や他人に興味のベクトルが向かいやすい、という特徴がある。そして近年の研究によって、この2つの属性が決まるには、ある遺伝子が大きく関わっているということが明らかになった。
それが、ドーパミンの受容体を作る『DRD4遺伝子(新奇性追求遺伝子)』である。内向型は遺伝子が短く、外向型は長いという決定的な違いがあり、それはドーパミンを受け取った時の反応の差に現れる。
内向型の人は、遺伝子が短い分少しの刺激で脳が働いてしまう一方で、外向型はドーパミンに反応しづらくより刺激を求め、外部と接触する。日本人では、外向型遺伝子は人口のたった5%程度で、その割合は他の国と比べて際立って低い。
さらに、外向型・内向型の違いは遺伝子だけでなく“脳の使い方”にも違いがあることがわかっている。アメリカ・アイオワ大学の研究によれば、初対面で人と話す際、内向型と外向型で使う脳の部分は、言語理解に関わる側頭皮質以外は異なっており、また内向型の人の方がより脳を働かせているという。つまり、内向型の人は逐一相手の顔色や話の内容と過去の記憶を照らし合わせていると考えられている。
また、内向型の人の脳の特徴として、言語処理や音声言語の算出に関わる部位である『ブローカ野』が働いており、総じて内向型は人との対話で脳を多く使う。
このように遺伝子や脳といった要因から人見知りを簡単に変えることは難しい。そこで、新たな環境でのコミュニケーションとして枝川が提案するのは、安心できる1人を見つけ、そこから人脈・コミュニティを広げていく、ということ。内向型の人は相手の話を聞く力や共感する力が強いため、1対1からコミュニティを広げるのが良いのではないか、と締めくくった。

早稲田大学教授
脳神経科学学者 枝川義邦
「0.1秒の不思議『まばたきひとつで人間関係が変わる!』」
我々人間は、ほとんどのまばたきを無意識・自発的に行っており、その回数はおよそ1分間に15~20回、一生涯では5億回にのぼるという。
そんなまばたきに関して、「第一印象でウマが合う・合わないというのは実はまばたきと密接な関係がある」と語るのは大阪大学 脳情報通信融合研究センター教授・中野珠実だ。
まずは映像を用いたまばたきのタイミングに関する実験を紹介。実験からわかったことは、皆のまばたきが同期するのは映像の意味的な句読点であったということだ。また、同様の実験にMRIを用いたところ、まばたきの度に、記憶を司る『海馬』と脳内に積み重なった情報を整理している状態である『デフォルトモードネットワーク』が活発に働くということも明らかになった。
次に紹介されたのは、人と人とのまばたきのタイミングの関係を調査した実験である。会話の代替として実験に使用した、ドラマの中で俳優がまばたきをするタイミングと、実験参加者がまばたきをするタイミングを測ったところ、両者はほぼ同じタイミングでまばたきをしていることが明らかになった。話し手のまばたきが発話の切れ目であり、聞き手は発話の切れ目で生じたまばたきに対して同期している状態といえる。
以上の実験から、まばたきによって会話の切れ目を共有することは“間が合う”ことにつながり、その結果相手に親近感がわくという。ポイントは、相手の目をみて話すことであり、それによってまばたきが同期。互いに親近感が生まれ、よりコミュニケーションが円滑になるのだ。
そして最後には、初対面の相手とまばたきを同期させる話し方を紹介。ポイントは、緩急をつけて話のリズムをわかりやすくすることだ。会話の中に“溜め(ため)”を作ると、相手もまばたきをするポイントを無意識に感じ、まばたきのタイミングがそろうことがある。

大阪大学 脳情報通信融合研究センター
教授 中野珠実