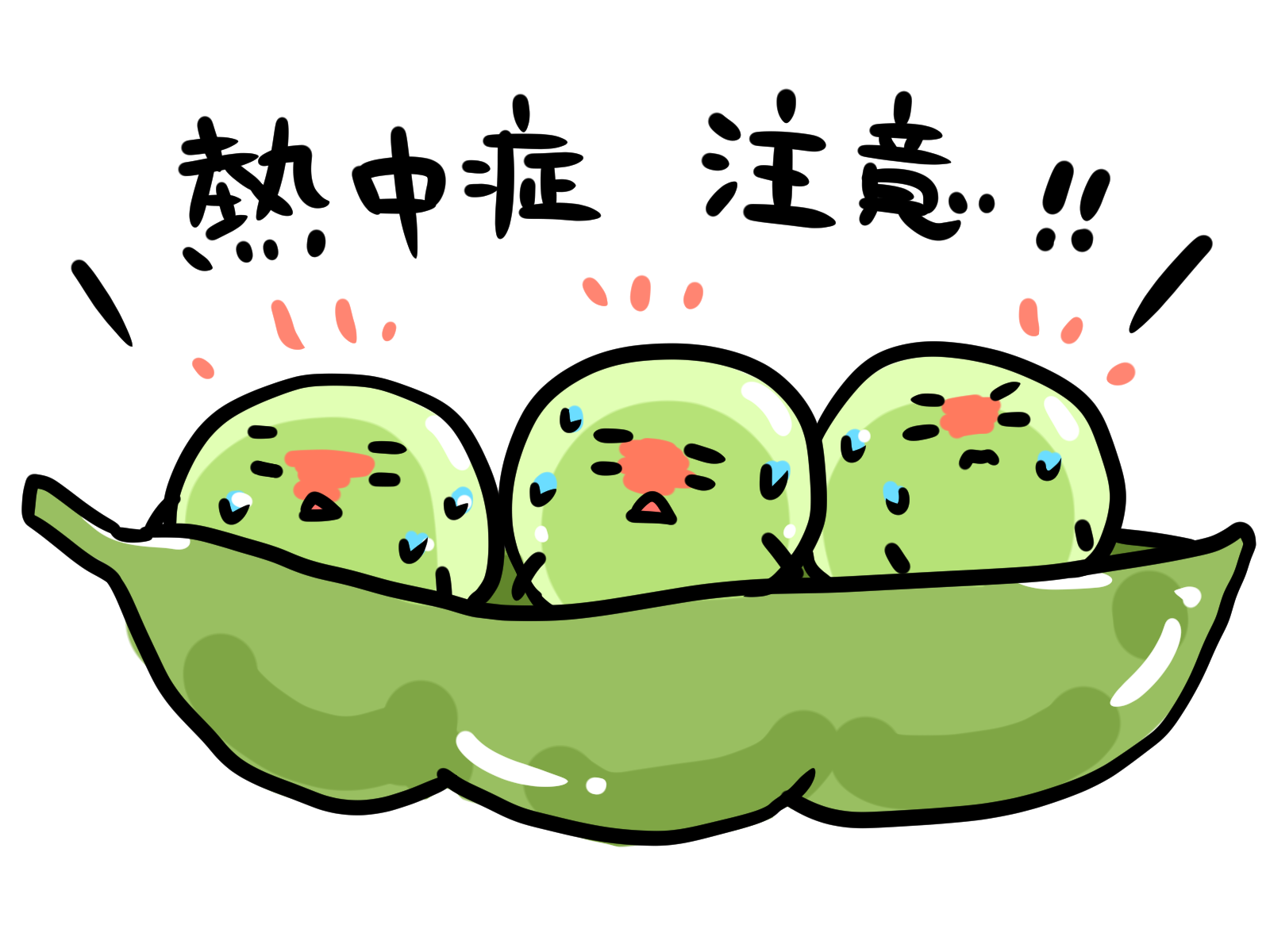今回はそんな「探偵ロマンス」の脚本担当・坪田文氏にインタビュー。脚本執筆の裏側や第2話で太郎を魅了するキャラクター・お百の着想秘話、作品に込めた思いなどについて聞いた。
■企画書を見た時は「これは大変な企画だぞと」
ーー「乱歩の知られざる誕生秘話」を描く同作ですが、オファーを受けた時のお気持ちはいかがでしたか?
最初に制作統括の櫻井賢さんに見せていただいた企画書には、若き日の乱歩は名探偵である、日本初の名探偵と言われる男に弟子入りを志願していたっていう奇想天外なエピソードと、探偵活劇がやりたい、ということだけがズバッと書いてあって。これは大変な企画だぞと思いました。
オリジナルドラマはずっとやってみたかったものの、今までにない引き出しを開けてやらなきゃいけないジャンルで、期間も短いし…と迷う気持ちももちろんありました。でも、作家が探偵に弟子入りを志願し、その後探偵小説を誕生させる大きな存在になっていく、というストーリーが非常に魅力的で。こんなチャンスは二度とないだろうから、ハードルを1個越えるつもりで挑戦しようと思って挑みました。
■資料を読む中で乱歩先生のことをもっと知りたくなっていった
ーーこれまでも江戸川乱歩作品に親しんでこられていたのでしょうか?
実は乱歩先生に関してはそこまで世代ではなく、有名な「黒蜥蜴」や「明智小五郎」シリーズに触れたことがあった程度でした。なので、私でいいのかな…という思いがあったのですが、櫻井さんから「その方がいい、今までにない乱歩を書いて欲しい」っていうお言葉をいただいて。
不思議な物語を書かれる方なので、当初「この人の心の内を見ていくのは難しいんじゃないかな」と思っていたのですが、資料を読んでいけば読んでいくほど「この人は何を考えているんだろう、この人のことをもっと知りたいな」と思うようになりました。特に大きかったのは、頂いた資料の中にあった乱歩先生の自伝的エッセイ「わが夢と真実」です。この中にあったエピソードはどれが真実でどれが遊び心かわからないけれども、これを自分のエッセイとして書く人はむちゃくちゃ面白いんじゃないか、っていうものが多くて。そういった断片的な情報を繋ぎ合わせて、“平井太郎”という登場人物として再構築していきました。
■ミステリーとしても面白い「探偵ロマンス」だが…
ーー「探偵ロマンス」はミステリーでもありますが、作家として、ジャンルとの相性はいかがでしたでしょうか?
ミステリーは読むのは大好きなのですが、作家としては比較的苦手な方です。
ただ、乱歩先生には登場人物の“心理的な部分での謎”もミステリーとして成り立つ、というところを教えていただいたように思うので、意識しています。
あとはミステリーをたくさん出されている知り合いの編集の方に相談しました。そうしたら、「ハウダニット(どのように犯行に及んだのか=How done it?)」と「ホワイダニット(なぜ犯行を行ったのか=Why dome it?)」の2人を出すとよくなる、と教えていただいて。なので、三郎は証拠を意識して考えるハウダニットの探偵、太郎は動機を考えるホワイダニットの探偵として作っています。
ーーあえてのアナログなアクションシーンも魅力的ですよね。
アクションシーンは、バッキバキのエグいのをやろうと思えばできたんだと思うんです。だけどやっぱり「活劇をやりたい」という思いが私達の中にはあったので、ではどういうふうにしたら活劇っぽくなるんだろう、と考えました。それこそ、「インディ・ジョーンズ」シリーズのような古い映画を研究していったのですが、そんな中で、逆にどこかコミカルな感じがないと三郎が嘘みたいになってしまうのではないか、と思い、今の形になりました。
実は、1番最初に作ったシーンは1話の、歓楽街の茶屋の2階で三郎と太郎がワーッとやり取りをして、窓から三郎が飛び降りるシーンだったんです。あれだけはやりたいと。飛び降りた三郎に対して太郎が「なんてじじいだ!」と言いますが、「探偵ロマンス」は「なんてじじいだ!」を楽しむドラマです。なので、ヒーローものと同じで、「なんてじじいだ!」は1話に1回出てきます。
■それでも光を信じて歩んでいく太郎の物語
ーーセリフの中に「夢」という言葉が多出しますが、意図された部分はありますか?
まずは乱歩先生の「うつし世はゆめ、夜の夢こそまこと」という言葉が自分の中で大きなヒントになった、ということが1つあります。
そして、私はこの物語はくすぶっていた平井太郎という青年が探偵小説家になるまでの話、だと思っているんです。現代人にも通じるところがあると思いますが、情報や人の意思にまみれて生きているような時代で、「自分は作家になるんだ」「何者かになるんだ」と光を信じて歩んでいくっていうのは非常に難しいことだと思うんです。そんな太郎の話なので、「夢」はキーワードとしてたくさん出てきます。
■魅惑の踊り子“お百”の着想は乱歩のエッセイから
ーー第2話では特に世古口凌さん演じるオペラ館の蠱惑的な踊り子・お百が印象的でした。
お百は乱歩先生が「わが夢と真実」の中で書いていた、学生の頃にかわいい男の子と恋をしたけれどもその関係はとても清く、キッスでさえ経験しなかった、というエピソードから着想しました。
“ジェンダーフリー”という部分は注目されるだろうと思いますが、果たしてお百とはどういう存在なのか、“女装している男性”と一言で言っていいのか、非常に考えるところだと思います。そして、お百のような存在はドラマの中でどう活躍させ、どう生きざまを表現すべきか難しく思われることが多いと思うのですが、本来ならその必要はないんだろうなとも思います。なぜなら、お百に限らず、「この人はこういう人だ」とその人の全てを一言で表す言葉はないからです。それぞれに唯一の喜びがあり、哀しみがあり、複雑に絡まりながら生きている。そういうことが描きたかったですね。
ーーお百の歌声は上白石萌音さんが担当されていましたが、とても美しかったです。あの曲はドラマオリジナルのものなのでしょうか?
あの歌は私が書いた歌詞に大橋トリオさんがメロディーをつけてくださったものです。実は、1話でもメロディーは出ていたんですよ。
(制作統括・櫻井氏補足:上白石萌音のキャスティングは音楽担当・大橋氏の提案がきっかけで実現)
■坪田氏が選ぶお気に入りのシーンは…
ーー心に残るシーンが多い「探偵ロマンス」ですが、特にお気に入りのシーンなどがあれば教えてください。
脚本家としては、第1話ラスト近くの、三郎のセリフ「知りたくなったからだ。太郎さんの目に映る世界を見てみたい」までの一連のシーンです。「なんで僕の小説を読みたいって言ってくれたんですか」と聞いた太郎に対して三郎が「そんなことが気になってたのかい」って笑うんだけれども、それに対して太郎が「“そんなこと”じゃない」と真剣に返したとき、きちんと若造に対して「それは悪かったな」って謝れる。体力があって強いからかっこいいんじゃない、白井三郎の魅力が存分に出ているシーンだと思います。そういうキャラクターが書けたこともうれしかったですし、自分が書いたものをおふたりの演技でより良いものにしていただいています。
個人的には第2話でお百が「住良木さん、キスして」と迫るのに対して、住良木が「ロマンスは本当に好きな人としかしちゃいけないんですよ」って返すシーンです。映像を見て、「あー、どうしよう!」って言っちゃいました(笑)。
あとは、森本慎太郎さん演じる潤二が出てくるシーンですね。潤二は、深みを持って演じるのがとても大変な役だと思うのですが、第1話の頭、物語や太郎がどういう扱いをされているのかの導入部分を、およそ10分森本さんの芝居で引っ張ってくださっているんです。森本さんとは以前一度ご一緒したことがあり、ぜひまた一緒に仕事したいと思っていた役者さんだったので、「こういう役をやってほしいんだよな」っていう役で出ていただいてうれしかったです。皆さんほめていらっしゃいますが、声がいいですよね。前半、ちょっとしっとりした感じになるドラマなので、あそこにからっとした、でも馬鹿には絶対に見えないという華のある演技が入るのはありがたいです。
ーーまだまだ続いてほしい「探偵ロマンス」ですが、全4話構成ということで、折り返しを迎えましたね。
全4話と言う話数はきれいに「起承転結」にする必要があり、ゆとりみたいなものを入れづらいので、難しかったです。書ききれなかった部分や、このキャラクターは実はこうなっていくんだ、っていうストーリーまで考えているので、続編のお話も期待しています(笑)。