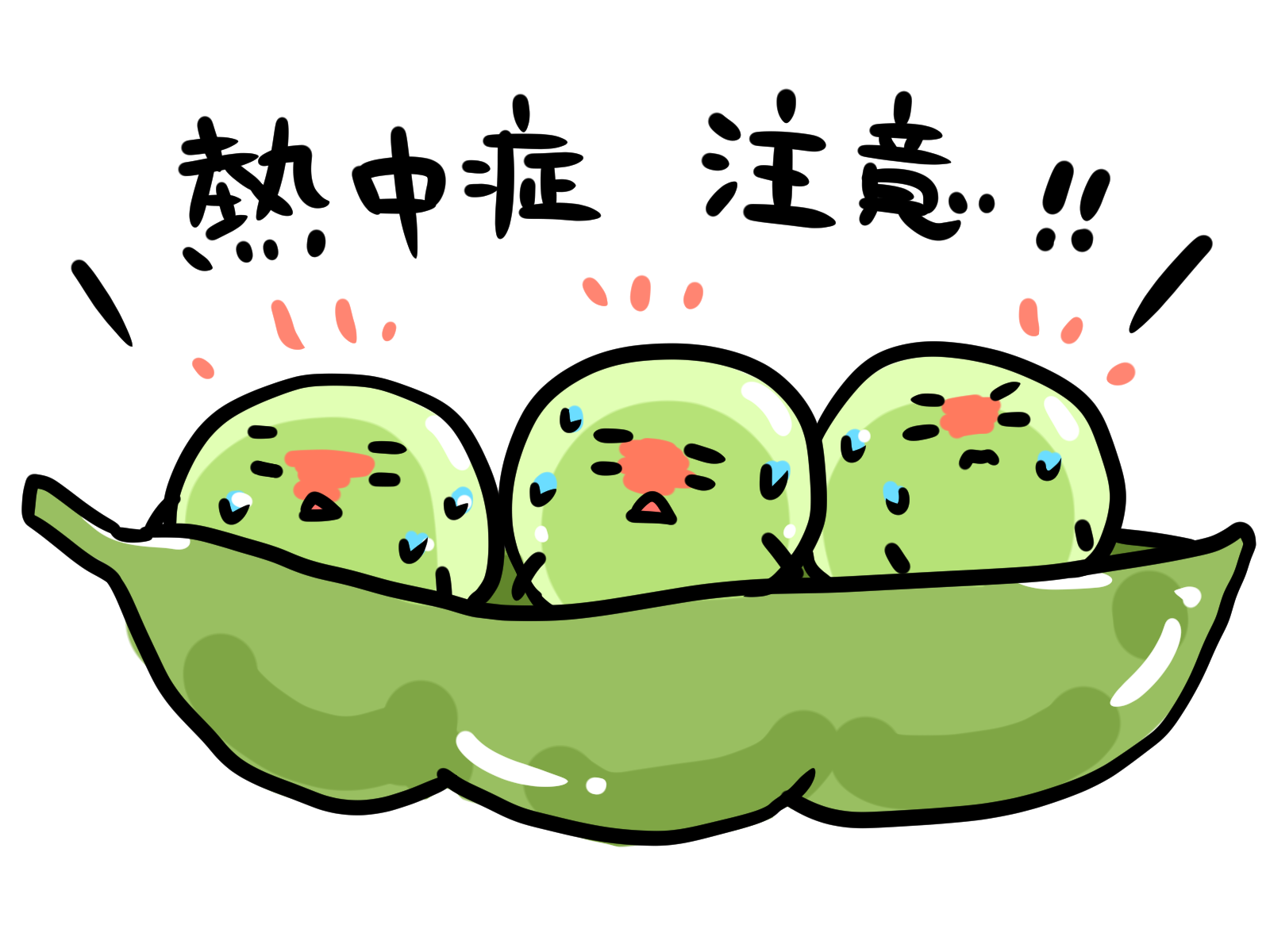2022年もいろいろあった。諸行無常とつくづく思うが、年末の映画館では変わらず、話題作が続々公開されている。というわけで今回の映画評は、韓国のドキュメンタリー「猫たちのアパートメント」と、ジェームズ・キャメロン監督による超大作「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」の2本立て。見終わった後、人の来し方行く末をちょっと考えてみるのもいいかもしれない。(編集委員 恩田泰子)
「猫たちのアパートメント」消える団地に住む250匹の幸せ移住計画
いかにも団地らしいコンクリートの建物の高層階から、はしご車のような装置を使って荷物が運び出されていく。
韓国ソウル市郊外、トゥンチョン複合団地。1980年に完成し、一時期は6000世帯、3万人前後の人々が暮らしていたマンモス団地は、老朽化し再開発が決まった。少しずつ寂しくなる団地の風景の中から浮かび上がってくるのは、猫たちの姿。その団地では、250匹もの野良猫が地域住民と共生していた。
快適な住環境があって、餌やりをする人間がいて、野良猫たちは健康で幸福そう。でも、再開発が始まったらどうなるのだろうか。2017年5月から2年半にわたって撮影されたこのドキュメンタリーは、猫たち、そして団地に住むイラストレーターや作家、写真家の女性たちを中心に進む「トゥンチョン団地猫の幸せ移住計画クラブ(略称・トゥンチョン猫の会)」の活動を追いかけながら、消えゆく団地の姿を記録している。
監督は、チョン・ジェウン。2001年のデビュー作「子猫をお願い」は、男性社会、学歴社会、格差社会の片隅で壁にぶつかりながらも居場所を求める若い女性たちの夢や挫折や友情をみずみずしく描き、時を経てなお愛され続けている傑作だ。その後はフィクションを手がける一方で都市や建築、そこに生きる人々の生活を記録するドキュメンタリーも撮ってきた。生きものとその居場所は、彼女にとって重要な関心事であることは間違いない。
団地が消えれば、そこで重ねられてきた日常が消える。映画の序盤、団地内の薬局前を定位置にしている、コンスンと呼ばれる猫が登場する。律義に店番をしているようにも見えるのだが、ほどなく店は畳まれ、風景は変わる。コンスンは何だか寂しそうにも見えるのだが、それは人間の勝手な想像。猫は、客が来ようと来まいと、そこにいる。
「猫の会」のメンバーは、一匹一匹をイラストや写真などに記録し、それぞれの個性を尊重しながら動くが、カメラもまた一匹一匹を丁寧に見つめる。建物の縁の下に潜り込んだ猫のショットなど、どんなふうに撮ったのかと思う映像も少なくない。映画が終わるころには何匹かの名前を覚えているだろう。そして終幕、団地の建物が消えた後の光景を見つめながら、みんなどこへ行くのだろうと思うはずだ。猫も、そして人間も。
◇「猫たちのアパートメント」(英題:CATS’ APARTMENT)=韓国、1時間28分、配給:パンドラ=12月23日から東京・ユーロスペース(渋谷)、ヒューマントラストシネマ有楽町。以後全国順次公開。
「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」没入感だけでは終わらない
「没入感」という言葉が日本で当たり前に使われるようになったのはいつからか、はっきりは覚えていないが、2009年に公開された「アバター」の3D映像と世界観は、それまでにない奥行きをもって観客の「没入」を誘うものだった。
舞台は22世紀、地球から遠く離れた神秘の星パンドラ。かつて人類は、この星の希少鉱物を手に入れるためのプロジェクトを敢行。人間と、パンドラの生命体ナヴィのDNAを融合させた「アバター」を使って計画を進めようとした。やがて武力で侵略を開始する人間が出てくるが、アバターの操縦者だった元海兵隊員のジェイク(サム・ワーシントン)は、高い知性と精神性を併せ持ち、自然と調和して生きるナヴィの側に立ち、パンドラを守った。
今度の「ウェイ・オブ・ウォーター」はその後の物語。アバターと自らの魂を一体化させ、森に生きるオマティカヤ族の長となったジェイクは、女性戦士ネイティリ(ゾーイ・サルダナ)と家庭を築き、子供たちともども、神聖な森で平和に暮らしていた。が、人類の脅威が再び迫ってくる。一家は森を離れ、海の部族メトケイナ族のコミュニティーに身を寄せる。
見せ場は森から海へ。その風景は、ラッセンの絵や、南国リゾートのようだという声も聞こえてきて、実際そうしたものを思い出したりもするのだが、水の質量や圧をも感じさせる海の世界の描写、そこで生きるユニークな生き物たちと共に繰り広げるダイナミックなアクションは圧倒的。キャメロンが海を舞台にした「アビス」「タイタニック」の人だったことを思い出す。男性ばかりでなく女性たちのきちんと強い姿が描かれる、家族の物語も文句のつけようがない。森の女ネイティリも強いが、海の女ロナル(ケイト・ウィンスレット)も強い。
13年前に覚えた「つくりもの」に対する違和感も、驚くほど薄れた。デジタル技術を駆使した映像に対するこちらの慣れもあるのだろうが、それ以上に、新たな撮影機材や隙のない脚本開発のためにお金と英知が注ぎ込まれているのをまざまざと感じる。映画のキャラクターを演じる俳優たちの表情も、より繊細に伝わってくるようになった感がある。ジェイクたちが育てている14歳の少女キリから、それを演じる70代のシガニー・ウィーバーの面影が見え隠れするのも面白い。
もっとも、ただ没入させるだけの映画ではない。見ているものをふっと現実に引き戻すのは、人間の破壊的な愚かさを見せるシーン。身体能力を増強するスケルスーツで武装した司令官の女性アードモアの姿は恐ろしくてどこか滑稽。他者への畏怖を忘れた利己的な生きものがそこにいる。映画を見ている間、多くの観客が心を寄せるのは、無論ナヴィたちのはずなのだが、日常に戻った時の自分のふるまいを省みると、ちくりとしたものが残る。そうした部分も含めて、やはり豊かな、
◇「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」(原題:Avatar:The Way of Water)=米国、3時間12分、配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン=12月16日から全国公開。