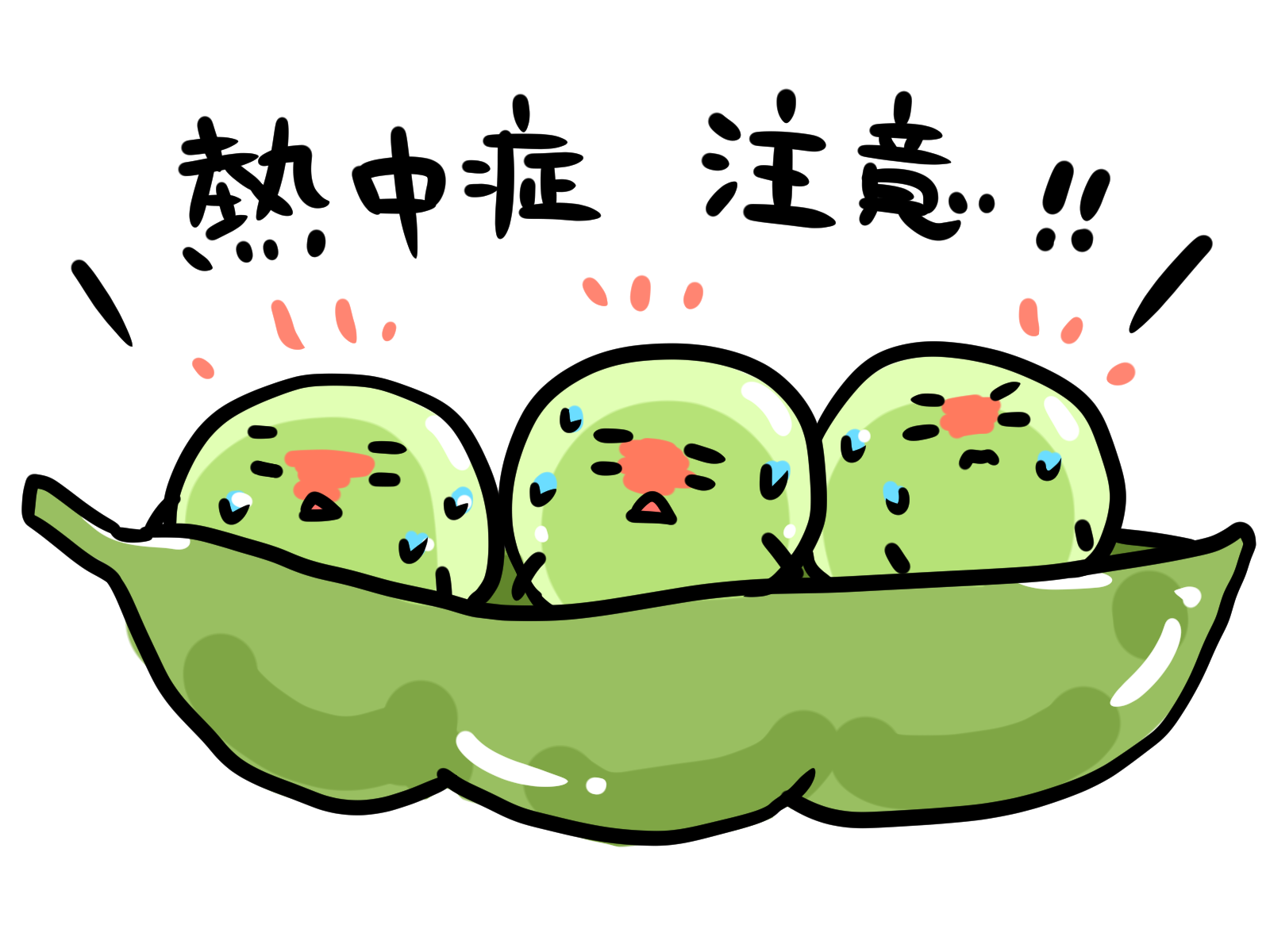人の孤独とつながりをコロナ禍を背景に描き出す映画「ワタシの中の彼女」(11月26日から、東京・渋谷のユーロスペースほか全国順次公開)は、四つの異なるストーリーからなる短編集。注目作への出演が続く
「コロナ禍は絶対に描きたいと思った」
中村は、2006年に劇映画「ハリヨの夏」で監督デビュー。フィクションとドキュメンタリーの両方で、人と社会を映してきた。「コロナ禍は絶対に描きたかったんです。全世界の人が経験していることですし、孤独とか、人のつながりを考えるきっかけでもあったし」と言う。
本作の第1話になっている「4人のあいだで」を撮ったのは、20年7月。「リモート」での「公園飲み」に興じる40代の男女3人(菜葉菜、占部房子、草野康太)が話すほどに、そこにはいない1人の女性の存在が色濃く浮かび上がってくるというストーリー。当初は独立した短編として制作したが、21年の大阪アジアン映画祭でJAPAN CUTS Awardスペシャル・メンション(特別表彰)に輝いたのをきっかけに企画が発展。菜葉菜が「4話4様」のキャラクターを演じる今作が生まれた。
カーヴァーの短編小説のように
「1人の女優がいろんな役をやる映画って、意外とありそうでないな、と思ったんです」と中村。「長編だと難しいけれど、短編集ならばできるな、と。菜葉菜さんのいい意味での『年齢不詳さ』も生かせると思いました」と話す。「不思議なほど、いろんな役に染まれる人。役者さんによっては、普通の人を演じても、その人自身の個性が前に出すぎてしまって普通に見えなくなってしまったりするのだけれど、菜葉菜さんの場合、そうはならない」
21年秋に残りの三つのストーリーを撮影した。「短編なので、長編みたいに大きなアドベンチャーは描けないけれど、誰かとの出会いでちょっと何かが変わる、ということを描いてみたいと思いました」。イメージしたのは、上質な短編小説のように充実した「読後感」をもたらす映画。米国の作家レイモンド・カーヴァーや、向田邦子の短編小説がもともと好きなのだという。
みんな、いろいろ思って生きている
菜葉菜が演じるのは、第1話では専業主婦、第2話「ワタシを見ている誰か」(共演・好井まさお)ではフードデリバリーを多用する在宅勤務中の30代女性、東京・幡ヶ谷のバス停でホームレス女性が死亡した事件に着想を得た第3話「ゴーストさん」(同・浅田美代子)では風俗勤めの20代、そして第4話「だましてください、やさしいことばで」(同・上村侑)では、オレオレ詐欺の標的にされる40代の盲目の女性だ。
どの女性も、話が進むにつれて第一印象とは異なる顔を見せ始める。現実世界の人間がそうであるように。
自分が演じた人物たちについて菜葉菜は、「何かを抱えているけれど、ちゃんと今を生きている女性たち」だと言う。「その弱さと強さの両面がちゃんと見えるところが、それぞれの女性たちの魅力であり、監督の描く女性の魅力だと私は思う。そうした面がいろいろ見られるので、すごく共感するし、無理なく、面白く演じさせてもらいました」。もともと、女性のさまざまな面がきちんと描かれている映画が好きだという。「例えば、若尾文子さんが出ている増村保造監督の作品とかでも、単なるいいお母さん、奥さんだけじゃない部分がちゃんと描かれている。きれいで優しいだけじゃなくて、いろいろ思って、強く生きている。人によって違った顔を見せたりする。何か、そういうのを見るのが好きなんですよね」
人が人と出会うということ
なおかつ、「そうした人も、誰かとの出会いによって変わっていく」ことが映し出されているのが本作のポイントだと菜葉菜は言う。「コロナ禍で人と接する機会が減ってしまったけれど、やっぱり人は人と出会って変わっていけたり、一歩踏み出していけたりするというようなことが、それぞれのストーリーの中に描かれている」
そんな物語の強度を増幅するのは、演技のアンサンブル。中でも第3話での浅田美代子との2人芝居は強い印象を残す。浅田が演じるホームレスの女性と、菜葉菜が演じる年下の女はいずれも、かつて女優の夢を追いかけていたという設定。2人が「芝居」を通じて心通わせるシーンは人の尊厳、女の尊厳を感じさせ、見る者の心を揺さぶる。「浅田さんが私の芝居を受け止めて、一つの作品としてどうあるべきかみたいなことをすごく考えて、まとめてくださった感じがあったので、私は自分がやってみようと思うお芝居をぶつけてみることができました」と菜葉菜は振り返る。
ストーリーの着想源となった幡ヶ谷の事件の被害者は、コロナ禍で苦境に陥り、路上での生活を余儀なくされていた。中村は、事件をひとごとではないととらえる若い女性の声をテレビ番組で聞いたことなどをきっかけに、この話を作ったという。立場や世代が違っても同じ思いを抱えた女たちの姿を浮き彫りにしていくために。そもそも1人の女優がさまざまな女性を演じるという仕掛けは、全編を通して、そうしたものを描き出すためでもあったという。「出発点は現実ですが、若干、ファンタジーに救われるみたいな構造にしています」
ファンタジーを裏打ちするもの
ただ、そのファンタジーがうそに見えないよう、心を砕いた。菜葉菜は演じることの「責任」も感じていたと明かす。例えば、盲目の女性の物語である4話に関しては、2人で一緒に目の見えない人たちの話を聞いたり、視覚障害者の案内で暗闇を体験する催し「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」に足を運んだり、リサーチを重ねた。
その上で、中村があえて入れた表現がある。菜葉菜が相手役の上村の顔に触れて造作を確かめるシーンだ。2人が話を聞いた人たちは、そうした行為は「まず、しない」と教えてくれたそうだが、中村は「他者に触ることに恐怖心があるコロナ禍の中で、信頼関係が生まれていないとできない行為」として描いたという。
信用できるまっすぐさ
菜葉菜は本作について、「(監督が)一緒に作ろうって言ってくれて、みんなで作った感じはある」と言う。「(2話で共演した)好井さんとかも脚本の段階で結構、アイデアを出してくださったり……。ただ、ほぼ採用されない。監督は最後まで自分を貫いた」と笑う。「でも、そういうまっすぐさは信用できるなって思います」
2人で最初に会った時、中村が菜葉菜に話したのは、年齢を重ねた女性を主役にした日本映画がもっと「あるべきだ」ということ。菜葉菜のほうも「年を重ねていく中ですごく感じていた」ことだったという。「海外の映画のように、いろんな面、中身を持った大人の女性を描く邦画を見たい、そうした作品に出たいと思っていたので、『あ、こういう監督がいてくれてよかった、一緒に作品ができたら幸せだな』と。本作で「それが実現できてすごくうれしかったです」。中村も「そういうのを、もっとやりたいですね」。はい、もっと見てみたいです。(敬称略)
◇中村真夕(なかむら・まゆ)=2006年、「ハリヨの夏」で映画監督デビュー。フィクションとドキュメンタリーの両方で活躍を続ける。22年3月公開の心理サスペンス「親密な他人」では、コロナ禍を生きるシングルマザーとオレオレ詐欺に手を染める青年の奇妙な関係を描いた。ドキュメンタリー作品に「ナオトひとりっきり」など。
◇菜葉菜(なはな)=2005年、映画「YUMENO」で本格的に女優デビュー。以後、「ヘヴンズ ストーリー」「百合子、ダスヴィダーニヤ」など数々の話題作に出演、評価を高めてきた。22年は圧倒的な演技を見せた映画「夕方のおともだち」をはじめ、「クボタ」のCMやNHK夜ドラ「つまらない住宅地のすべて」などでも注目を集める。